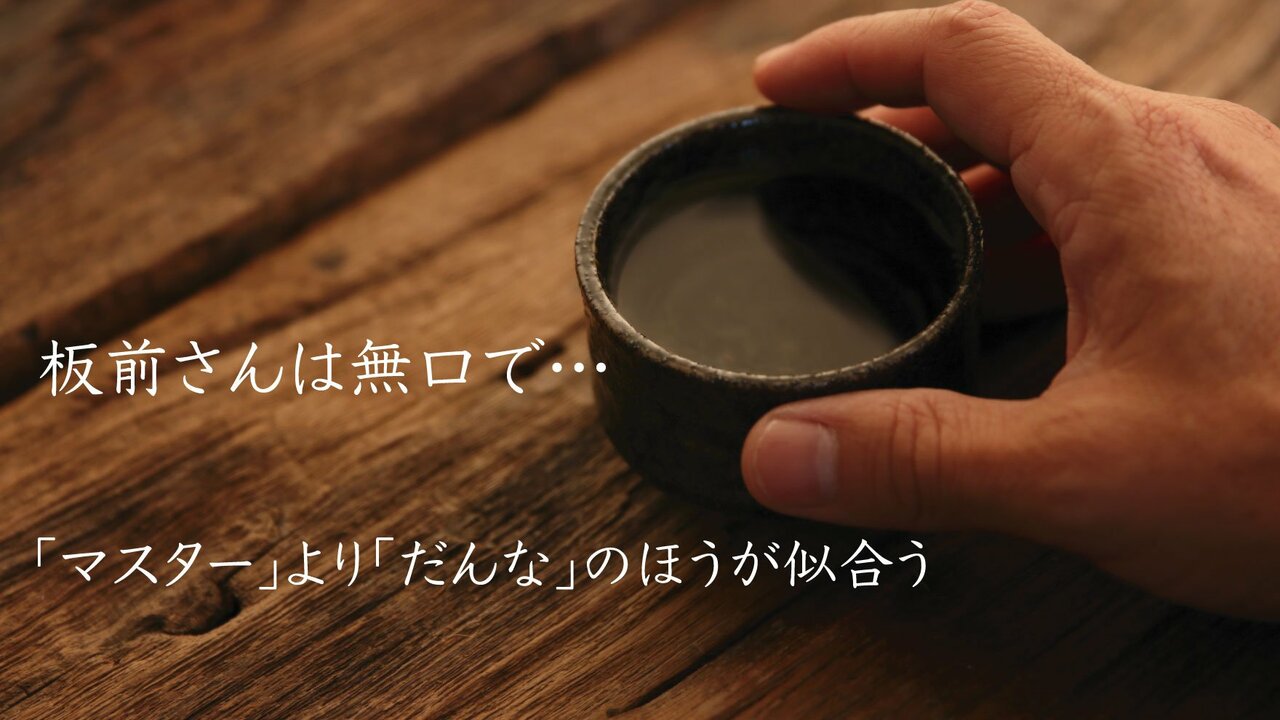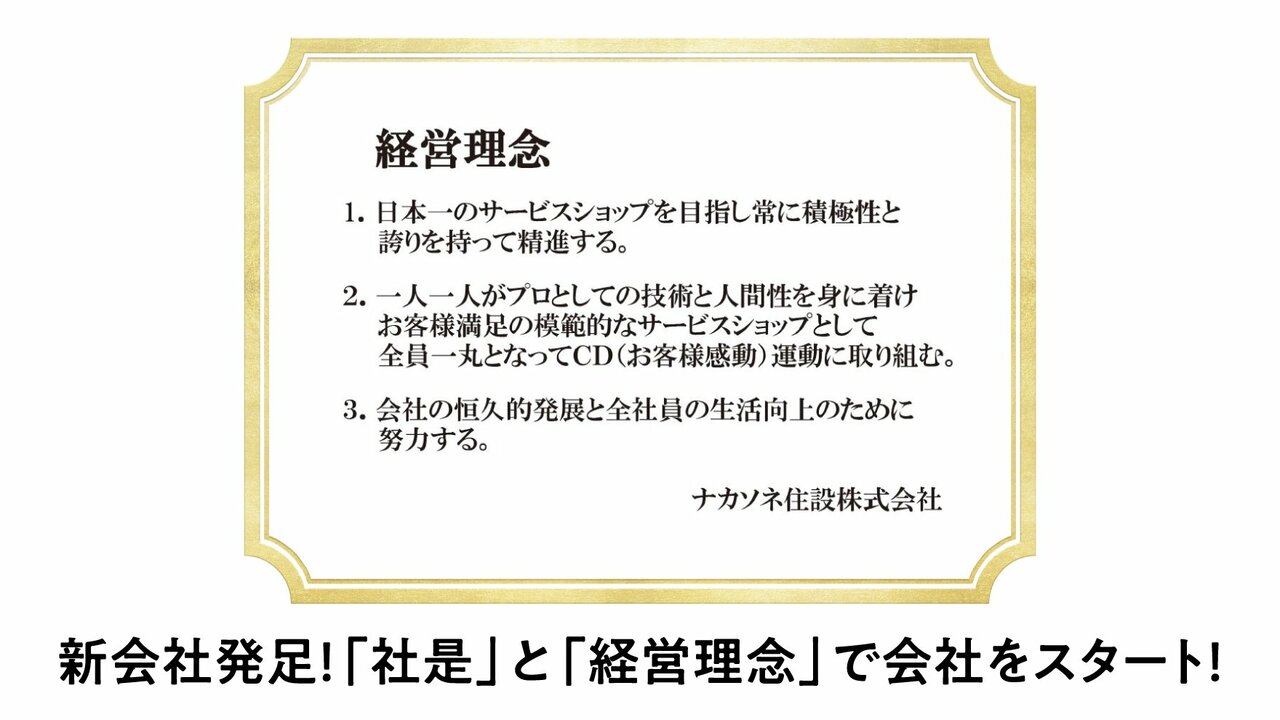第二章 ゼロからのスタート
父の跡を継ぐ
九州火力建設株式会社(現在は西日本プラント工業株式会社)では、発電所という大きなプラント建設に携わることができ、配管、機器の据え付け、溶接、鳶仕事、工程表や図面作成など、いろいろな技術を学ぶことができました。二年ほどしか在籍しませんでしたが、後の私の仕事に貴重な経験として生かされることになりました。
「もはや戦後ではない」と言われ始めたころでしたが、一九五五(昭和三十)年ごろから、戦前の経済水準を超えたという報道がされていました。一般の労働者、中小企業などの賃金はまだまだ低く、当時流行っていたフランク永井の歌に《一万三千八百円》というものがありました。
一般サラリーマンで一万三千八百円もらえたら、いいほうだったと思います。給料が安いために、残業をしないと生活ができませんでした。作業員はみんな、徹夜残業を進んで行っていました。家族がいて、単身で来ている人も多く、残業しないと食べていけませんでした。
私もやっと日当四百円になっていましたが、残業代を入れても月に手取りで一万二、三千円の稼ぎでした。寮生活だったので、食べるほうは心配ないのですが、それでも若いので腹が減ると、町に出ては回転饅頭やラーメンを食べることが楽しみでした。
少ないながら、月に千円、二千円と貯金をしていました。ある時、母が寮まで訪ねてきて、「借金の支払いができないので、少しお金を貸しておくれ」と言うのです。私はもらったばかりの少ない給料の中から七千円を母に渡しました。それでも足りなかったと思いますが、母は「ありがとう」と言って、うつむいて涙ぐんでいました。
そして母は、「実はお父さんが朝から酒を飲んで、今はほとんど仕事ができなくなっているのよ、会社を辞めてうちに帰ってお父さんの仕事を手伝っておくれ」と言うのです。
給料は安いけれど、やっと仕事も面白くなってきて、会社も将来を期待してくれている時でした。私もどうしていいかわかりませんでしたが、会社の仕事が終わってから、家まで汽車で片道一時間半かけて帰り、父の仕事を夜中まで手伝い、翌朝早く会社に出勤をしていました。でも、そんなことが長続きするはずがありません。
体力的にも限界になり、上司に事情を話して、退職することになりました。当時は他社から若い社員の引き抜きなどがあったため、私も引き抜きをされているのかもしれないと思われたのか、上司が我が家を訪ねてきました。
父の様子や仕事のことを聞き、「そのような事情ならやむを得ないですね。またいつでも会社に戻っていいからね」と言ってくれました。
ここでも母の思いが私の方向性を決めました。私が父の仕事を事実上引き継ぐことになりました。