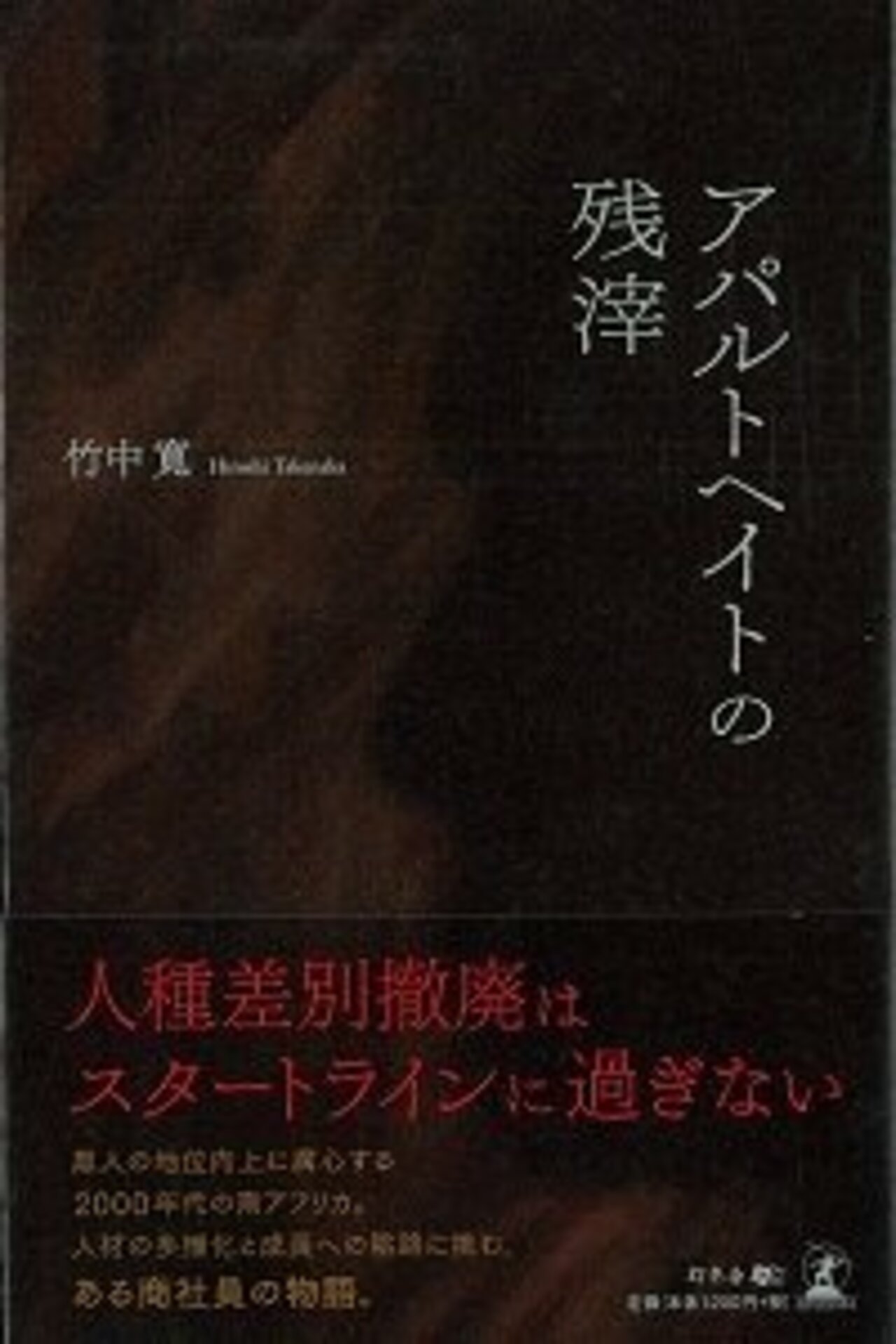「私にはこのジンバブエで事業をやらせて頂いている見返りとして、きちっとこの国に税金を納める義務があります。従業員の生活を守るために給料を支払わなければなりません。それに将来のための投資や、株主である南アフリカのマキシマ社へ配当もしなければなりません。
しかし現状ではとても無理です。稼いでも稼いでも価値がどんどん下がっていくのです。だから対策を立てる必要があります。そのために本当のことが知りたいのです」
必死でクバネ氏の本音を引き出そうとする。
しばしの沈黙の時が流れた。
「タカクラサン……」
と、クバネ氏は左右を確認した。ここは彼の自宅兼オフィスだから安全な筈だが、まわりを確認するのは外交官であった習性なのか。
庭の方から犬の吠える声が聞こえた。
クバネ氏は窓の方に行き、庭を見渡してカーテンを閉めた。高倉はクバネ氏の本音が聞けると期待した。
「タカクラサン……」
クバネ氏は何かいおうとして再びためらった。そしてようやく口を開いた。
「我々は苦労の末に、一九八〇年にイギリス領南ローデシアから独立してジンバブエとなりました。そして白人が占領していた土地を没収しました。元々は我々の土地ですから当然です。それで多くの白人がこの国から去りました。しかし広大な土地を前にした我々黒人には農業技術や経営の知識経験がなかったのです。
アフリカ有数の農業国であったこの土地は荒れ果て、食糧不足となりました。それが現在のハイパー・インフレの一つの要因です。でもこれは黒人農民が技術を習得すればおさまることです。今は過渡期なのです。
元々我が国民は、あなたが今住まれている国とかその他まわりの国の黒人よりも教育程度は高いのです。必ずうまくいきます。とに角、白人に出来た作物を我々黒人が作れないはずはないと信じています」
高倉はクバネ氏が意地を見せるように説明するのを黙って聞いていた。そしてこれは建前論だと確信した。
引退したとはいえ、元外交官が現政権に批判的なことを言うのは無理だろう、壁に耳あり、なのかも知れないと思った。
「タカクラサン、私の話は以上です。理解して下さい」
「わかりました、クバネさん、ありがとうございました」
彼はハラレのクバネ邸を去ると同時に、このマーケットからの撤退を決断していた。