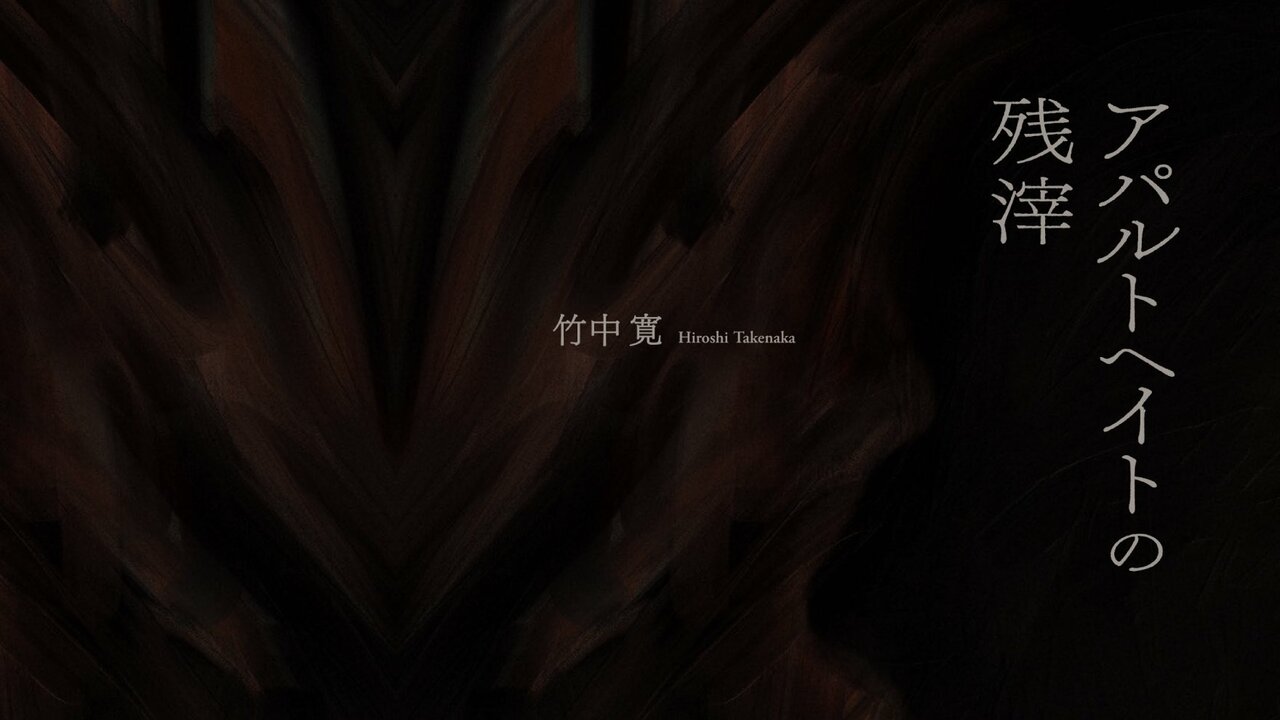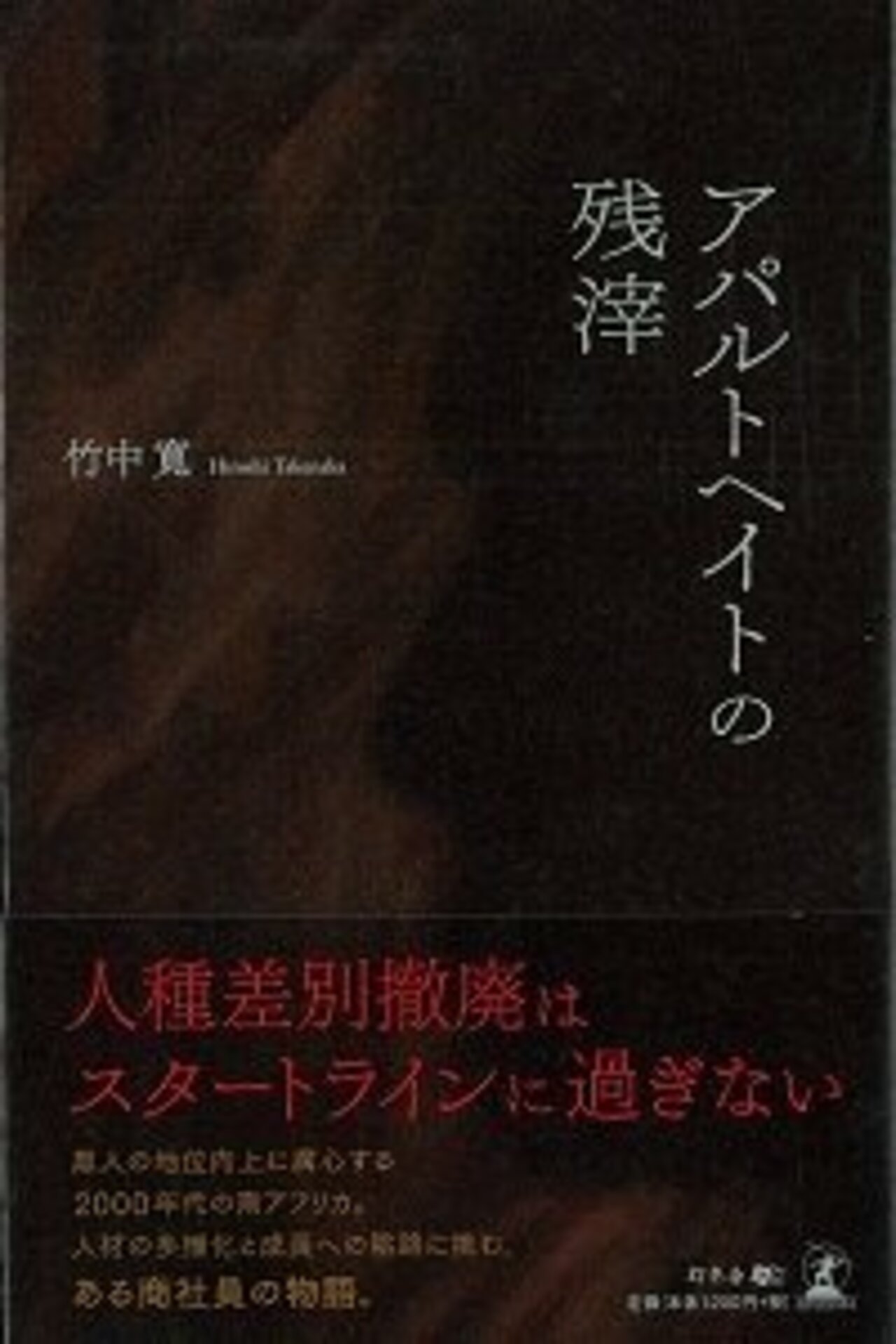六
息子夫婦とのつかの間の再会の半月後、高倉はジンバブエの首都ハラレにあるリッキーの父親の家を訪問した。
郊外の緑の多い閑静な、いかにも高級住宅街という地域の一角にクバネ氏の家はあった。
独立前は英国人が多く住んでいたことを容易に想像させるたたずまいである。
リッキーから話を聞いていたようで、クバネ氏は高倉を快く受け入れ、大きな屋敷の一室に通した。彼はそこをオフィスとして使っているそうだ。
自己紹介をすると、それもリッキーから聞いていたらしく、クバネ氏はいかにも知っているという顔で「うんうん」と頷いている。
年齢は六十過ぎだろうか、縮れた髪には白いものが混じっているが目は鋭く光っていた。
型通りの挨拶と子どもたちの話題のあと、最も関心のあるジンバブエの経済状況に切り込んだ。
同席していたリッキーの母親は、気を使ったように席を外した。
「クバネさん、私が経営している南アフリカのマキシマ社は、このジンバブエにも進出しています。そこでお聞きしたいのですが、この国の政治、経済の現状と将来展望はどうなのでしょうか?」
クバネ氏は少し考えてから、
「白人を排除し、我々黒人の代表であるムガベ大統領の強いリーダーシップのもとで、政治も経済も大変うまくいっています」
と、わざとらしく胸を反らせて答えた。
彼があえて堂々とした仕草を見せたことに、高倉は不自然さを感じた。
「クバネさん、しかし数字を見ると、インフレ率は数百%になっており、ジンバブエ・ドルも米ドル対比で大幅に下落しています。これで順調といえるのですか。正直にいって頂ければありがたいのですがハイパー・インフレは収まると見ておられるのでしょうか?」
息子の友人の父親という気安さも手伝って、少し強い口調となった。
「タカクラサン、それは一時的なものです。つまり産みの苦しみといいましょうか」