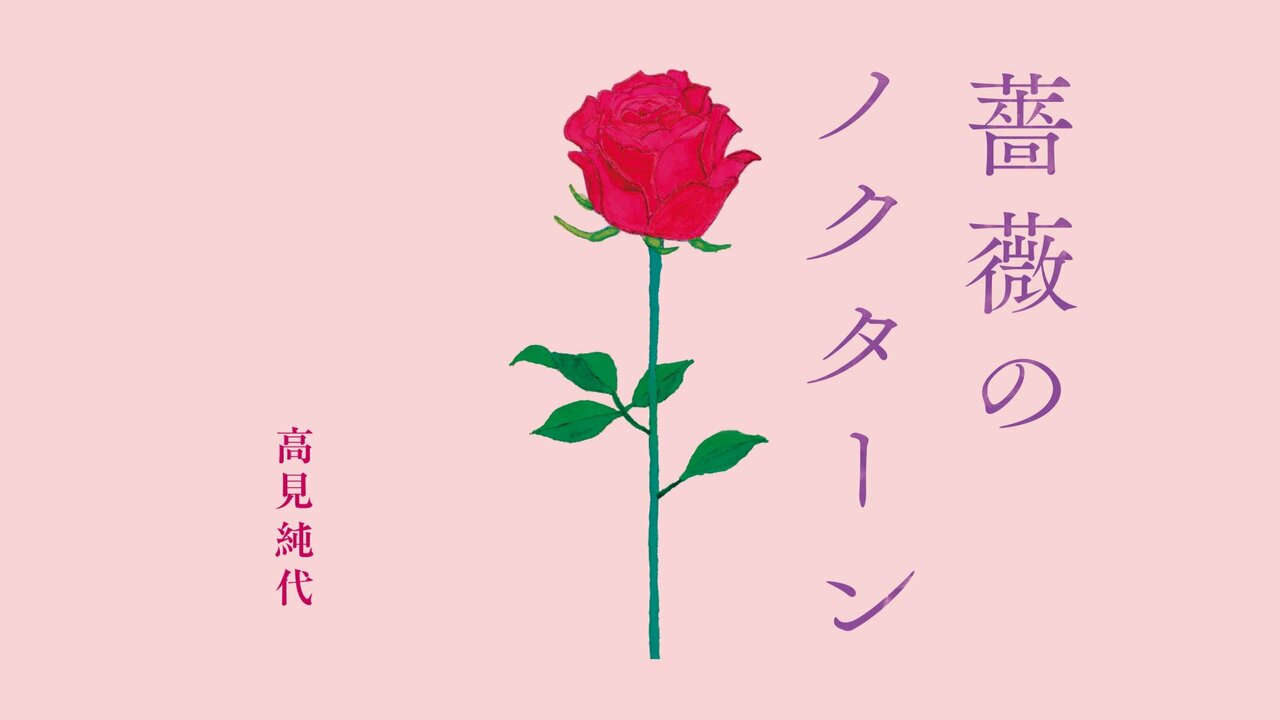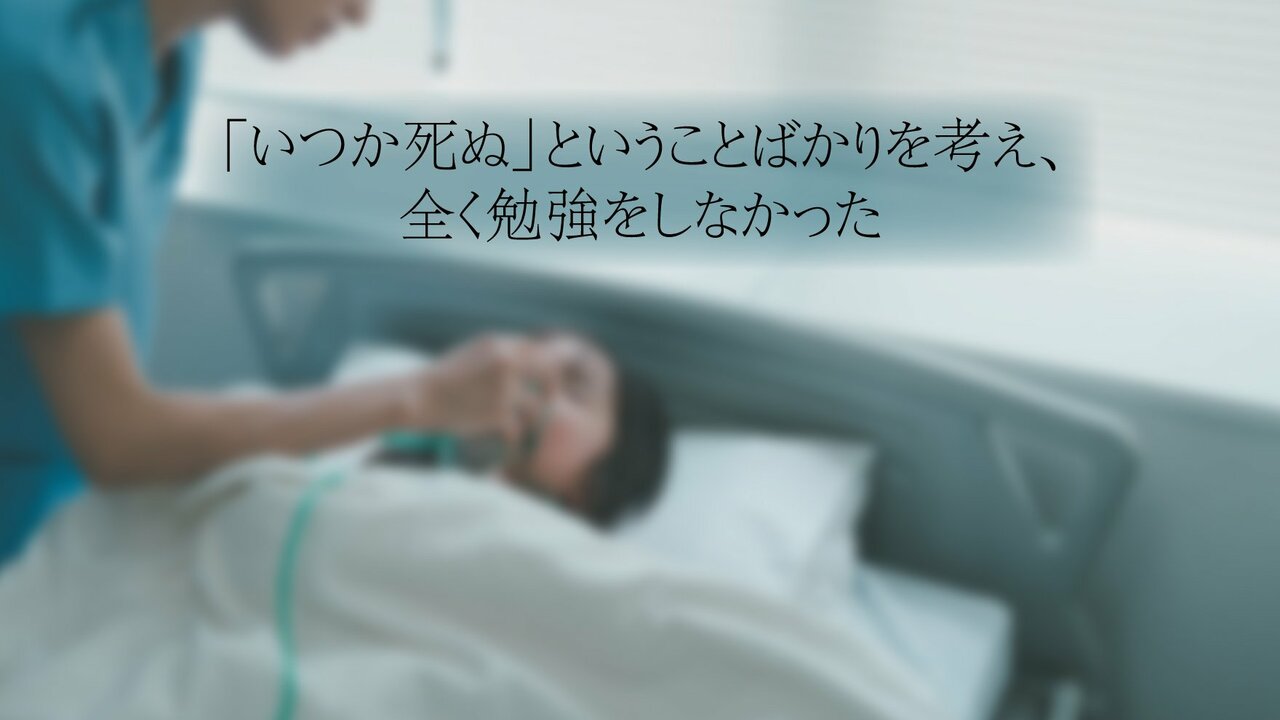二
澄世には青春がなかった。八歳の時に肺炎にかかり生死をさまよい、命だけはとりとめたが、その後ずっと病弱だった。
肺炎の時の事は、前半しか覚えていない。風邪だと思い風邪薬を飲んでいるのに一向によくならず、そのうち四十度を超す熱が続き、薬を吐き出すようになり、小児科の病院をたらい回しにされた。
結局、父の親友のつてを頼り、町の小さな富田外科に、やっと入院できた。幼い澄世は注射が嫌だったが、息があまりに苦しいので、早く楽になれるならと思い、自分から「ちゅうしゃをしてください」と先生に腕を出したのを覚えている。そこからは、もう気を失った。
周りの話によると、病院の前を通ると、二階の病室の窓から、澄世のゼーゼーと喘ぐ息の音が聞こえたという。澄世が気がついたのは、十一月の始めで、入院してからひと月後だった。
ぼんやり目をあけると、白い天井がまぶしく見えた。そばに居た看護婦に「澄世ちゃん!?」と呼びかけ体を揺すられ、パチリと目を開いた。
看護婦が跳んで出て廊下を走って行った。先生がニッコリと覗き込まれ、母がジッと澄世を見つめ手を握り、その横で父が喜びのあまり泣いていた。一つ上の兄は学校に行っていていなかった。
「澄世ちゃん、どう?」と富田先生が言ったので、何が何だかわからないけれど、自分の体の感覚をあちこち確かめてみた。左耳がカッと熱かった。手で耳をさわってみると、何かベトベトと汁がついた。先生が「中耳炎です。高熱で鼓膜が破れたんでしょう」と両親に説明した。
看護婦に助けられ、ベッドに座った。湯の入ったたらいが出され、手を洗ったら、白い粉がいっぱい浮いた。垢だった。次に「立ってみようか?」と言われ、足にスリッパを履かせてもらい、床に足をつけ、ベッドから立った。
みんなが見守り、喜んでいるのがわかったが、二、三歩歩き出しただけで、よろめいてパタンと倒れた。澄世は自分に大変な事が起こったのだと、やっと理解した。
澄世が苦しがって、酸素マスクを手ではずすので、富田先生は小さな個人医院にもかかわらず、澄世を助ける為に、酸素テントを導入し、酸素ボンベを何本も使ってくれ、夜も殆ど付きっきりで寝ておられなかったと聞いた。
澄世が診察室まで歩けるようになった時、富田先生は胸のレントゲン写真を見せてくれ「真っ白でしょ! 肺炎、マイコプラズマでした」と言われた。澄世は(マイコプラズマ、マイコプラズマ……)と心の中で繰り返し、自分を苦しめた相手を覚えておこうと思った。