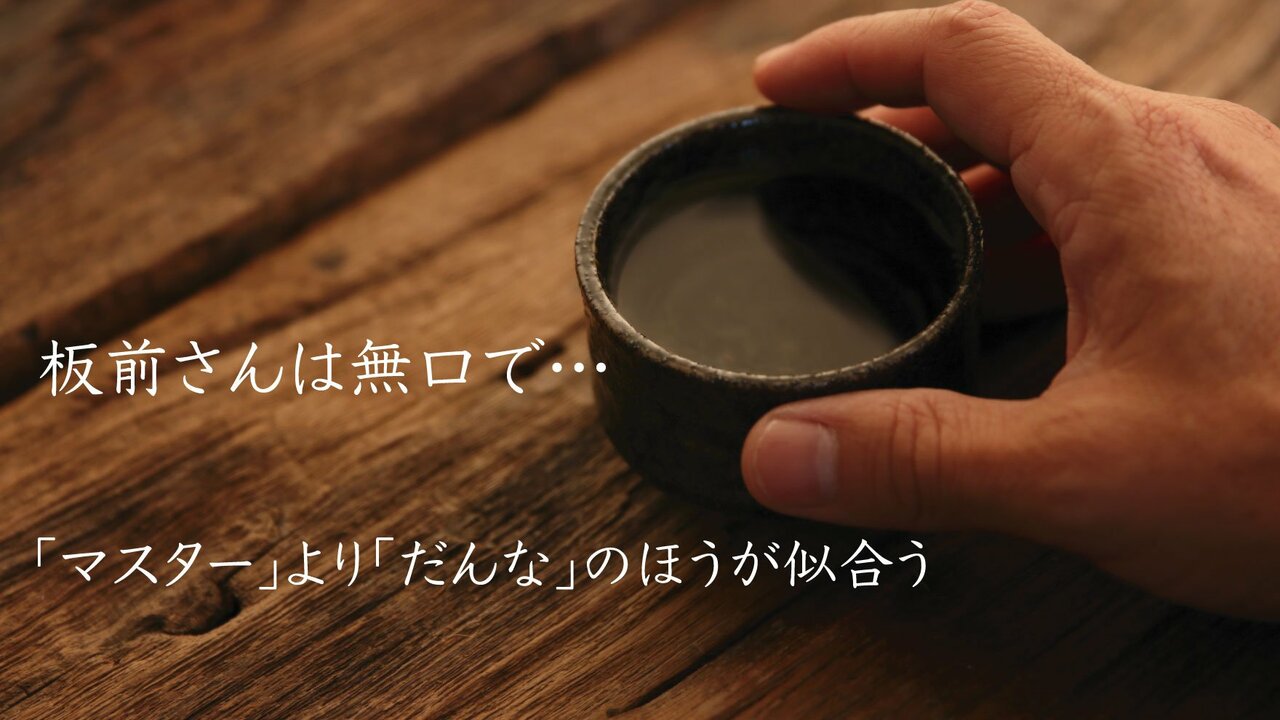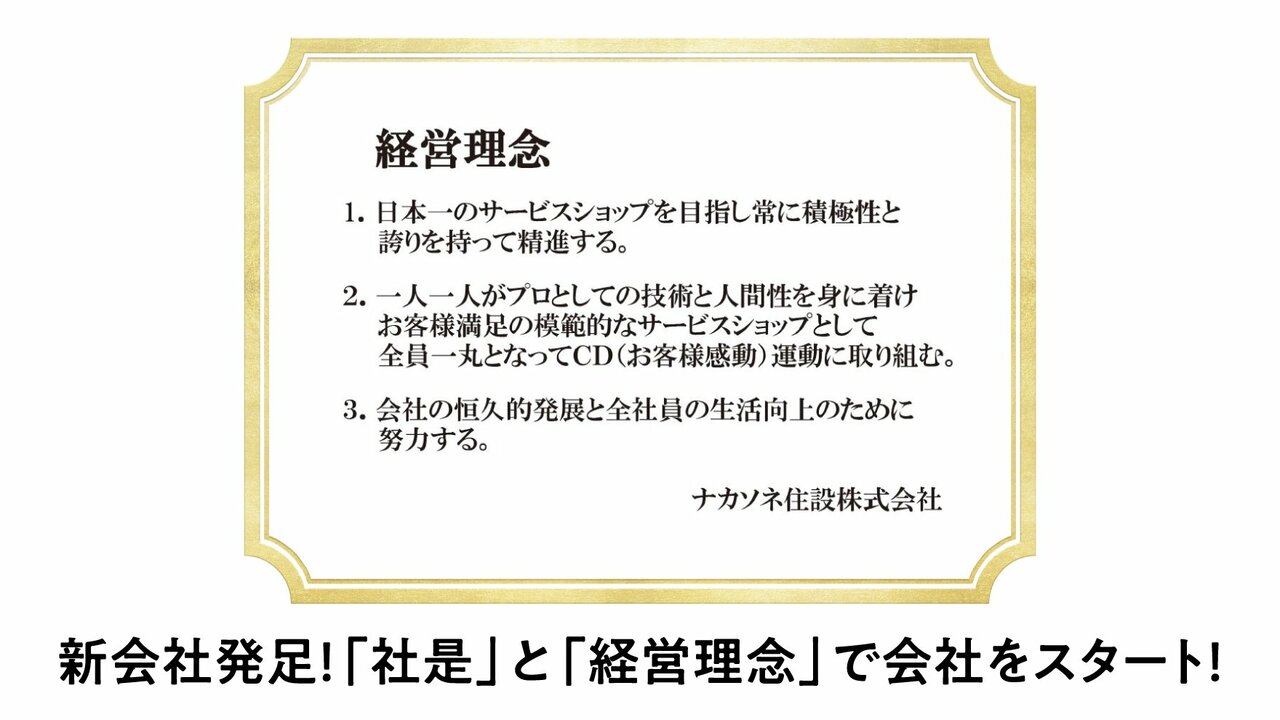第一章 ほうりでわたる
文子おばさんの狐憑き
同居していた文子おばさんもすでに結婚して、二人の子供がいました。文子おばさんの夫、私からすればおじさんは、遠洋漁業の漁師で、一度漁に出るとしばらくは帰ってきませんでした。
おばさんたちは、我が家の横にある物置を少し改造した、とても粗末な部屋で暮らしていました。隙間だらけの板壁に、海からの風が吹きつけます。それでも仕方がなかったのです。当時は誰もが満足な家に住めるほど豊かではありませんでした。
ある時、三歳になったおばさんの上の子供、私の従妹にあたる英子が小児結核にかかってしまいました。町の小児科で治療を受けていましたが、結核に効果があると言われていた抗生物質のストレプトマイシンも開発されたばかりで、値段も高く、たびたび注射できるものではありませんでした。
英子が弱っていく姿を見るのは不憫でたまりませんでした。輸血が必要ということで、私の血液を採取し輸血したこともあります。おばさんは私に「ごめんね、ありがとうね」と言って涙を浮かべていました。
必死の看病もむなしく、英子は眠るようにして短い生涯を閉じました。
簡単な家族葬も済ませた数日後、文子おばさんの様子がおかしくなりました。夜、蚊帳の中で勉強をしていると、引き戸一枚で隔てた部屋からおばさんが出てきて、「時計の音がカチカチして眠れないから止めて」と言うのです。私は恐る恐る柱時計の振り子を止めました。その時のおばさんの目はフクロウのようにぎょろっとして、目が据わっていました。その姿にゾッとして、血の気が引いていくのを感じました。
その翌日のことです。文子おばさんが英子の下に生まれた一歳の男の子を抱いて、刈り入れ前の田んぼの中を、獣が跳ねるようにぴょんぴょんと走って、近くの墓場のほうに行くのです。母が追いかけて家に連れ戻しましたが、髪は乱れ、形相は人間の相ではありませんでした。娘を亡くしたショックから来る精神錯乱状態でした。
母が近所の人に相談すると、おばには「狐が憑いている」と言われました。狐憑きを落とすお祈りをする祈禱師を紹介され、それから毎晩のように数人が集まってお祈りが始まりました。おばさんはますます荒れ狂い、飛び跳ねて回ろうとします。大人二、三人で押さえ込んでも、ものすごい力で跳ね返そうとします。