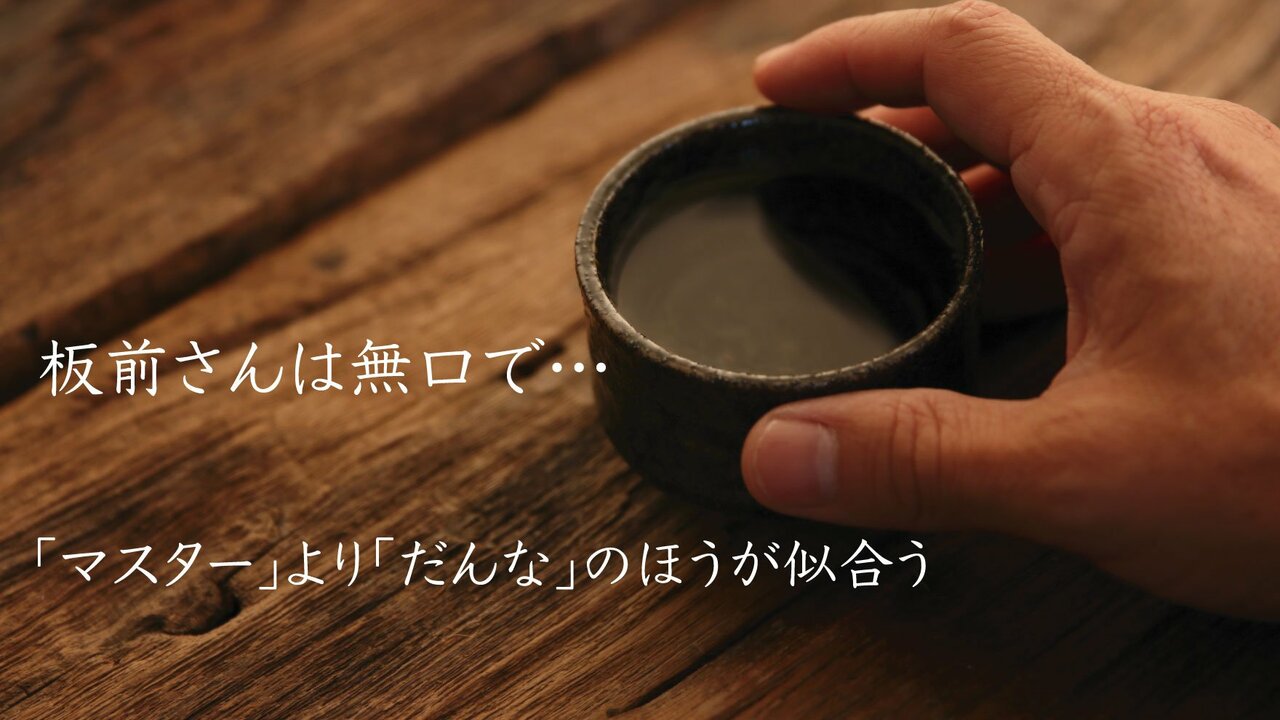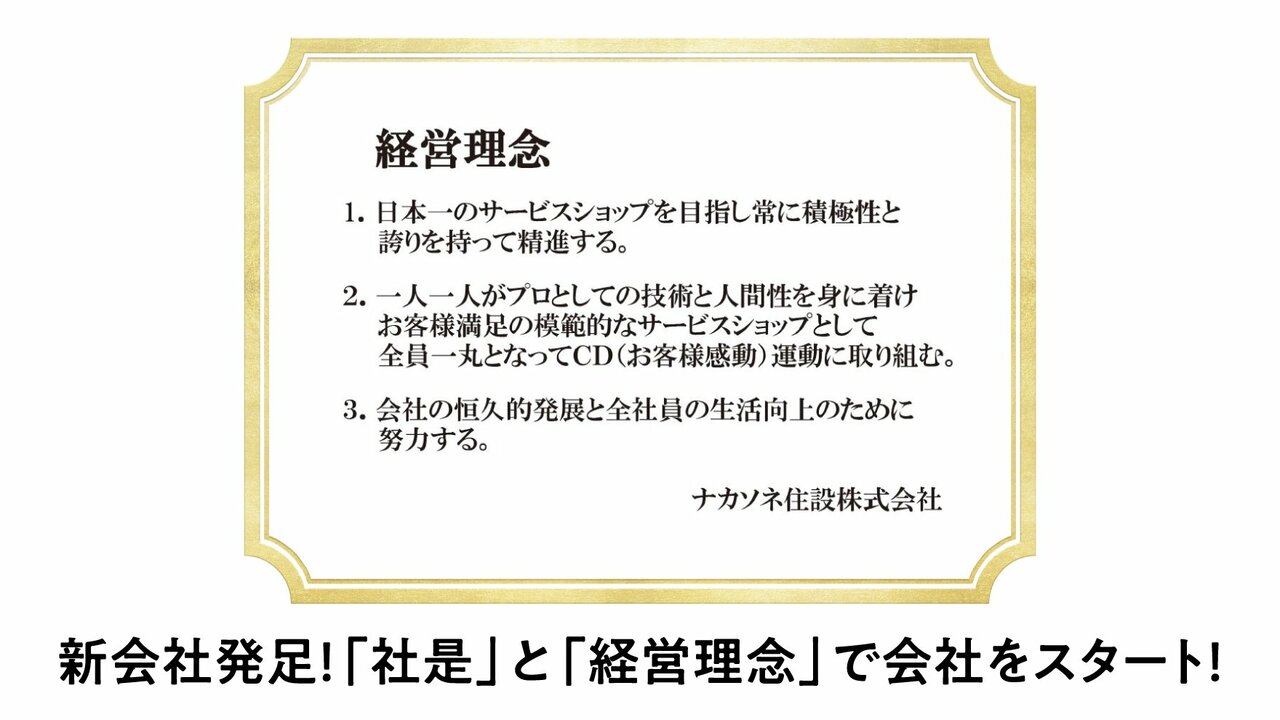そのころ、父の仕事も忙しくなり、漁師たちからは、捕れたての魚をもらったりして、大変によくしてもらいました。しかし父は根っからの職人で、商売はへたくそでした。
修理した代金を集金に行っても、漁師はなかなか払ってくれません。宵越しの金は持たないというのは江戸っ子の代名詞のようですが、漁師も漁のある時は気前がいいのですが、漁のない時期にはお金を払ってくれないので、我が家はいつも火の車でした。
このころには兄弟姉妹も六人になり、六人とも学校に通い始めると、生活が苦しくなりました。ある時、役場の税務課の人が税金の取り立てに来ましたが、支払うお金がありませんでした。
「支払いができないのなら仕方がありません」と言って、タンスや家具など、たいした代物もないのに、差し押さえとして赤紙を貼っていくのです。母は涙を流しながら、「もう少し待ってください」と懇願していました。
またある時は、電気代が払えないということで、電力会社から来たと思われる紺色の作業着の電工屋に、家に引き込まれていた電線をペンチで切られてしまい、幾日も電気のない食卓で食事をしました。ローソクを囲み、ぼわあとした灯りが、みんなの沈んだ顔を照らしていました。
もっとも冷蔵庫も洗濯機もテレビもエアコンもない時代で、照明だけのために電気を使っていましたので、ローソクさえあればなんとか我慢できたのです。私のハングリー精神は、このころから心に刻まれたのかもしれません。
母も生活の糧にと、海に行き、あさり採り、天草や青のりなどの海藻採りをしながら家計を支えていました。子供たちもあさり採りにはよく行き、弟は子供ながら採ったあさりを早朝の町に売りに行っていました。
近くの製薬工場では、ボイラーで焚いた石炭の燃焼かす(石炭ガラ)を、工場の人がトロッコに積んできて捨てる場所がありました。その石炭ガラに水をかけ、湯気が上がっている中からコークスを拾い出していくのです。
近所の大人や子供たちが潮干狩り用の熊手などでコークスを選り分け、それを拾い集めて持って帰り、七輪の燃料とするのです。火力が強く貴重な燃料になり、家計の助けとなっていました。
終戦後は砂糖不足のため、その製薬工場では砂糖の代用品としてズルチンやサッカリンを製造していました。しかし、がんになるなど毒性が指摘されて製造禁止になり、次第に市場から消えてしまいました。