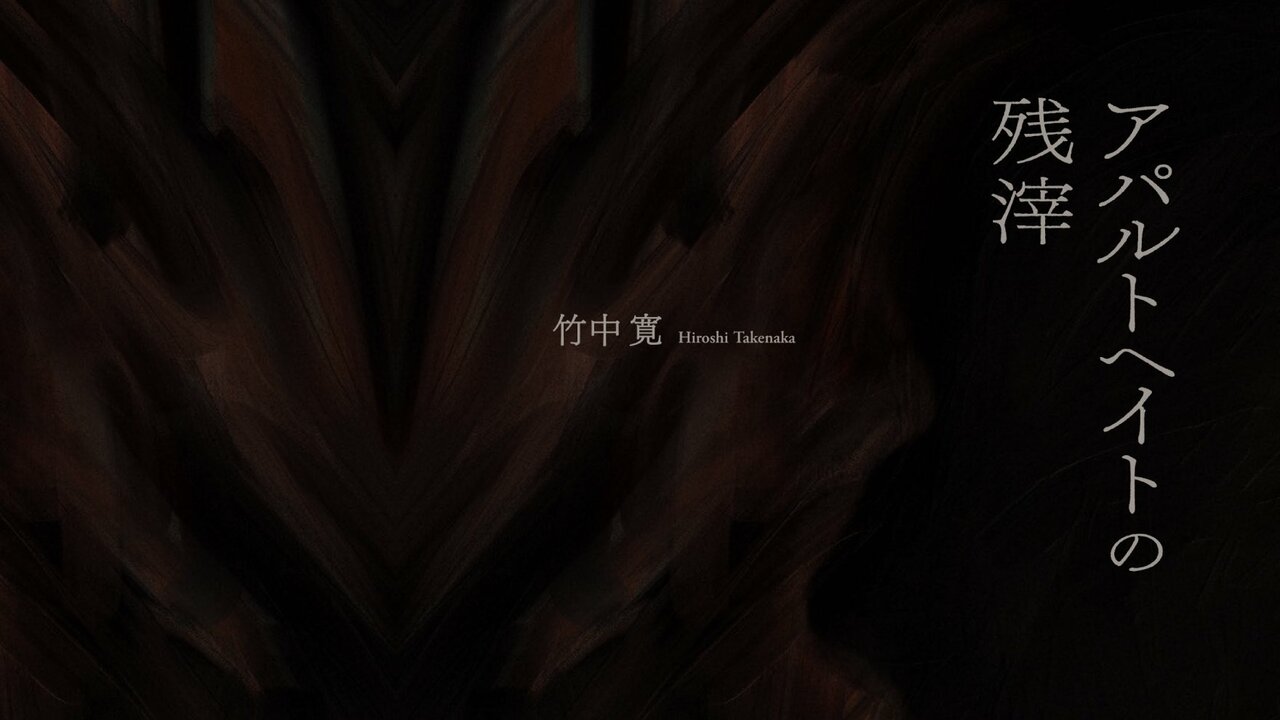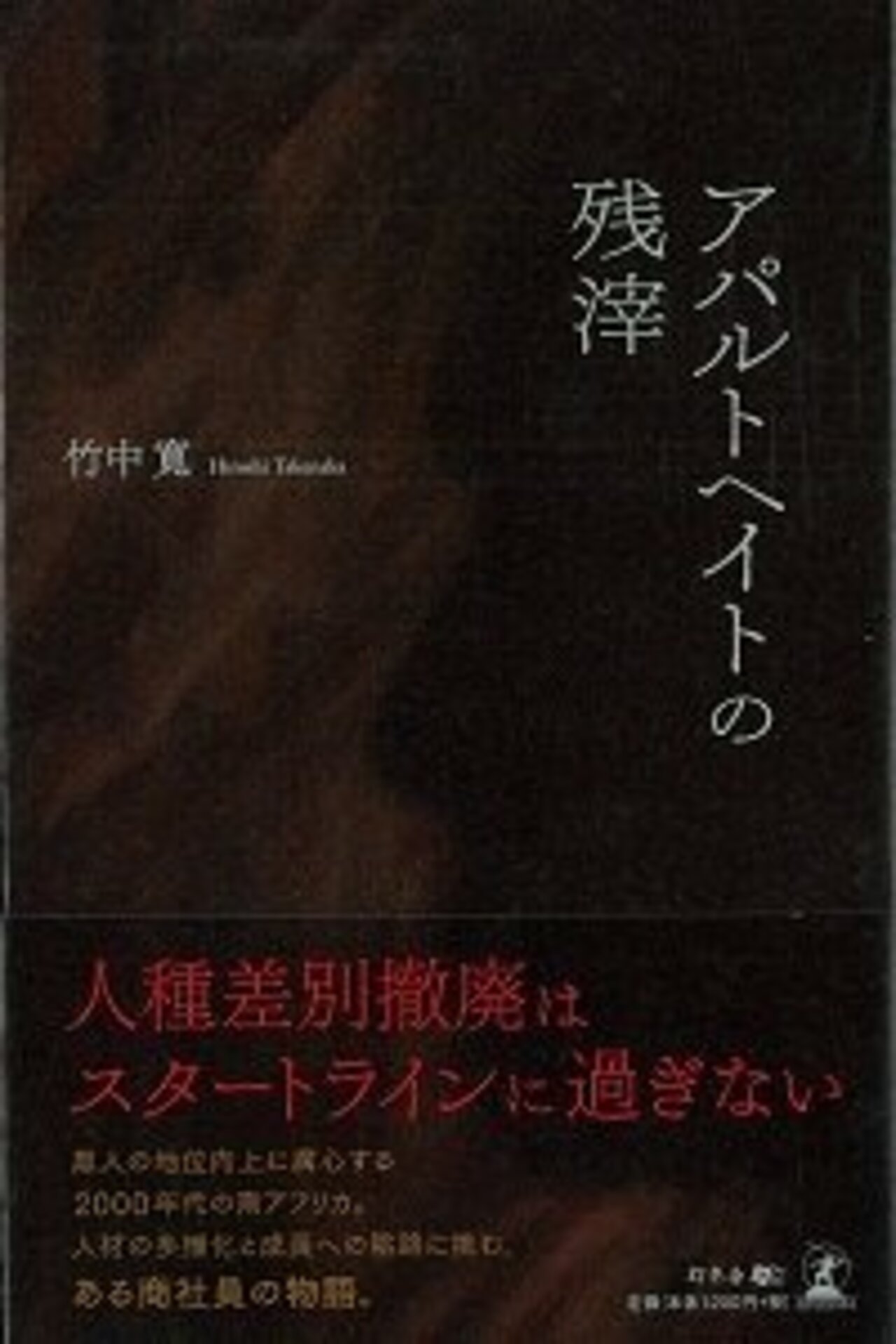一
強盗泥棒対策のために高圧電線を張りめぐらせた高い塀が外界との関係を遮断している。塀の向こうには、すぐ近くのタウンシップと呼ばれる黒人居住区の住民たちが行き交い、その頭部だけが見える。白い歯が、肌の色とのコントラストで鮮やかに輝く。白人や日本人らしい姿を見かけることはない。
高倉譲二はオフィスの窓からじっとその光景を眺め、
この人たち、この国、この会社の将来はどうなるのだろう?との思いにふけっていた。
彼は日本の総合商社、七洋商事の物資本部から南アフリカ子会社であるマキシマ株式会社の社長として二〇〇四年に派遣され、約一年が経過している。
突然、秘書のアンネマリーが社長室に飛び込んできて叫んだ。
「ミスター・タカクラ、パニックボタン(非常用ボタン)を押して下さい」
また何か事故か事件が起きたな、と思いながら、とにかく彼の執務机の下に隠すように取り付けてある非常ボタンを押した。これは契約している警備会社につながっており、すぐにガードマンが来る。
アンネマリーは彼がパニックボタンを押したのを確認すると、事態を説明した。
「倉庫のチーフが武装強盗に襲われて撃たれたらしいのです。まだ詳しいことは不明です」
このオフィスの裏手に社有の倉庫があるが、そこが強盗に襲われたようだ。倉庫の中には会社の取り扱い商品であるタイヤやホイールがびっしりと保管されている。
在庫商品を狙った武装強盗に襲われたことは何度かある。従業員には絶対に抵抗してはいけな いと通達してあるが、チーフが襲われたということは抵抗したのだろうか? 相手は拳銃だろうか? もしマシンガンだったらひとたまりもないが……。
心配する高倉に三十年前の『あの時』の恐怖の体験が蘇ってきた。