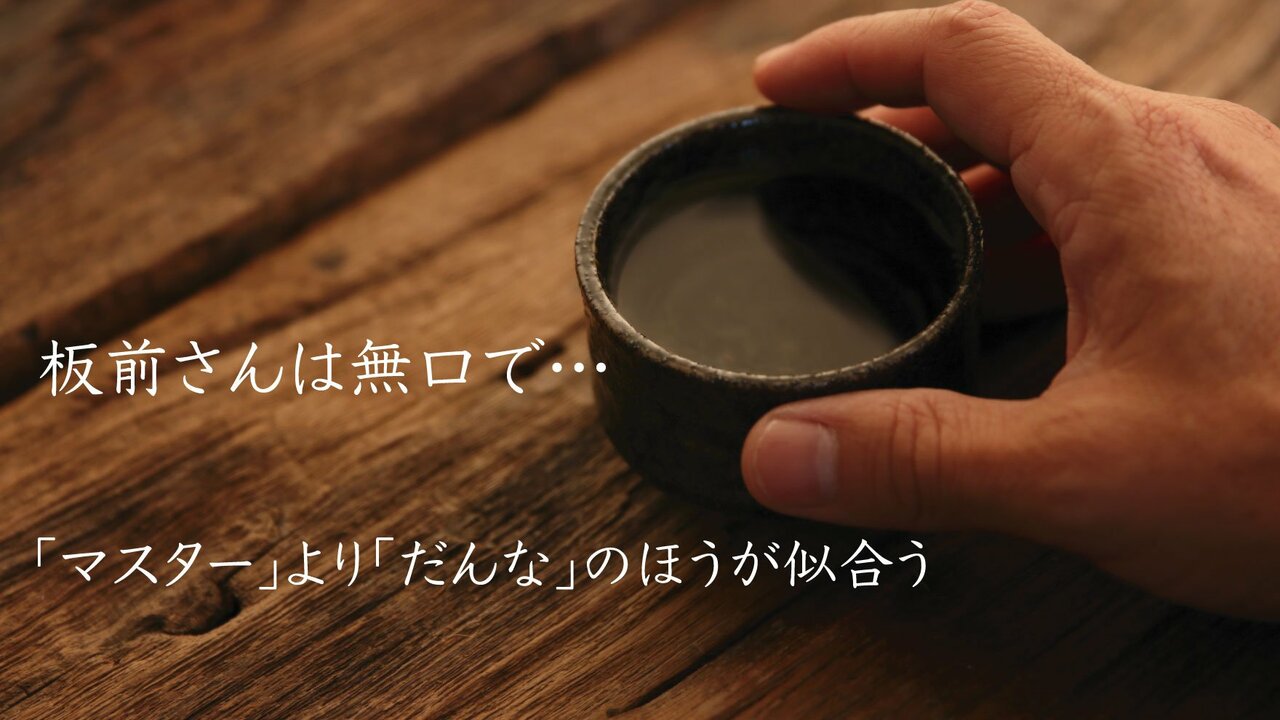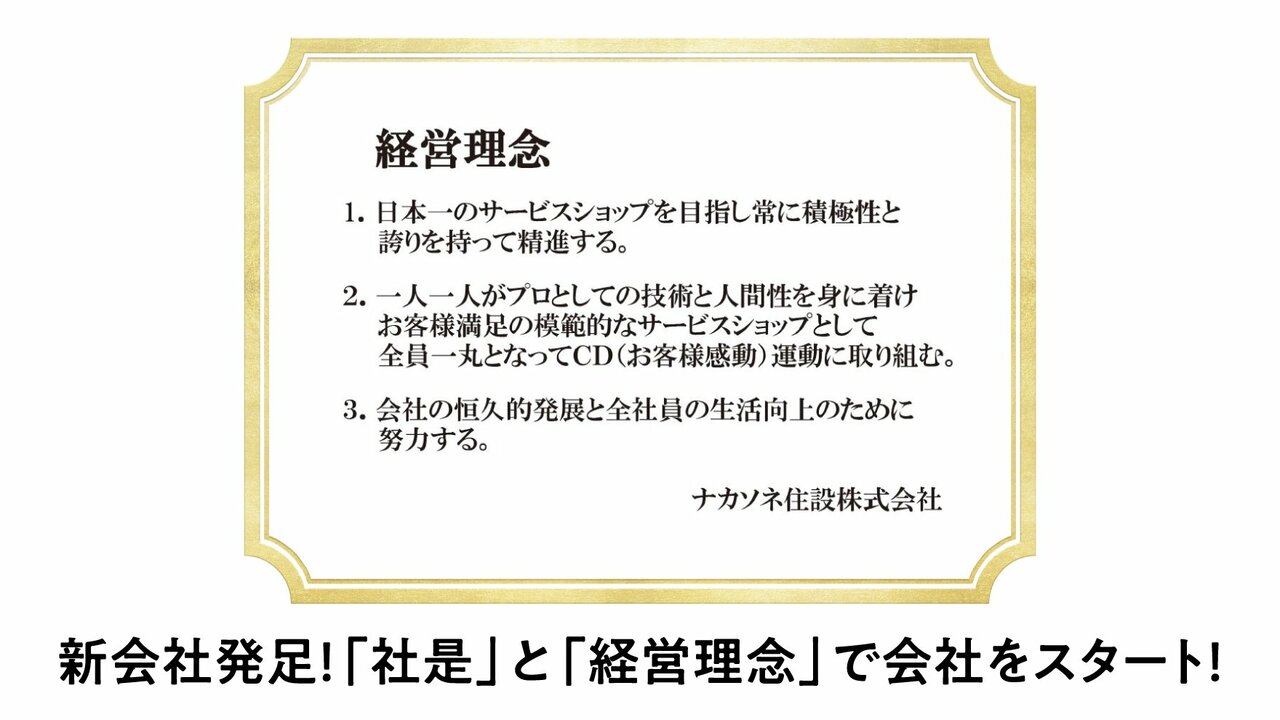休憩なのでしょうか、軒先や庭先で昼食をとり始めたのです。我が家にも数人の兵士が入ってきて、縁側に座り飯盒(はんごう)に詰められたご飯を食べ始めました。「ちょっとお邪魔します」などと一言断って入ってきたのかどうかはわかりません。
我が家に入ってきた兵士たちに、母はお茶を出していました。軍服に身を固め、脚絆(きゃはん)(ゲートル)を巻いた足を組んで、私にも笑顔で話しかけてきました。
「ぼん、大きくなったら大将になってお国のために頑張れよ」などと言ったような、どこかほのぼのとした雰囲気だった気がします。外に出て軍用車のほうを見ると、車のわきには小銃が三挺、車ごとに銃先で組み合わせて立てかけてあるのが見えました(叉銃(さじゅう)というらしい)。
なぜこんなことを鮮明に覚えているのか、自分でも不思議ですが、私の頭の中のマイクロチップに記憶されたデータが、まるでダウンロードされるようによみがえってきます。
わたしはとまどっていた。わが身になにがおこったのだろう? 前にはそんな兆候がなかったのに、なぜ最近、こんなにも過去のことが蘇って来るのだろう? 作家にとって、子供の頃の体験を蘇らせてくれる思い出に触れるのはよろこばしいことかもしれないが、〈中略〉なんの努力もなしに、記憶の貯水池からわきだしてくるのだ。
『この世で一番の贈り物』オグ・マンディーノ著(菅靖彦訳、PHP研究所、二〇〇一)