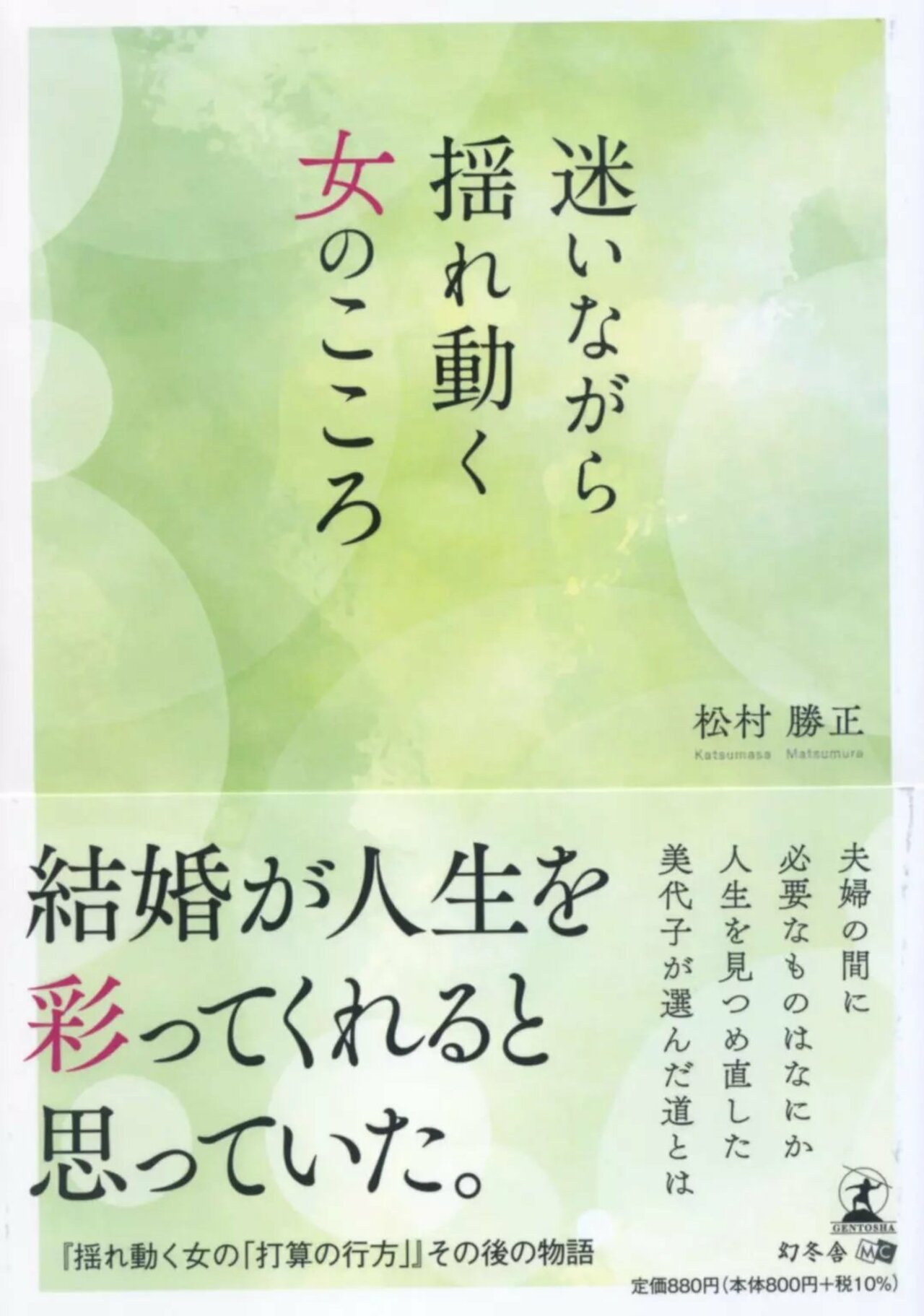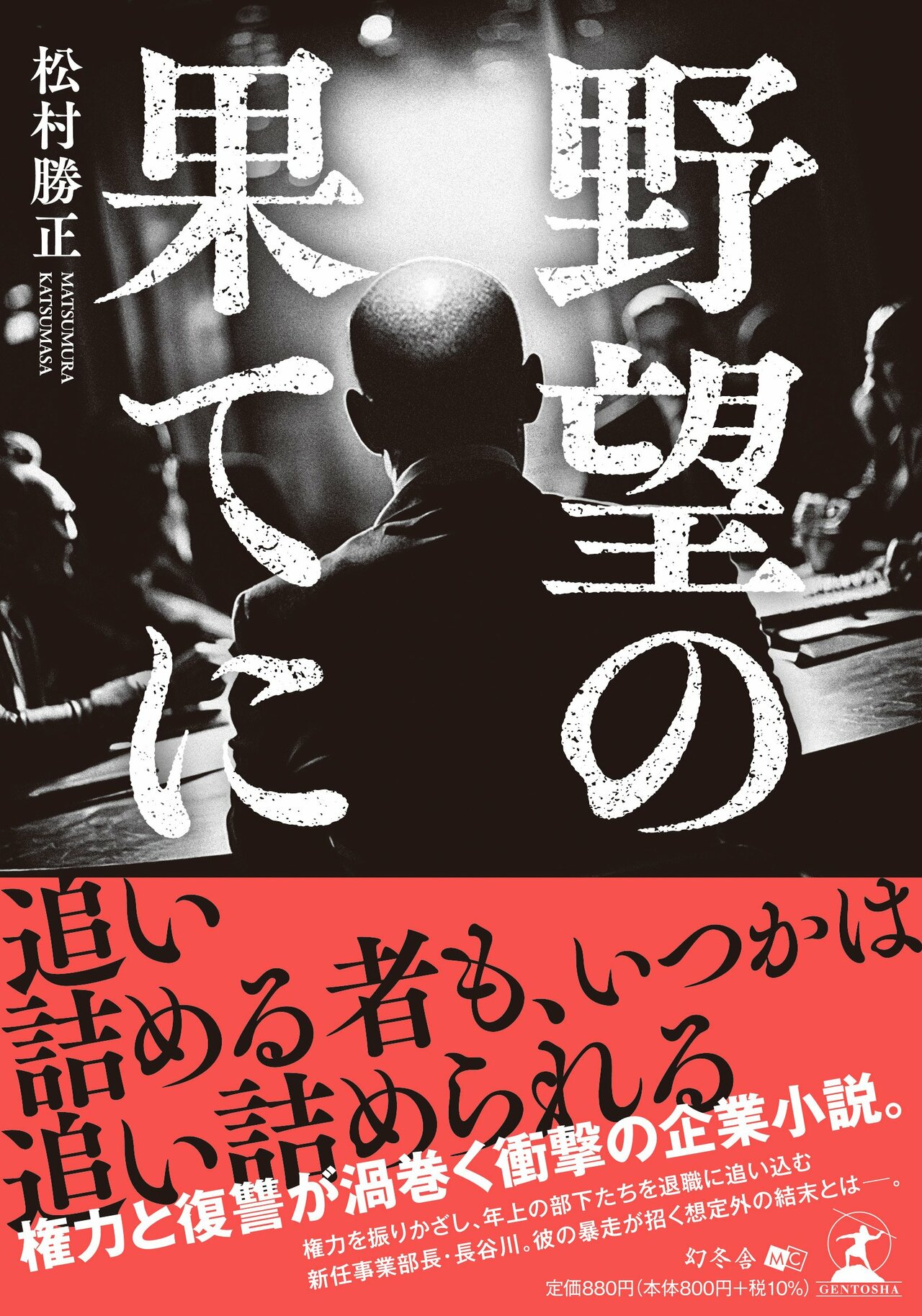「誰かしら」
「ご家族の方らしいですよ」
「ああ、そうですかありがとう」
美代子は職場へは戻らずそのまま会議室に向かった。
ドアを開けると「お姉さん」とちゃっかりテーブルの真ん中の椅子に座っていた。
「英子どうしたの、お仕事じゃないの?」
「今日、珍しく丸の内のお客まで打ち合わせに来たの、お姉さんの会社が近くだからどんな会社か覗いてみたかったの」
「びっくりするじゃないの、受付で家族の方がいらしていますと聞いたから、何か起こったのかと思った、心臓に悪いよ」
「それで目的は、ただ会社を見にきただけ?」
「もう一つあるの、ほら、お姉さんの彼がどんな人かひょっとしたら事務所でニアミスになるかなと密かに思ったの」
「英子は趣味が悪いわね、お母さんに何か聞いた?」
「いや、何も、何かあったの?」
「もう終わったことなの、あれからずいぶん経っているから」
「うそでしょう、私だけ何も知らなかったのね」
「本当よ、貴女も誰かを好きになっても近視眼的になり盲目にならないことよ」
「私は、もうすぐゴールインするとばかり思っていた」
「詳しいことは、今度お話しするわ、今日は御苦労さま、早く帰って頂戴」