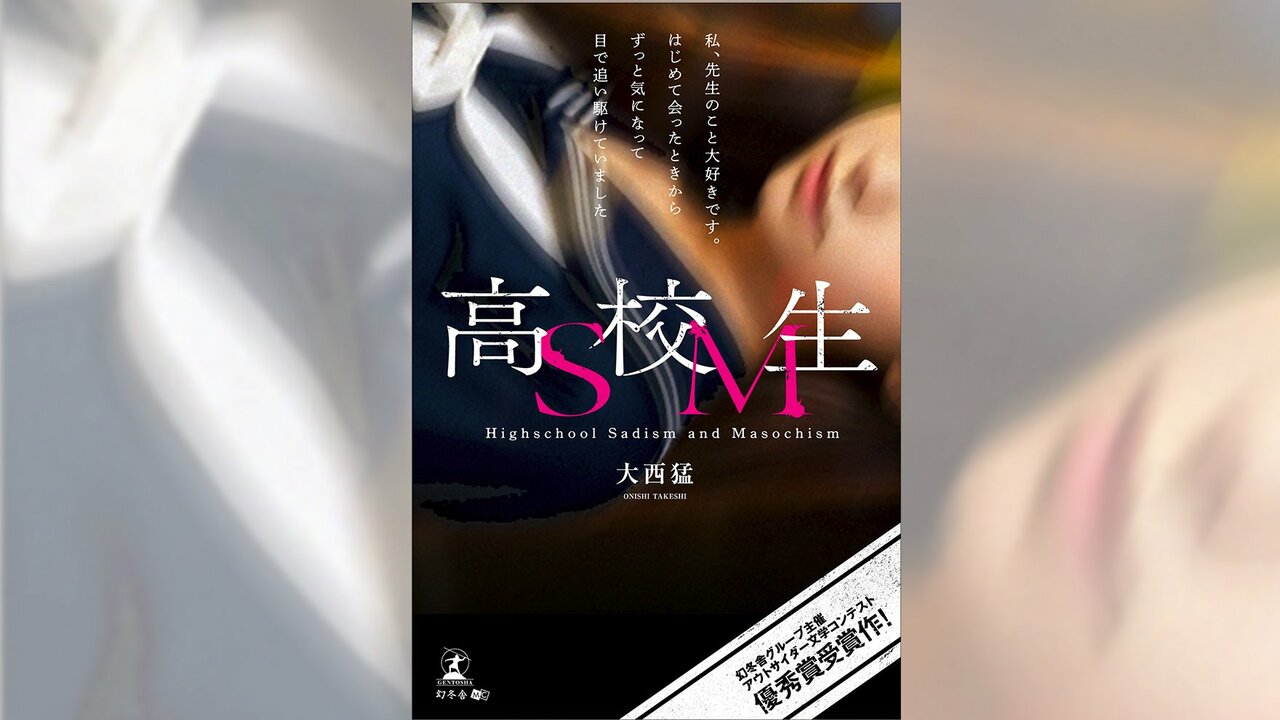序
さっきよりも空が暗くなったと思ったら雨が降ってきた。頬に、額に、冷たい雨の粒が落ちた。零下に近い空気で冷やされたその粒は今にも雪に変わりそうだった。私は自然と急ぎ足になった。
その建物の前を通ったとき、雨脚が強まった。急ごうと思った私だったが、十字に光るそのオブジェを見て急に止まった。十字のオブジェは金色のメッキがされており、電飾などないはずなのにそれ自体が光をまとっていた。私はそれが十字架だと気づいた。そして目の前にある建物は教会だった。
教会は白い漆喰で塗り固められた簡素な作りだった。十字架がなかったら教会だとはわからなかっただろう。私の立っている目の前に鉄の門があり、それは開かれていた。鉄の門から教会の入口まで石畳が伸びていた。
私の足はなぜかその門に吸い込まれるように向きを変えた。雨宿りができると思ったのだろうか。隣人への愛を説く教会なら濡れてみすぼらしい姿の自分も受け入れてくれると思ったのだろうか。それともまったく別の力によって導かれたのだろうか。いずれにしても意思よりも先に足が動いていた。
入口のドアを押すと、何の抵抗もなく簡単に開いた。外の空気と変わらない冷たい空気がドアの向こうの空間にも広がっていた。信者が座る木の椅子が整然と並べられていた。その先には祭壇があった。人の姿は見当たらなかった。一瞬入ることをためらったが、強さを増した雨の音に背中を押されるように足が勝手に前に出た。
そこは完全な静寂が支配していた。高い天井は私がたてた足音をあっという間に飲み込み、静寂の密度を高めた。雨音さえもその建物の中には入ってこなかった。
教会の中を見るのははじめてだった。私は無意識に一番光る場所に目を向けた。それは入口の真正面にある祭壇だった。明かりをとりいれる大きな窓が左右にあり、そこから光が射していた。そして一番目立つところには十字架に磔にされた一人の男がいた。私はそれをよく見るために近づいた。
男は数十センチに満たない大きさだった。にもかかわらず近づくにつれ、実物のように大きく見えた。額を覆う茨の冠も、手に打ち付けられた杭も、精巧に再現されていた。額から流れる血の流れも。
それを見た瞬間、私の体に痛みが走った。久しぶりに感じる痛みだった。同時に忘れていた快感も蘇った。キリストの顔が一瞬あの人の顔に見えた。でも、すぐにそれは自分の顔に変わった。
あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。
体中の血が熱くなっていた。そして血が巡るように、全身を悲しみと喜び、さらにはあの人に対する消えない思いが駆け巡った。