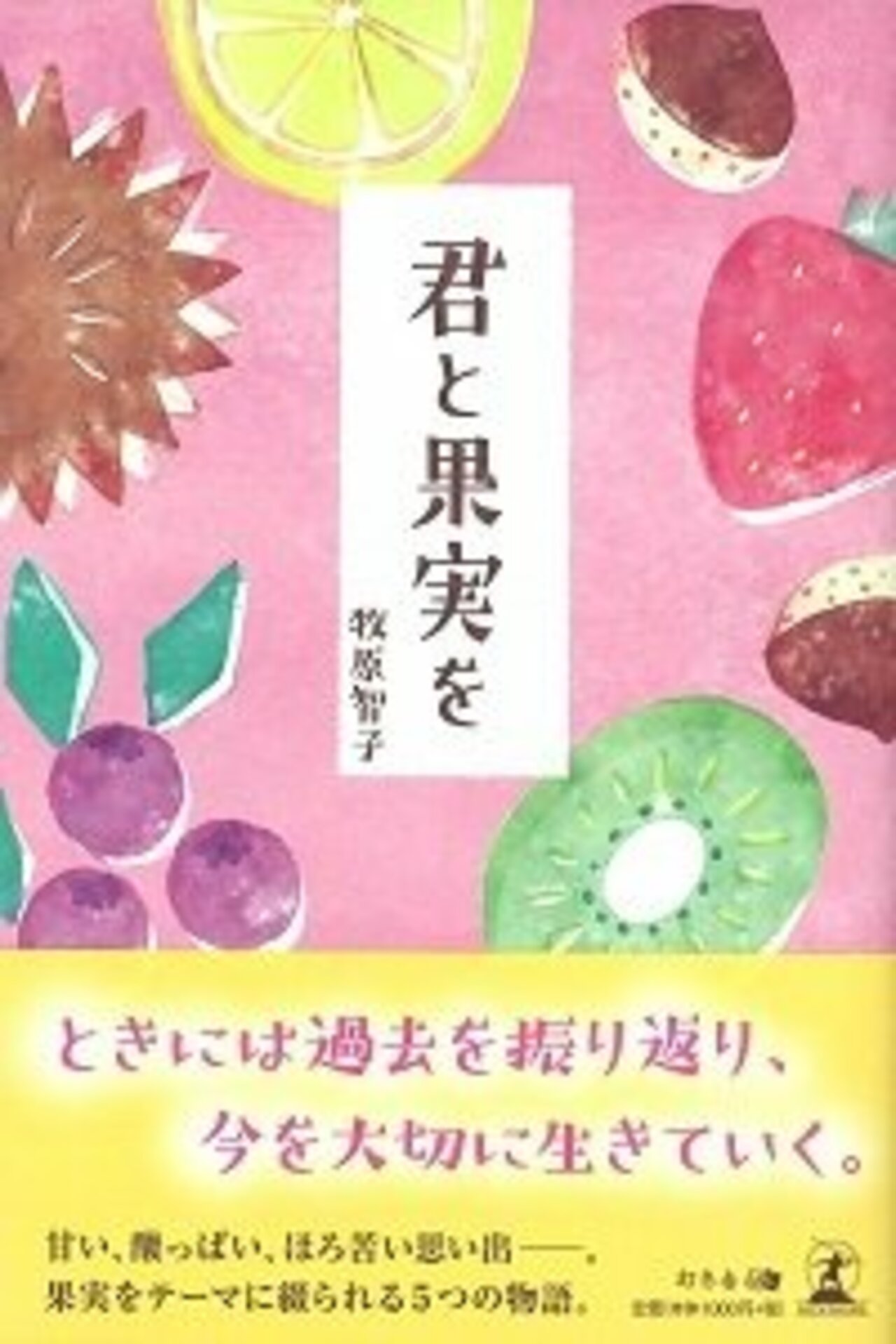栗に願いを
次の仕事は、地元のタウン情報を扱う小さな会社だった。クリーニング店のオープン、養護施設の紹介、街角イベントなど、以前に比べると華やかさには欠けるものの、反響がすぐに伝わってくるので、ものすごくやりがいはあった。
取材で伺ったお店のおばあさんがとても優しい笑顔で迎えてくれて、お茶を飲みながら話し込んでしまうこともあった。時間に追われて取材をしていたあの頃より、人と触れて、何気ない会話の中で、そのお店の本来の素晴らしさに気づくこともしばしばあった。地元に根付いたタウン誌ならではの経験。街を歩いているとお店の人から声をかけてもらうことが多くなり、横浜という街が大好きになった。
新しい仕事を始めると同時に、ずっと習いたかった英会話を本格的に始めた。週に一回の個人レッスンだったので気分転換になったし、自分のペースで学ぶことができたので、今までの勉強人生において一番吸収できたんじゃないかと思うくらいの収穫があった。海外取材の時、これくらいの語学力があればもっといい取材ができたのに、なんて思ったことも。
そして、英会話の先生の紹介で翻訳家の方と知り合い、その仕事の奥深さを知り、興味が湧いてきた。出版社を辞める時に、もう仕事でワクワクすることなんてないだろうと思っていたのに、新鮮で刺激的なワクワクが自分に舞い込んできているような気がして嬉しかった。
リチャードとは最初の翻訳の仕事で知り合った。澄んだ瞳と上品な口元が好印象で、実年齢よりは老けて見えたが、とても優しいアメリカ人だった。細身の濃紺のスーツに念入りに手入れされたレザーのローファーという出で立ち。
キリっとしていて一瞬怖い人かな? と思うくらいだったが、冗談も交えて話ができる彼は、その場の空気を和ませてくれる人だった。打ち合せを重ねる度に、彼との距離も縮まり、参考になる資料を貰いにいったり、自然とお互いの家を行き来するようになった。
時にはリチャードが「新鮮なムール貝が手に入った」と大量に買ってきてワイン蒸しを作って飲んだり、私の好きな映画『プリティ・リーグ』を一緒に見て飲んだり。彼のDVDラックが私の好きな映画で溢れそうになった頃、この人とだったら……と私は初めて結婚を意識した。
リチャードが持ってくる仕事話はいつも刺激的で、びっくりさせられることも多かったが、なんとか二人で乗り切れた。そんなある日、また彼に驚かされる。
「ミキ、北海道に行こう。いい家があるんだ」
これはプロポーズなのか、それとも、住まいを変えることで何かまた新しい仕事を始めるつもりなのか。旅行気分で向かった北海道で私の運命は、大きく揺らぎ始めた。
彼がすでに目を付けていたその家までは、新千歳空港からレンタカーで二時間弱。徹夜続きだった私たちのスケジュールでこの日しか連休が取れなかったので仕方ないよね、といって彼は充血した目をこすりながら、運転してくれた。
「同じ日本の空なのに、ほんと色が違うよね」
「うん、澄んだ空気もスバラシイ。僕が気に入った家、ミキも気に入ってくれたらいいんだけど」
それまでずっと明るい青い空が続いていたのに、急に暗い雲が空を覆い始めた。一気に天気は下り坂。激しくフロントガラスを叩く雨が完全に視界を遮り始めた。
その瞬間のことは、覚えていないほど。気がついた時、私は病院のベッドで寝ていた。看護師さんが優しく話しかけてくれた。
「目が覚めましたか? お加減いかがです?」
何の事かさっぱり分からなかったけど、私は相当な時間、眠っていたようだった。最後の記憶は、あの雨のフロントガラス、で止まっていた。
「彼はどこですか?」