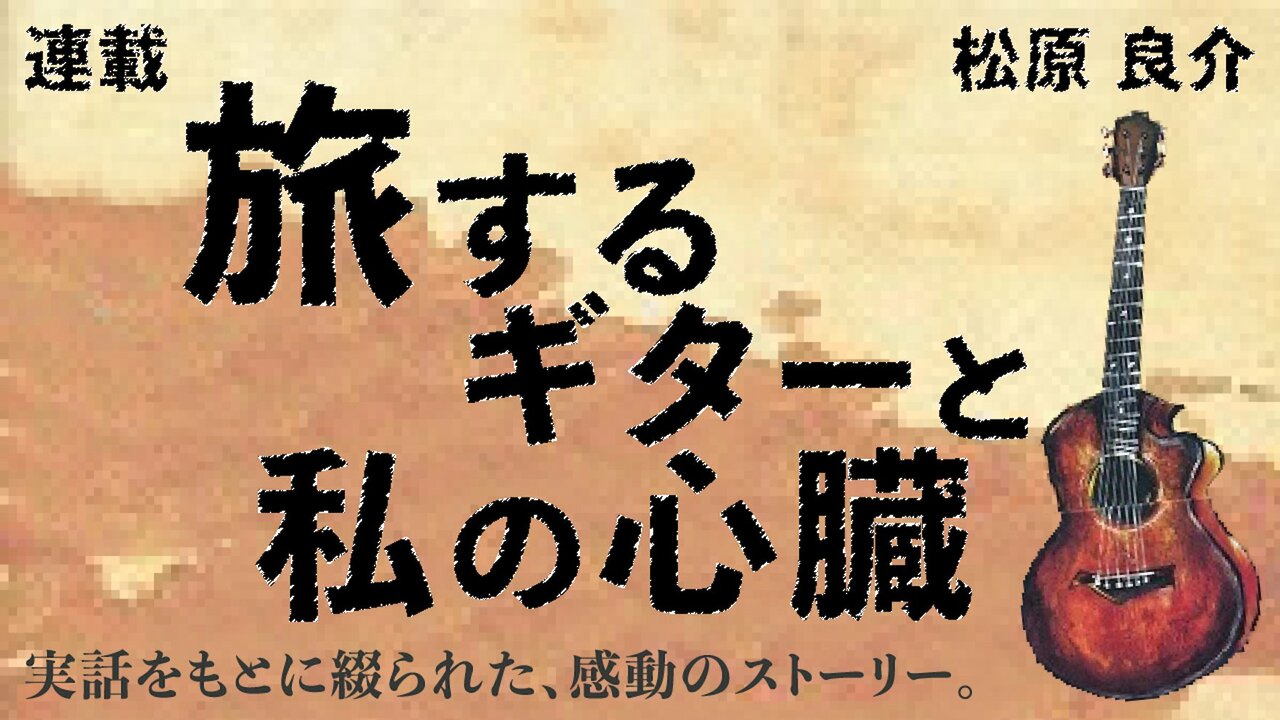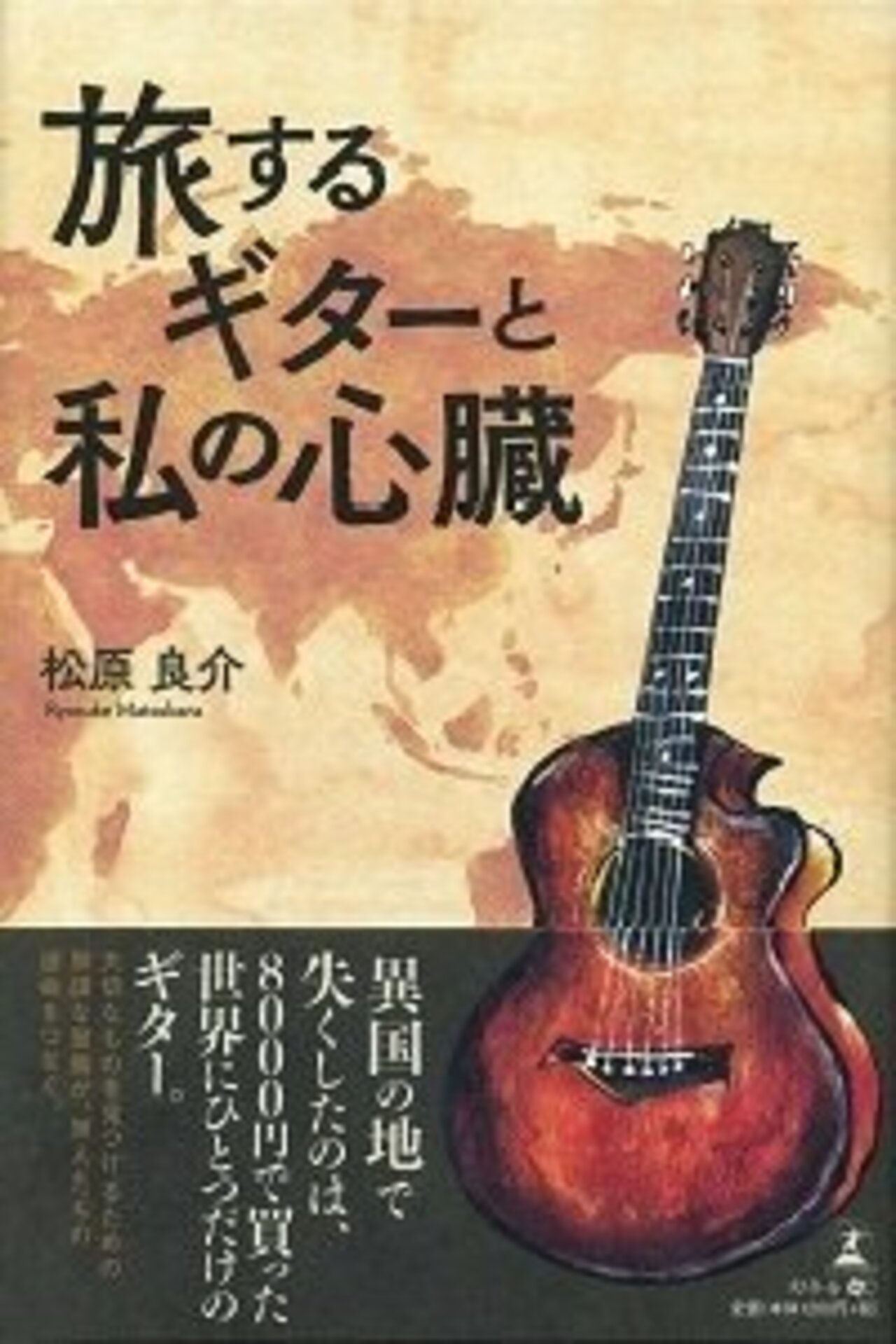自分の評価(山平遥)
2014年10月。
山平遥はバンコク市内のゲストハウスに宿泊していた。
日本人が多く集まるこの「ミスティ」と呼ばれるゲストハウスは、お世辞にもきれいとは言えないコンディションの宿であったが、格安で個室に宿泊できることもあって、バックパッカーには人気があった。
連日のように降り続く雨で、ゲストハウス前の通りには、池のようになった水たまりがいくつも広がっていた。バンコクに来て3日目の遥は、まともに観光もできず自室にこもっていた。時折1階の共有スペースに顔を出すものの、ほかの宿泊客の姿はなく、相手をしてくれるのはレセプションにいる年老いた黒猫だけだった。
数ヵ月前、高円寺のカフェで働いていた遥のもとに、大学時代の友人である西村香織が訪ねてきた。3年ぶりに会った香織は髪の色が少し明るくなったくらいしか変わっておらず、「就職したけど1ヵ月で上司とケンカして辞めた」とか「今タイに住んでいる」とか「バンコクで仕事を始める」とか、口を開けば勢いのある話ばかりが飛び出した。
そんな彼女が「バンコクで一緒に仕事をしない?」と、わけのわからないことを言い出したときには自分の耳を疑った。
大学時代、バイト先もサークルも同じだった香織と遥は四六時中一緒だった。男らしい性格の彼女は、時折ストレートな物言いで遥を悩ませることもあったが、なんでも相談できる親友だった。
現在、香織はタイの北部にあるパイという町に住んでおり、彼女と5日後にこのゲストハウスで会う約束をしていた。遥は初めてのバンコクに心を躍らせ、1週間早くここに来ていたが、今のところバンコクには、こっぴどく降り続ける雨のイメージしかなかった。
膝の上の猫が面倒くさそうにあくびを一つした。
遥は1階のレセプションの隣に広がる共用スペースで、この日も日本で録りためたお笑い番組の動画を見ていた。これからの人生を書き留める日記用にと大志を抱いて購入した11インチのマックブックだったが、皮肉にも思わぬ形で向き合うこととなった。
このゲストハウスは大雨が降ると、きまってインターネットが使えなくなるのだが、1階のソファ付近はかろうじてWi-Fiがつながったので、遥は雨が降るとこの場所を我先にと陣取っていた。
ずぶ濡れの男が転がり込むようにミスティに現れたのは、雨が本降りになってきた夕刻のことだった。遥はソファに座りながら、その男が長髪から滴る水を振り払う様子を眺めていた。
レセプションにいたスタッフとしばらく談笑しているところを見ると、男はこのゲストハウスの常連客か友人のようだった。しばらく話し込んでから2階に案内された彼は、服のまま海にでも飛び込んだような格好で階段を上がっていった。
それからしばらく経っても雨は一向に止む気配はなく、ミスティの前にできた水たまりはまだまだ大きくなりそうだった。気まぐれな天候に左右され、明日の予定も立てられないまま、遥は少しずつモチベーションが下がっていくのを感じていた。
1階の共有スペースにいた遥に、さきほど見たずぶ濡れの男性が話しかけてきたのは、遥がお笑い番組を見飽きた頃だった。
「こんにちは。日本人ですか?」
男は頭にタオルを押し当てながら、遥の前にやってきて話しかけた。
「あ、こ、こんにちは。はい、日本人です」
遥は少し驚きながら返事をした。日本語で話しかけてきた男は、どうやら日本人のようだったが、日焼けした肌や、彫りの深い顔は、近くで見ても現地人とそう変わらなかった。
身長は170センチくらいで、細身だったが健康的でがっしりした体型をしていた。
「日本人だったんですね、さっき見かけたときから、てっきり現地の方かと思っていました」 遥がそう言うと、男は「確かに…最近かなり日焼けしたからなぁ」と笑った。