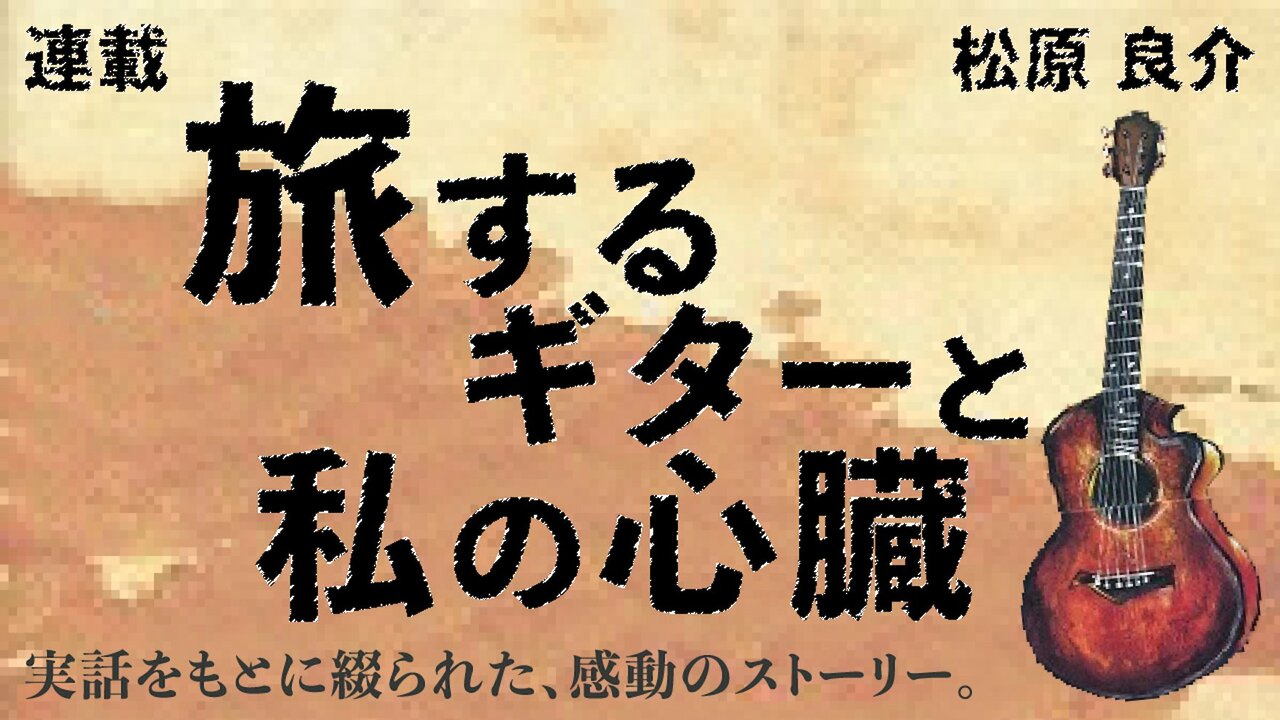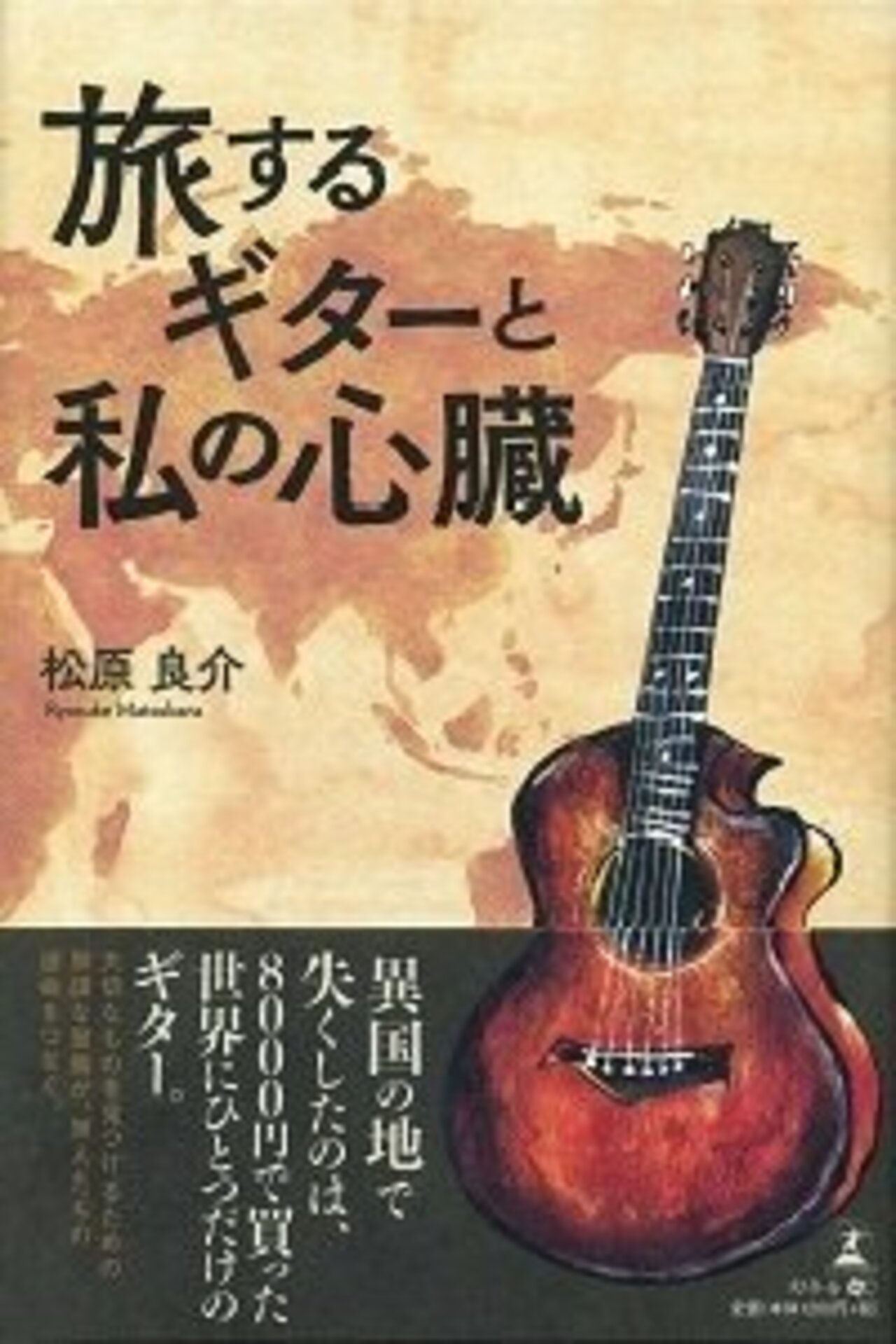〈宇山祐介の事情〉 探し物
2014年9月。
私が日本を出発してから2ヵ月が経過していた。
タイの首都バンコクは、朝から雨が降り続いていたが、私が出かける頃には上がっていた。空を見上げると、ゆったりした風がどす黒い雲を南に追いやるのが見えた。空は本来の美しい色を思い出したように、青い色を頭上に広げていった。
陽炎の揺らめく大通りでは交通渋滞ができており、排気ガスをまき散らしてトゥクトゥクやタクシーが騒がしくクラクションを鳴らしている。その隙間をバイクがすり抜けていく様子はまるで曲芸だった。
舗装が不十分な道路のあちこちでは、でこぼこの地面が目立ち、そこにできた水たまりは叩きつけるような太陽の熱で今にも沸騰しそうだった。
大通りから1本奥まった場所に小さなカフェがあった。
名前はおそらくない。毎日のように通うお気に入りのカフェだったが、そこにはエアコンなどなく、お世辞にも居心地がいいとは言えなかった。だが、何度か通っているうちに店員たちとも仲良くなり、次第に足を運ぶようになっていた。
いつものテラス席に陣取った私は、腕をまくってサングラスを外した。店員が運んできたタイティーを受け取ると、コップンカー(ありがとう)と言ってそれを口元に運んだ。扇風機のある店内よりも日陰になっているテラス席で風を感じたほうが涼しいことを知っていた私は常連気分だった。
肘までまくり上げた白いシャツからは、日焼けした腕がのぞいている。サッカーをしていた学生時代を除いて、私がここまで日焼けをした記憶はない。それを旅人のステータスのように誇らしく感じていた。
2週間の滞在で、私の風貌はバンコクの雰囲気にすっかり溶け込んでいた。
私は35歳を目前にした自分が、バックパッカーとしてここに存在していることに気持ちが高ぶっていた。田舎から上京したときに似ているようにも思える。
タイティーを半分ほど飲みかけた頃、トミーがバイクで迎えに来た。
トミーはゲストハウスで知り合ったタイ人男性だ。バイクにまたがりキョロキョロしているトミーに向かって、私が手を振ると、すぐにこちらに気がついた。
「ユウスケ! 後ろが詰まっているから! 早く!」
器用に日本語で返事をしたトミーは、一度笑顔を見せてから、急かすように大きく手招きをした。カフェの前は道路が狭く、そのうえ路上駐車も多いため、バイクに乗ったトミーの後ろには、小さな渋滞ができあがっていた。
私はトミーの声とやかましいクラクションに急かされるようにタイティーを飲み干すと、ポケットに入っていた60バーツをテーブルの上に置いて店を出た。
目を細めながら太陽の下に身を放り出すと、その日差しは容赦なく肌を焼き始めた。私はバイクの後ろにまたがり、ポンッとトミーの肩をたたくと、彼は親指を立ててからアクセルを回した。
やかましい騒音を鳴らしてバイクが走り出した。大通りに出るとトミーはスピードを上げた。じっとりした向かい風だったが、それも今は心地よく感じる。私たちは交差点を抜けて南へ向かった。
私がトミーに出会ったのは、カオサンロード裏手にある「ミスティ」というゲストハウスだった。小柄でシャイなこのタイ人は、ミスティのオーナーの親族らしく、ときどきレセプションに立っていた。
日本のアニメと地元のサッカークラブをこよなく愛するトミーは、何かと世話を焼いてくれた。ちなみに「トミー」という名前はオフィシャルなものではなく、本名は長すぎて覚えられないため、まわりからトミーと呼ばれているとのことだった。年齢は不詳だった。
日本のアニメを見て独学で覚えたというトミーの日本語は、実に愉快で愛くるしいものだった。多少違和感はあったが、独特なイントネーションに慣れてしまえば、お互いの意思疎通はしっかりできた。
市内から20分ほどのマーケットに差しかかると、私は身を乗り出しながら、とある露店を探し始めた。一つ目の角を曲がったところで、お目当ての露店が目に入った。
「トミー! あそこだ!」
運転しているトミーの顔の横で私は腕を伸ばし、マーケットの外周にひしめき合う露店の方向を指さした。そこには中古楽器が数多く並んでいた。