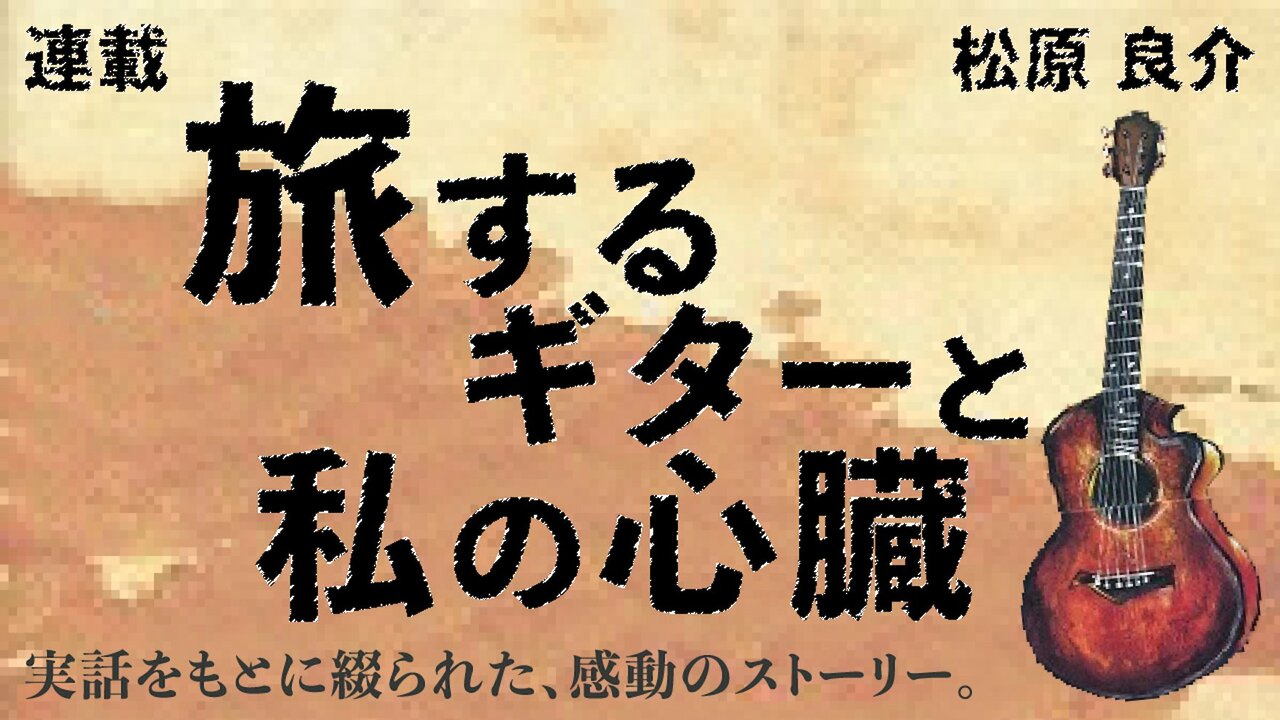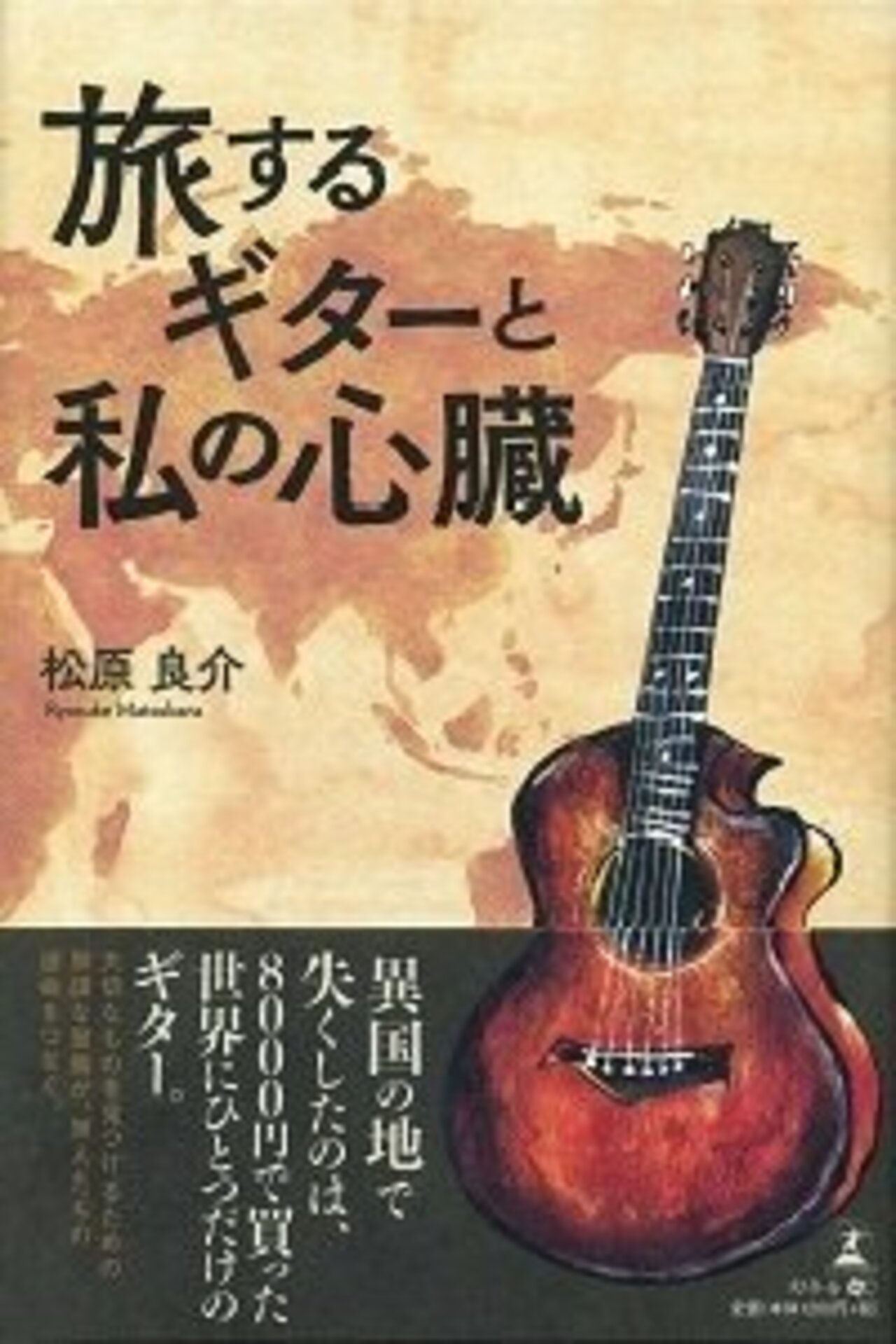「大丈夫、移植までなんとか乗り切ろう。そしたらさ、今度は一緒に旅に行こうぜ。教室だっていつかまた──」
私がそこまで言うと哲也の顔が険しくなった。
「移植まで何年かかるか知ってるか? じっくり待っていたら7年だぞ? それまでこんなんでいろってのかよ」
安易な私の話を哲也は遮って言った。絞り出したその声は小さく、何とか聞きとれる程度だったが怒りに満ちていた。
「でも、可能性はあるんだ。一緒に前向きに考えようぜ。必ず方法はあるはずだよ。ほら、海外で適合者を待てば、そんなに待たなくていいんだろ?」
「そんなに簡単じゃねぇんだよ…海外で移植するのにいくらかかるか知ってんのか? 3億だぞ? どこにそんな大金があんだよ」
哲也があきらめた口調で言った。
「ほら、募金とか。今流行ってんじゃん、クラウドなんとかってやつ」
「無理だって。お前……3億だぞ……」
「何でだよ、やってみなきゃわかんねーじゃん?」
「何の伝手もない30代半ばのオッサンに誰が金出すっていうんだよ」
でも……と、言いかけて私はそれをためらった。哲也の言うことは的を射ていたし、私も言う前からわかっていた。
確かに、これが未来ある幼い子どもが移植を待っている、という状況であったとしたら、募金も集まりやすいだろう。だが、我々のような立場の人間では、どんなに背伸びをしても集まる額はたかが知れている。それでも私は何か前に進む方法を考えたかった。
「何か方法があるはずだよ、足掻かなきゃ……一緒に頑張ろう…俺も一緒に……」
「もういいって、帰ってくれ」
「哲也……」
「疲れたんだ。頼む。帰ってくれ」
このとき私は哲也に「お前の気持ちはよくわかるよ」とか「お前はよくやったよ」とか、そんな言葉をかければよかったのかもしれない。でも、私には言えなかった。
結局、そのあと何を話したのか、自分がどうやって病院を去ったのかも覚えていない。ただ、帰り際に哲也が休業にしている音楽教室を閉める話をしたことだけは耳に残っていた。
〈宇山祐介の事情〉 可能性があるなら
実家から歩いて数分のところに、小さな公園があった。そこは林に囲まれているため、小さい頃は『森の公園』と呼んでいた。十数年経った今も、昔のままの姿で森の公園は残っていた。ここに来て新鮮な空気を吸えば、胸の奥のモヤモヤがすっきりするかと思ってきてみたが、そう簡単にはいかなかった。
しばらくすると公園に若い母親が子どもを連れて遊びにやってきた。こちらをチラチラ見ていたが、どうやら平日の昼間っから公園にいる中年男性を少し気にしている様子だった。
私は落ち着かなくなってそこを去ろうとすると、スマホに見知らぬ番号から電話がかかってきた。哲也の母からだった。電話の内容は、話があるから少し会うことはできないかというものだった。哲也の実家は公園の目と鼻の先にあったため、私はその足で向かうことにした。
哲也の実家に到着してリビングに案内されると、哲也の父がソファに座って待っていた。
「ごめんね、忙しいのに来てもらって」
哲也の母が、先週と同じ香りのする紅茶をテーブルに置いて言った。
「いえ、大して予定もないので。今日も哲也の見舞いに行こうかと。ちょっとあいつに謝りたいこともあって…」
両親二人はそれを聞くと、少し困った顔を見合わせてから、私に見舞いに行くことを遠慮してほしいと告げた。
「哲也がね、少し考える時間が欲しいから、誰にも会いたくないって……」
哲也の母は、さらに続けた。
「哲也、本当はとっても嬉しいのよ、それはわかってあげてほしいの」
哲也の母は、自分の子どもを慰めるように優しく声をかけた。
私は身体から力が抜けてしまうような気分になった。今こそ彼に手を差し伸べるときだというのに、何もできないでいる自分は、あまりにも無力に思えた。ともかく私は、言葉を選ぶ両親の気持ちを察して、落ち込む様子や動揺を見せないよう精一杯表情を作って見せた。
「あ、そうだ。おばさん、もう一回哲也の部屋見てもいいかな? ちょっと見たいものがあるんだけど」
話題を変えてその場を離れたかったせいもあるが、そのとき私は急に哲也が病室で言っていたギターのことを思い出したのだ。
「ええ、もちろん」
と哲也の母は特に気にする様子もなく返事をしてくれた。
2階に上がると、哲也の部屋は数日前と何も変わっておらず、バックパックは大きな口を広げて壁に立てかけられたままだった。私は大して広くない部屋のなかをウロウロしながら、どうせ見てもピンとこないであろうギターに関する情報を探した。
私は本棚にあるCDを手に取り、うっすらとかぶった埃を落とした。特に聞きたかったわけでもなかったが、窓際にプレーヤーを見つけると、それにCDをセットした。もう何年も音を出していないスピーカーからエリッククラプトンの「ピルグリム」が流れた。
それを聞いているうちに、どんどん昔のことが思い出された。昔、この家の屋根にあがってギターを弾いたことも、しょうもない曲を夜通し作ってみたことも、このアルバムを駅前のCDショップに一緒に買いに行ったことも、鮮明に脳裏に浮かんだ。
ふと、何かに引き寄せられるように窓に歩み寄った。窓の横に数枚の写真が画鋲で無造作に留められている。どれも15〜16歳の頃に撮ったもので、そのなかの1枚に目が止まった。
それは『森の公園』に楽器を持ち寄ったときの写真だった。