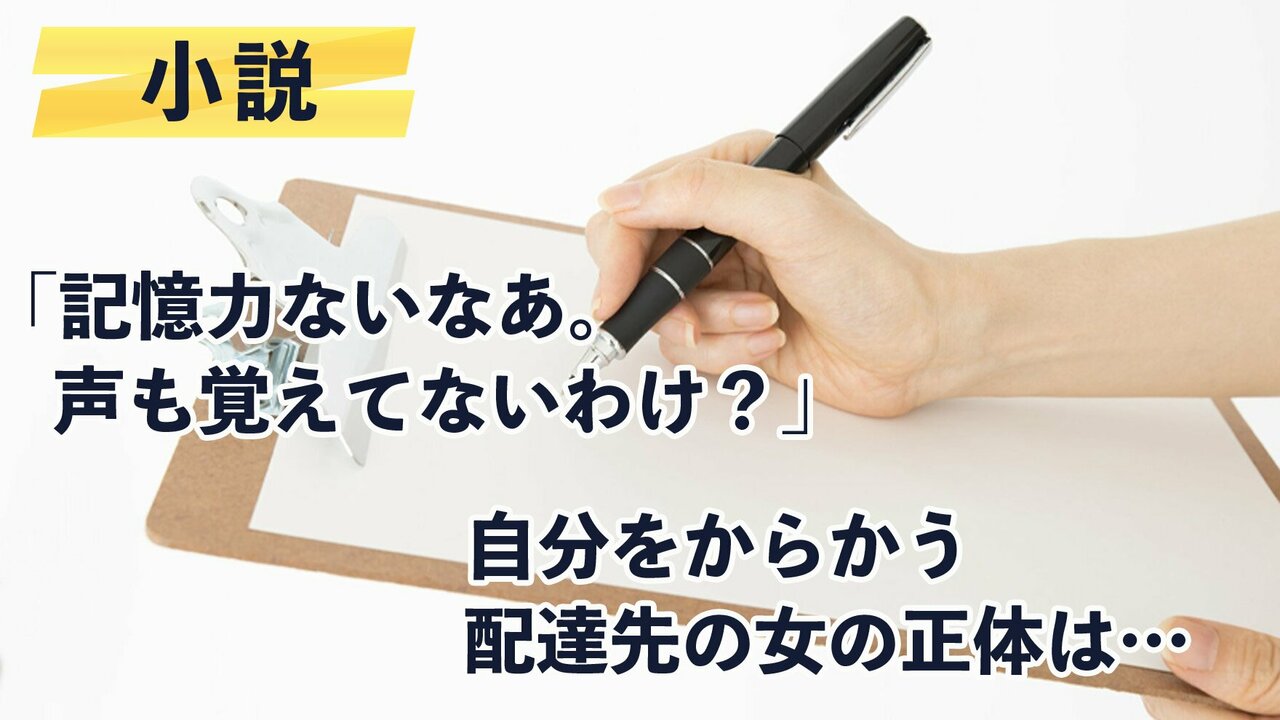1
まもなく、ピンポーンとチャイムが鳴るとともに、モニターにバイキンマンの顔が映し出される。いきなりこんなヤツが訪問してきた日にはそれこそ通報沙汰で、愛想もへったくれもないが、愛想を教えると言うからには、朗らかな声で、「宅配便でーす、荷物お持ちしましたァ」と来るかと思った。それが冷静な声で、「あなたさあ、まだ気付かない?」と呟くのだ。
「何に?」モニターに向かって、尋ねる。
「記憶力ないなあ。声も覚えてないわけ?」
小馬鹿にしたように女は漏らし、バイキンマンのお面を持ち上げ、サングラスをそうするように、頭にお面を掛けた。ようやくぼくに素顔を晒した女は、こちらに手を振り、「久しぶりィ」と笑う。
あ、コイツ……。
眉毛も黒目がちの目も、優美な弧を描いていて、一見穏やかな風貌。ロングヘアを真ん中から分け、額を出している様など、ぼくより大人びている感じであり、落ち着いているように見える。清楚な美人の部類に属するといっていいかもしれないが、目に隠しようもない妖しい企みが宿っている。
確かにぼくは、この女を知っていた。会うのはどれくらいぶりだろうか。懐かしかった。かつてのぼくと彼女との関係を考えれば、もっとバツの悪いような、複雑な再会となっていいはずなのに、なぜだかびっくりするくらい懐かしかった。ほっとするような心地で、
「ああ、ハハ。確かに、久しぶりだなァ」
かすれる声でぼくは呟く。
「びっくりしたわよ。昨日さ、このボロアパートに、カメラ付きのこやつを付けてもらったの。で、最初に映ったのが、あなただったんだもん」
「で、思わずからかってみたわけ?」
「からかうっていうより、こやつでいろいろ会話してみたかったのよ」
「それがあの会話? 嫌がらせとしか思えなかったけど。まあ、君らしいけどな」
相手からはこちらが見えないという理由で、ぼくはモニターに映る彼の顔をしっかりと見ている。画面が小さすぎて細かいところまでは映らない。けれど以前より落ち着いているという気がするのは、歳月のせいだろうか。大人のいい女になった。それでもバイキンマンのお面を頭に掛けていれば、真人間に成長したとは到底いえそうもない。相変わらず掴みどころがない謎めいた女だ。
ほどなく彼女が玄関のドアを開けた時、その顔は再びバイキンマンになっていた。入れ違いに玄関に戻り、スニーカーを履きながら、
「もう正体バレてんだからさ、隠さなくていいじゃん」
ぼくは苦笑し、荷物と配達票を彼女に差し出すと、
「サインください」