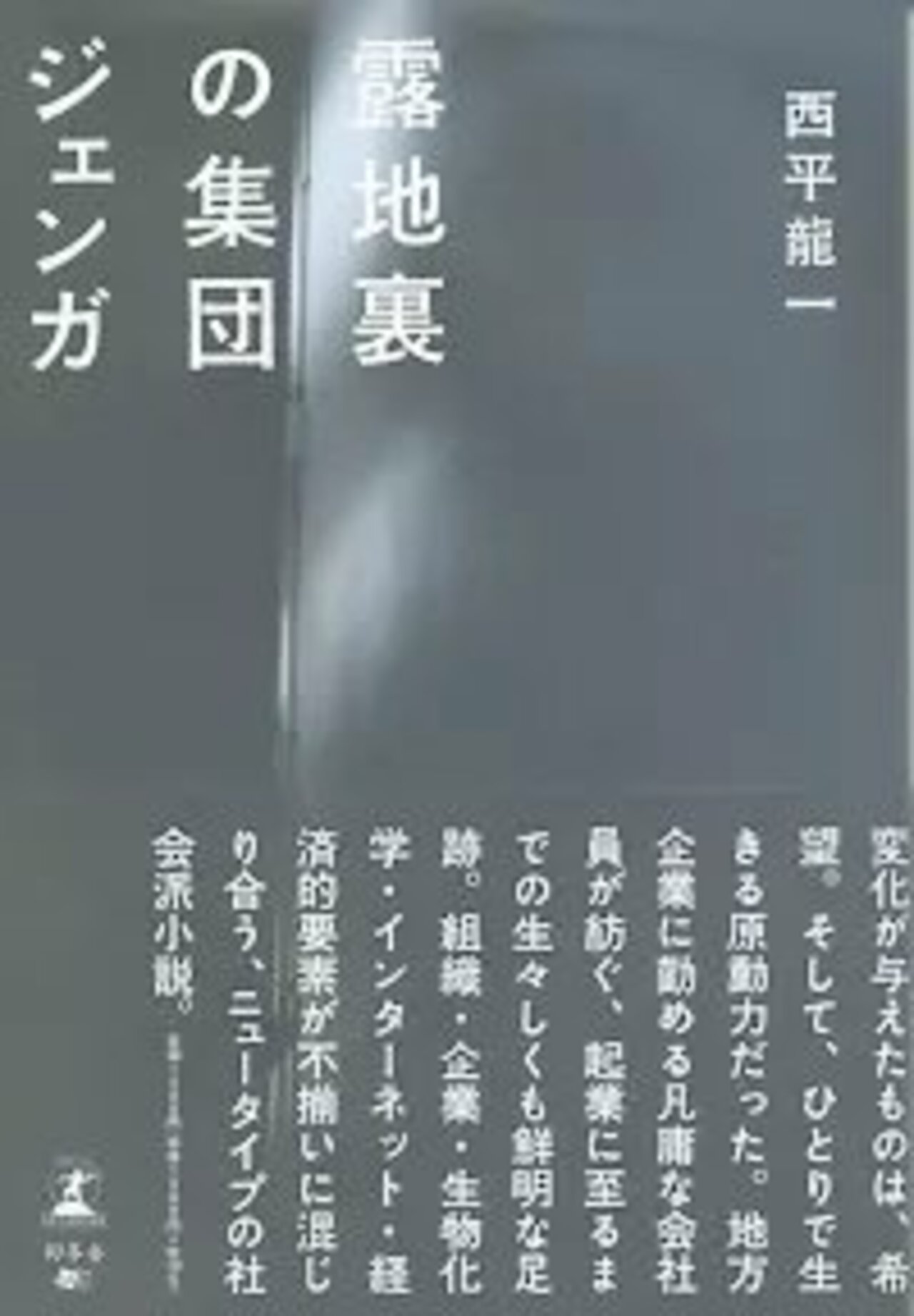第二章 ケータ
「川島さんていうたっけ? そらな。いつかおまえの嫌いな森ちゅう奴に嵌められるで」
ケータの勘はよく当たる。あまり論理的な表現はしないし、情報収集も得意でないのに、ケータの勘は不思議なくらいよく当たるのだ。
ケータとは、大学時代からの旧知の仲だ。それまで聴かなかった音楽を教えたのもケータだし、読まなかった小説を教えたのもケータだった。そして頻繁に酒を飲んだ。浅ましい貪婪な好奇心も、七色に光るような将来についても、ケータにだけは躊躇うことなく溌剌と話すことができた。
ケータには、常に多くの関心事があった。しかしそれは大抵僕や僕の周囲の関心事とは異なっていた。
例えば流行しているファッションだったり、割のよいアルバイトの求人情報だったり、人脈を広げたりすることには、異常なくらい鈍感だった。
ケータは、いま流れている音楽だったり、いま眼に入った本だったりに強く関心を傾けた。そして人にもそうだった。心の通った会話が好きなのだと、歯の浮くような言葉を平気でいつも言っていた。そして、「俺は実存主義者やねん」というのが又、頻繁に使う口癖だった。
ケータは僕の感情を、誰よりもよく理解してくれた。