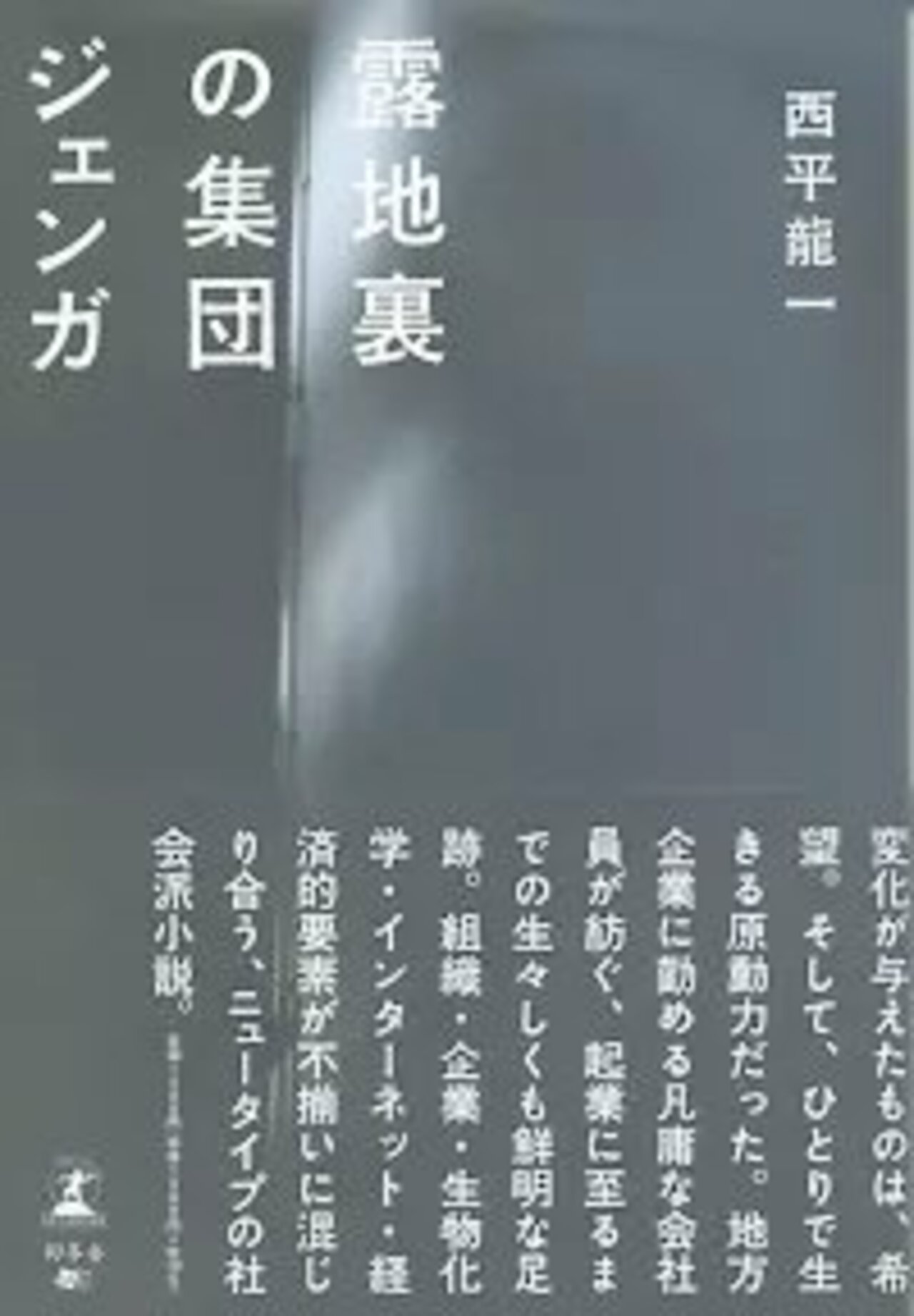第一章 洞穴の燈火
靴を履くと、ナツが音を立てて寄ってきて、毛糸で編まれた手袋を、そっと僕に差し出した。下を向いて受け取った。ナツは、爪が透明な。綺麗な裸足をしていて、ほのかにオーデコロンの香りがしていた。
「エリカはもう飽きてね。あいつは俺のいうことを。なんでもすぐに聞くんですよ」
森は、エリカとはもう二年以上もセックスだけの関係だと。ニヤニヤしながらそう白状した。
「あいつは単純でね。アッチのほうも単調ですから」
近くにはコンビニがあるのに、森はスーパーマーケットがいいんだと駄々をこねるように貫いた。冬の空っ風は、針で刺されたように顔をチクチク刺激する。僕は苛立ちを隠すように、小鼻を大きく膨らませ、上着のフードを深く被った。そして、ヘヘヘっと、口先だけで聞こえるように笑ってみせた。
森はトナカイみたいに鼻を赤くして、嬉しそうに僕を覗いている。ゆっくり上がる口角が見えた。
「エリカじゃなくてね。俺はナツがいいんですよ。家にはもう、四回目でしてね」
糸を抜かれた痛みのように、背筋が一瞬固まった。勘づかれるのを恐れたので、歩幅を大きく変えてみる。森にとってのエリカとは、ただの抱き合わせに過ぎなかった。
「前回はね。あーっと前回なので三回目で。これはめちゃめちゃ惜しかったのですよ。エリカはそのとき酒に潰れていてね」
森は歯と歯のあいだで唾液をだらしなくひいている。髭は不気味なくらい均一に整っていて、冷たく赤くなった指の腹で、何度もゆっくりと撫でている。そしてトリップしているような眼をしていた。
「ナツはね、警戒心があるので絶対潰れない。しっかりしているんです。けどね、エリカが潰れたときにね。これはって。いけるんじゃないかって」
森は細い目を大きく開いて、そして突然足を止めた。スーパーマーケットはまだ先だ。しかし僕にもそうするように、仕草を送って促した。
「アイツの家とナツの家は近いんですよね。前回は空気の読めないタクシー運転手でしたね。このまま帰れよっていってね。アイツをベッドまで二人で運んだあと、ナツを家まで歩いて送るまではさ。本当にイケる感じだったのにな」
今回はね。ちょっと心境としてはチャンスだと思っているんですよ。悲しそうで寂しそうな顔してるでしょ。ニシさんはどう思いますか? と、続けた。
エリカはいつの間にか、ずっとアイツになっていた。顔だけではない。体中がチクチク刺激されている。僕は毛糸の手袋を、外して森に差し出した。森は怪訝そうに僕を見て、それを黙って受け取った。
「今度はいけるんちゃいますか? あの子ね。さっきいろいろ話したんですけどね、髭の似合う男が好きっていうてましたから。あれ多分森さんのことやと思うな」
僕は上を向いてそう言った。科白には精一杯、真実味を含ませた。
「髭の似合う男って。そこら中にいますからね」
森は又、髭を触った。森の手は赤くて冷たそうだった。僕の手は、まだ温かかった。綺麗な裸足の残像と、オーデコロンの匂いはまだ残っている。
トリマーの「ナツ」のことは、なぜか八年経ったいまになっても、心のどこかで引っ掛かっていた。