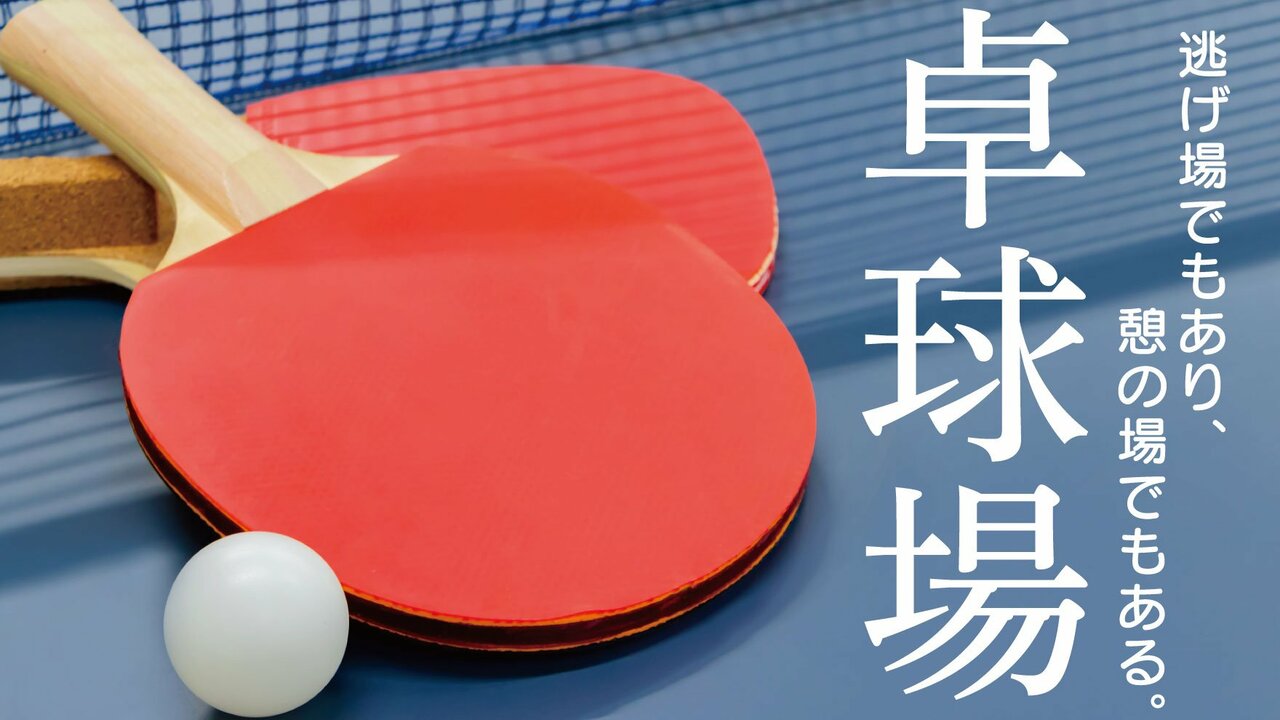三
先生がガラス戸を開けると、中は卓球場だった。三台の卓球台が並んでいる。
十人くらいの男女が、ラケットを振っていた。
よっ。あっ先生や。久しぶり~。しぇんしぇ。あちこちから声がかかり、皆が先生を歓迎した。年齢は様々で、八十歳くらいかと思えるお爺さんもいれば、三つか四つくらいの女の子もいる。
「せんせ。女の人、連れてくるの、珍しい」
「初めてちゃうか。彼女か」
「いえ、そんな。塾の教え子です。彼女、やなんて。そんな、とんでもない」
生真面目な返答に、頷けばいいのか笑っていればいいのか。
またまたあ。照れんでもええやないか。彼女さんやないって、それマジっすか。
ぐるりと見渡せば、ここにいる人たちは国際色豊かだ。どう見ても大阪のおっちゃんという人もいれば、アフロヘアーの子どももいる。スタイル抜群の女性は言葉から中国人のようで、東南アジア系の美女もいる。まさかゲイと思うようなバイセクシャルな男性。多分、二十代だろう。四歳くらいの女の子は綺麗な茶髪で、ピンク色の頰が愛らしい。
ワッツ、ネーム。いきなり聞かれて、朱里です。朱色の朱に里です。なんて堅苦しく答えてしまった。
「ジャパニーズらしい、ビューティフルな名前」
少女の母親だろうか、片言の日本語で笑いかける。
ありがとうございます。サンキュー、そんなひとことすら出てこない。
「せんせの彼女、べっぴんだね」
「べっぴ、べっぴ。ねえ、べっぴ。いっしょ遊ぼ。たっきゅ、しよ」
アフロヘアーの坊やが、私の手を握ってくる。色が浅黒く、まん丸い目をしている。