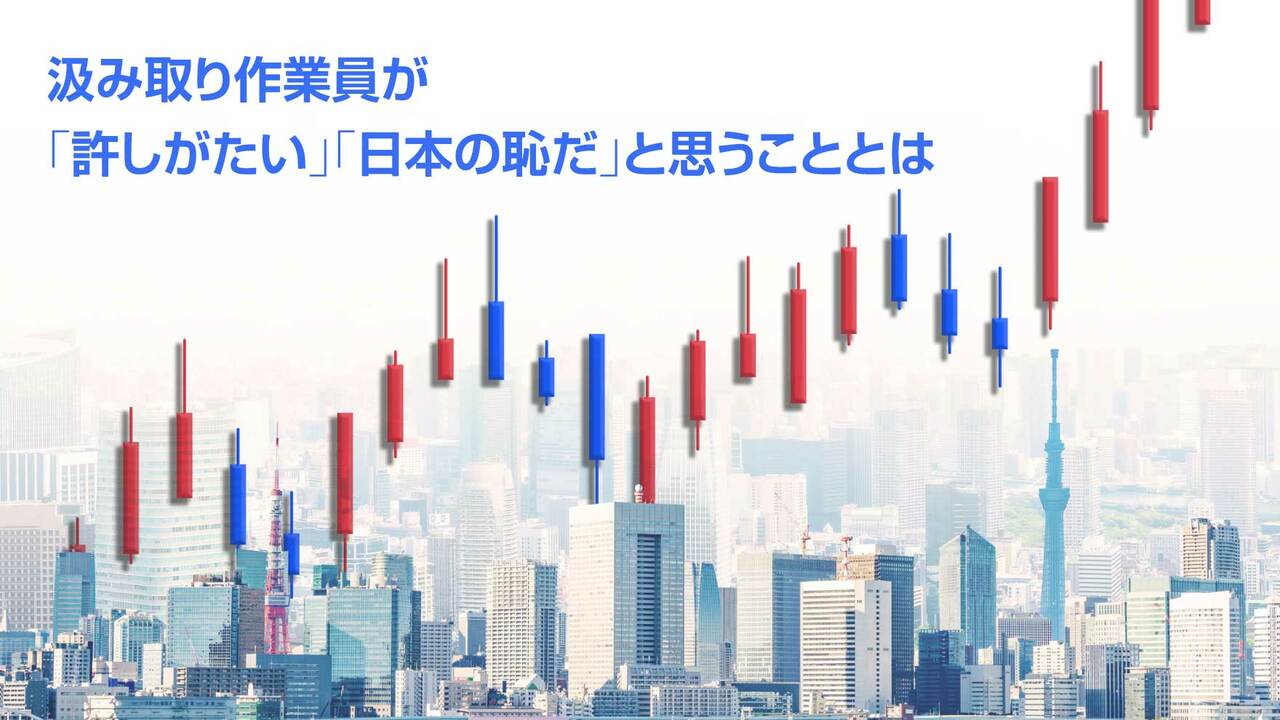赤線の町はオアシスでもあった
大型輸送機に載せられていたのは何十人もの重症の負傷兵と貨物室に積まれた無数のドラム缶だった。
「なんだ、負傷兵が送られてきたのか……」と納得していたが、アメリカ人の兵士と看護婦が負傷兵を基地内の病院に運んで行ってしまうので、西田の爺さんたちの出番はない。
機内に残されたのはドラム缶だけだ。どうやらこれを運ぶのが仕事らしい。
それで一人一人台車を持って輸送機の中に入るとなんとも嫌な異臭がした。吐き気を堪えながら機内の奥へと進みドラム缶の側に寄ると、缶の腹には白いペンキで何やら文字が書き込んであった。
よく見てみるとそれは何かの数字と朝鮮の地名、それから人の名前だった。「アレ」というのは戦死した兵士の死体だったのである。
古株の話では、通常死体は九州の米軍基地に船で運ばれて、そこにある専門の機関がバラバラに吹き飛んだ手足を縫い付けるのだが、アメリカ軍が戦闘で大負けすると九州だけでは処理できないため、横田基地に運ばれてくるのだそうだ。
そして通称「裁縫小屋」と呼ばれるオレンジ色の建物で死体に処理を施して、棺に入れてアメリカ本国に送還するということだった。
末吉はこの記事を読んで、「戦争の勝利のために人殺しの手伝いをして金をもらう。そして戦争で殺された人を運んで、また金をもらう。ああ~戦争は絶対に嫌だ」と思った。
ただ一瞬、「アメリカ政府にも戦死した人の遺体をできるだけきれいな状態で、家族に届けてやりたいという気持ちはあるのかな。もしそうなら、それだけが唯一の救いかな」などと思った。
しかし、現場(通称裁縫小屋)などで働く人は別にしても、結局は戦争を肯定してしまうことになるな。と思い返して首をブルブルブルッと激しく横に振って、「戦争は、絶対にダメだ」と叫んだ。
末吉が通った赤線の町は、戦場という地獄絵図を現実としたような場所へ送り込まれる若者や、国家から「国防」という美名の下に、生きることを否定されたような、それでいて崇高な使命感を持った人たちが、次の最終目的地に飛び立つために、羽を休めるためのオアシスでもあった。
そう考えると、末吉には赤線で働く女性たちがサゲスマレル存在どころか、何か崇高で輝かしい存在にすら思えるのだった。