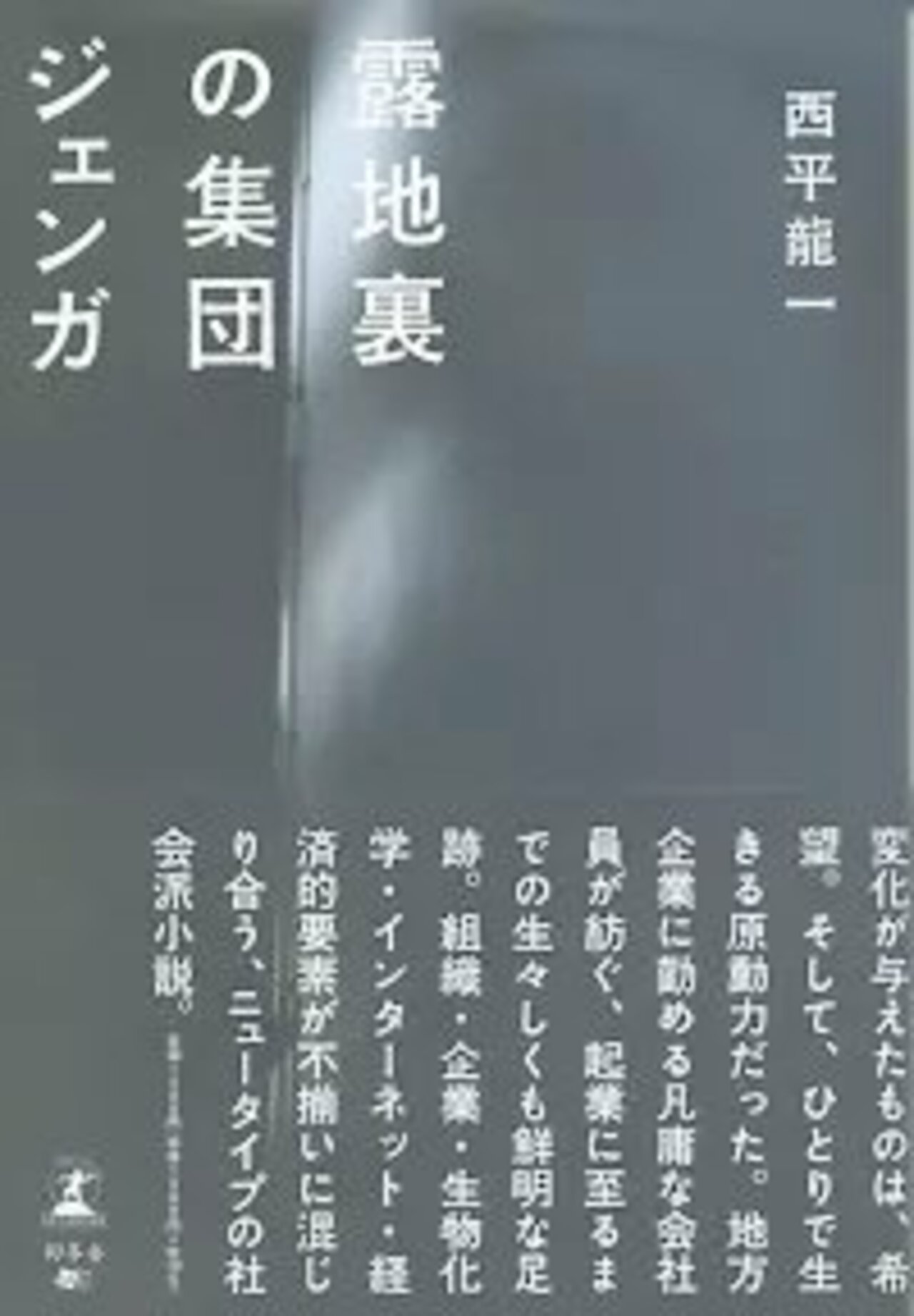第一章 洞穴の燈火
僕はいま殴られている。相手は十七歳の少年らしい。顔を覆うように防御しようとしたのだが、重たくなった左腕は上がらなかった。目の前が一瞬だけ暗くなる。それと同時に鼻っ柱には強烈な痛みが突然走り、刺激が明度を少し回復させた。粘り気のある雀色の物体が、僕の鼻から出た血の塊なのだとわかり、幼気だった少年の態度を回顧して、そして異様に腹が立った。
モップが掛かった黄色い布地は、滑るはずがないのにヌルリと靴底を動かした。背中の皮膚には、ゴムを介したワイヤーが食い込む柔らかな感触がする。足の力は抜けていて、体をうまく操作することができなかった。束の間を残して、再び少年の射程圏内に入ることになりそうだ。
ブザー音が鳴る前は、女性シンガーソングライターの好みの声が、有線放送から鳴っていた。しかしもう、それは聞こえなくなっている。
鈍い音がした。その瞬間に鼻腔の奥から錆びた鉄の臭いがした。打たれた骨の痛みより、呼吸が自由にできないことがつらくなった。鼻に詰まった固形物と血が絡まる。息吐く音が酷く目立って、吸い込む音もそうだった。
少年は耳を澄ませているほど冷静だ。僕の呼吸に合わせて、掬うように拳を鳩尾に鋭く刺す。血が吐瀉物と混じって、黄色い布地に糸を引いて垂れ落ちる。ロープにもたれて呑気に傍観していたトレーナーは、獰猛な眼をした少年に体をぶつけて動きを止めた。
デジタルタイマーは三分間まで残り一分四十五秒を照らしていて、女性シンガーソングライターの歌は、まだ間奏に入ったばかりだった。
鏡に映る顔は、削がれたように弱々しい。それは、頬についている肉がみるみる減少しているとかではなくて、蒼味がさして艶がなかったり、下瞼にしつこく張りつく影のせいだったりする。首が痛くて動かない。昨日少年に強く殴られたせいだ。際立つ傷がないことが、余計に心を惨めにさせる。
少年は小柄だったし、経験だって少なかった。そして何より年齢が、僕の丁度半数だった。