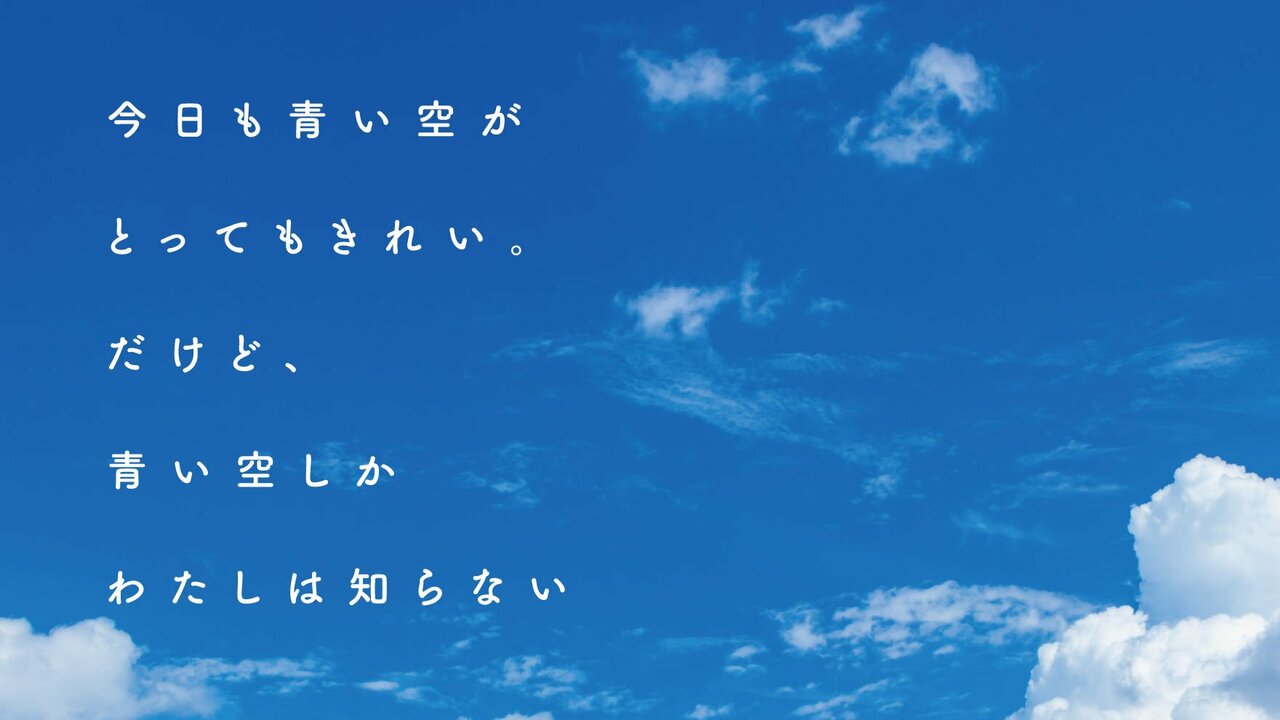きょうも、いつものように、ふたりで空をさんぽしていたときのことです。
「おい、ラーラ、もう少しはやくとべないのかい?」
リックは、おっとりしたラーラにいらだちをかくせません。
「わたしは、花の精なのよ。ふわりふわりとぶのがわたし流なんだから」
ちょっとむっとして、ラーラはこたえました。
「なあ、ラーラ。もうすぐきみの頭にあるつぼみが開きそうなんだけど、どんな花が咲くんだろうね」
ラーラは、またそのはなし? といいたいのをがまんしていいました。
「そうね。赤いバラがいいわ。バラの花のようにゴージャスにとびまわってみたいわ」
「バラだって! バラはとげがあるからぼくはあまり好きじゃないな。今の季節は秋だから、コスモスかな。うすいピンクのかわいい花」
ラーラのことなのに、リックはどうしても自分のことのように考えてしまうのでした。
「バラでもいいじゃない。それよりリック、下におりて少し休みましょ」
リックとラーラは、いつもあそんでいる湖の芝生の上にふわりとおりて、寄り添うようにすわりました。
この国には、ほかにもなん百、なん千種類もの妖精たちがいました。みんながなかよくくらしていけるのは、人間がすべての妖精たちを求めていたからでした。火には妖精が宿ると信じられていました。もちろん、風にも、水にも光にも。人間たちの目に妖精は見えません。しかし、信じることで人々の心は救われていたのです。そんな人間たちのすぐそばで、妖精たちは生きていました。
風はそよそよとときにはげしくうたいおどりながら四季のたよりを知らせてくれました。春には、風と花びらのワルツがはじまります。夏には、新緑の葉っぱたちが風とフラダンスをおどります。秋は、風と落ち葉のタップダンス。冬は、風が雪の結晶といっしょにバレエをおどるのです。
それらは自然の劇場となり、だれもがその美しさにうっとりするでしょう。
あたたかい人々のまなざしの中で、妖精もすべての生き物もおどることをとても楽しんでいました。人もまた、彼らのパフォーマンスに心をいやしていたのでした。