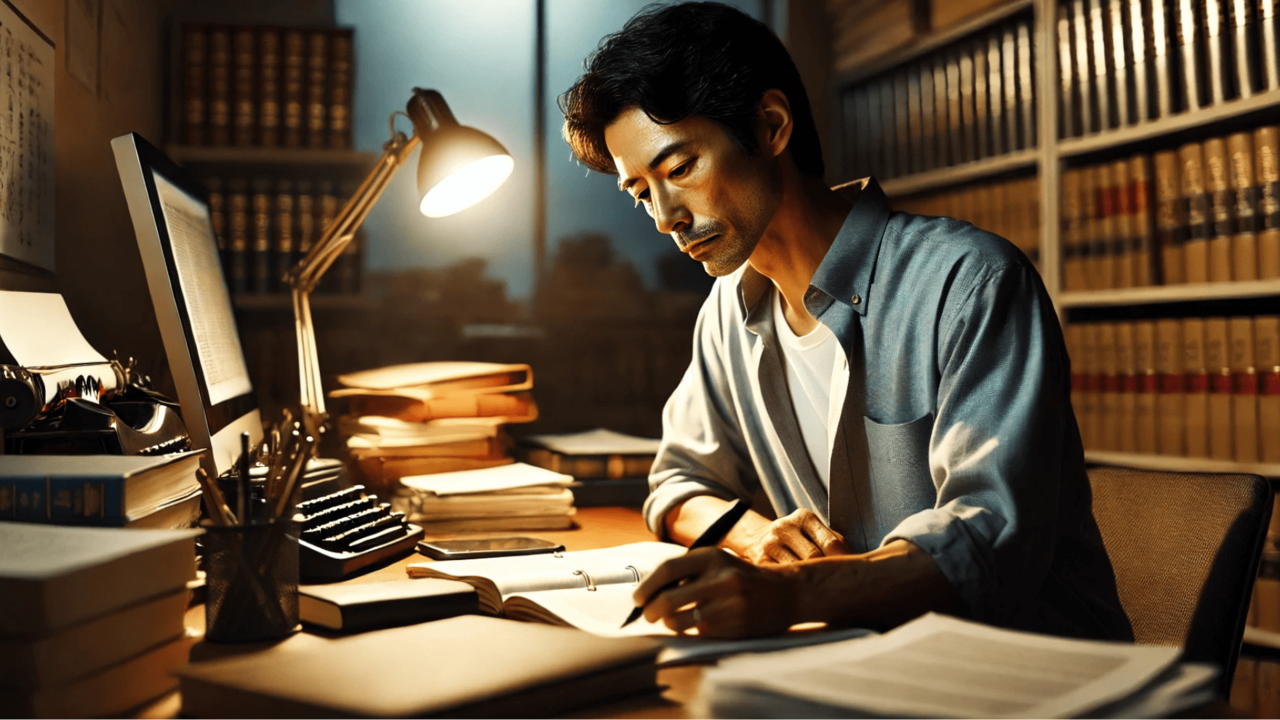「……たぶん、こうしてもらいたかったんだと思う。抱かれるんなら、ちゃんと抱かれることをしなきゃいけないと思ってたのかな。でも、そうじゃなくて、こういう腕枕とかがほしかった」
「そうか。気がつかなくて、悪かった」
「男の人には、そういうときはないの? 腕枕だけというのは嫌なの?」
「いや。こうしているの、気持ちいいよ、すごく。ただ」
「ただ?」
「僕のほうで、抱く以上はちゃんとセックスしなきゃ男として恥ずかしいみたいな思い込みがあった気がする。自覚していたわけじゃないけど」
「そうだったの。そんなことないのに。こんなふうに腕枕してもらってると、伸び伸びする。安心する」
「僕も」
「男だからなんて無理しないでね。こんなふうにずっと一緒にいられたらいいな」
「そうだな。百歳になっても、これなら大丈夫だし」
「うん」
「あのさ、僕も言っておきたいんだけど」
「何?」
「泣いていいから。ただし僕の横でだけ。僕以外の男の前では絶対に泣くなよ」
笑ってしがみついた。博史とはケンカをしても最後はいつも笑い合った気がする。
その後、夕食の食器の洗い物は深夜に帰宅した博史がしてくれることになった。
「台所のシンクに浸けておくだけでいいから。僕の分と一緒に洗うから」という提案に甘えた。それだけで、夕食後すぐに娘をお風呂に入れることができるので、とても助かった。
日曜の昼食は、博史が作ってくれる機会も増えた。メニューは和洋の麺類。
つわりのときにうどんを茹でてくれたことがあって、「こんなおいしいおうどん、生まれて初めて食べた」と、大感謝の言葉を連ねた。
パスタは「絶対、世界一おいしい」と、ほめちぎった。博史はまんざらでもない顔をして、茹で方のうんちくを披露した。
以来、麺類は博史の担当に決まった。娘も、その後に生まれた息子も「世界」という言葉の意味も知らないうちから「パパのチュパゲッチーはセカイいちなんだよね」と言って博史を喜ばせた。