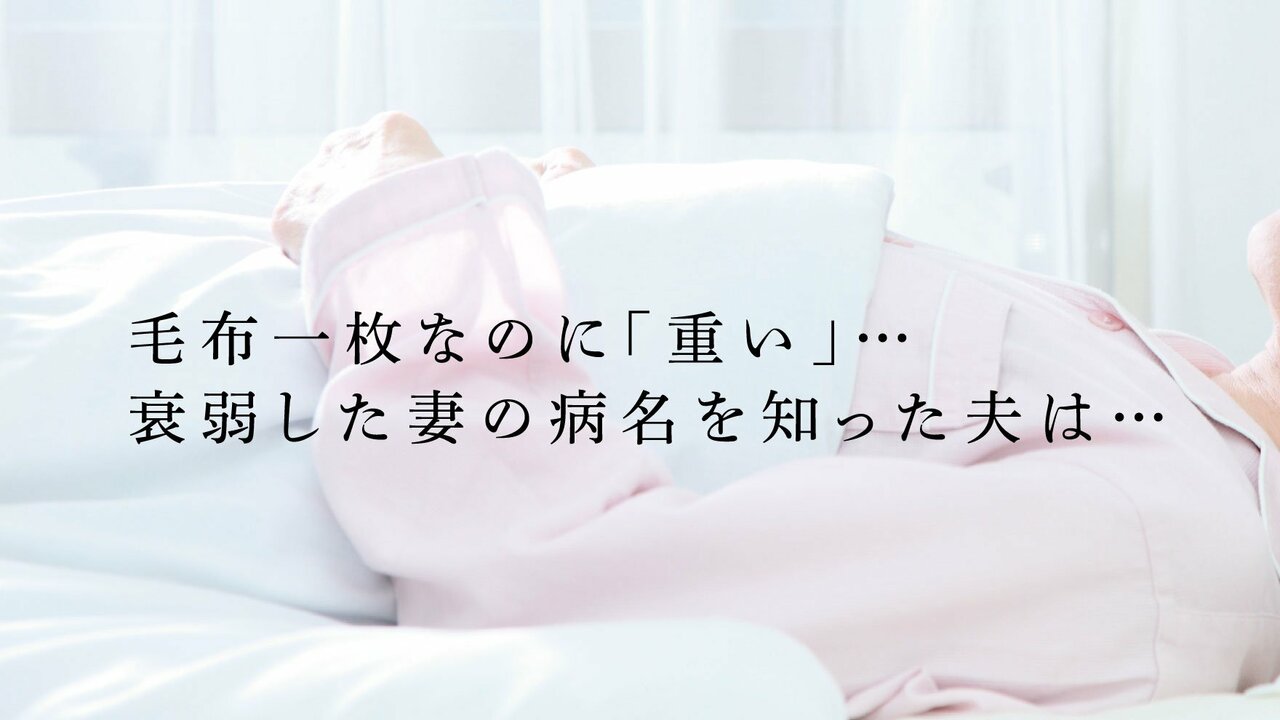母の認知症と妻のうつ病
母親の件が一段落しても、妻の「脊柱管狭窄症」の病気は一向に良くならない。そのことが、私の気がかりごとになり始めた。
「まだ手術するほどではない」「手術しても完治しない人もいる」「最後は手術がある」整形外科医院ではいろいろな言葉を聞いていた。思い切って、大学病院で検査をしてもらうことにした。それが二〇一八年三月だった。
一週間の検査入院で、髄液、血液、尿、及び便の採取、CT、MRI、筋電図と、京子は一日中検査の連続の中にいた。医大生に囲まれ、検査室から検査室へと向かう間、ストレッチャーの上に乗せられたまま、通路で検査待ちしていた。
「布団が重い」と京子は私の顔を捜しあて、言い出しにくそうに小声で言った。見ると毛布一枚で、ほかに何も掛けられていない。毛布が折り返されているところもないうえに、上に物が置かれているわけでもなかった。京子の言葉を漏れ聞いた医大生達は、互いに顔を見合わせ、「ALS……」とつぶやいた。
しかし、すぐに筋萎縮性側索硬化症(ALS)という病気の進行度と恐ろしさを飲み込むかのように、互いに何かを囁き合った後、私に向かって小声で言った。
「だいぶ筋力が弱ってますね」
さらに耳元で、「気の毒ですが、もっともっと進行しますよ」と告げられた。
「……」
私は検査の途中で病名を聞き、完全に言葉を失った。
『どうして……』
心の中に浮かんだのはこの単語だけで、言葉にならなかった。
『なんで……』
呆然とする頭の中に、反射的に浮かぶのは、文章にならない単語の羅列だけであった。
『京子と俺は、何か悪いことをしたのか?』
次に湧き上がってきたのは、自責の念であった。しかもその時は、まだ具体性はなかった。
「なんで京子が?」
それだけが、うめくような小さな言葉になって、外に出た。私が知っている限りでは、京子がやましいことをして生きてきた記憶がない。
『それに引き換え、自分は仕事上で、気付かぬうちに不道徳なことをしていたかもしれない』
『何もかも、……京子が悪いのか? そうではなかろう、……』
天の裁きを目前にして、これまでの生きざまを瞬時に振り返っている自分がいた。