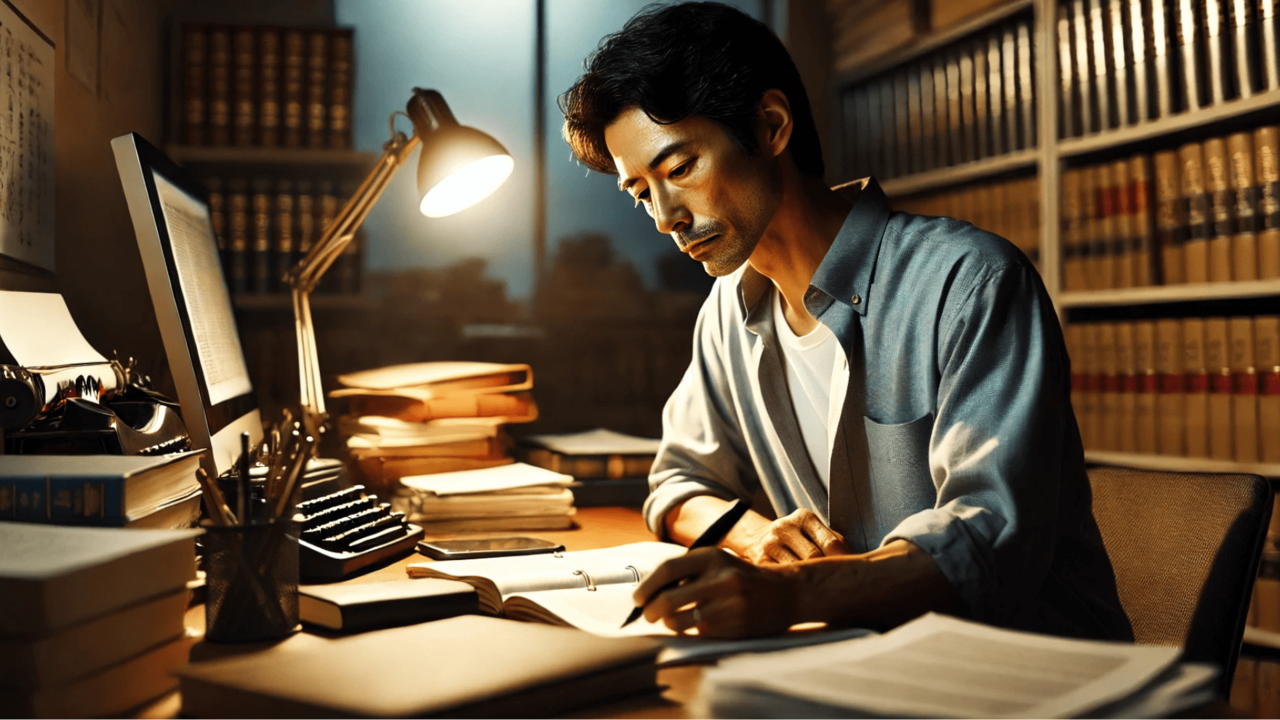発熱騒動以来、博史は以前より積極的に育児を手伝ってくれたし、私も倒れる前に頼むようにした。頼みすぎたかもしれない。「僕だって、今は大変なんだ」と、博史が言ったのである。
「授業だって、毎回、怖いし。準備してもうまくハマらないこともあるし」
初めて聞く弱音だった。彼が毎日授業の準備を一生懸命していることは見ていた。ときには「ちょっと聞いて」と言われてリハーサルに立ち会ったこともある。それで、どんなときでも彼は楽しそうに授業準備をしている、と思い込んでいた。
私が大学時代に受けた授業の中に、立て板に水という講義をする教授がいらっしゃった。江戸川柳の授業ということもあり、笑いが絶えなかった。ところが、あるとき、一人の学生が研究室を訪ね、ノックしようとしたところ、部屋の中からブツブツ言う声が聞こえてきた。その先生は講義のリハーサルを何度も繰り返していたというのである。
そんな話を、博史にした。すると、翌日には「聞いて」と、原稿を手にしてきた。講談よろしく、
「そもそも日本国憲法と申しまするは、時は一九四五年八月十五日、昭和天皇が『耐えがたきを耐え、しのびがたきをしのび』と言って受諾したポツダム宣言により要求されましたところの」
「バン、ババンバン」
口で張り扇を入れた瞬間に、「ダメだ、こりゃ」二人して噴き出してしまった。
「この調子では、基本的人権まで行きつかないよ」
「あなたらしくやったらいいんじゃない?」
「その僕らしい授業がわからないから、困ってるんじゃないか」
「大切な用語は『ここ大事です』と念を押して、もうちょっとゆっくり。早口にならないで。板書もいいと思うんだけど」
「知ってるだろう。字、下手なんだ」
「読めればいいのよ。それと、一方的に話さないで、時々『これ、わかりますか?』とか尋ねてみたら、学生さんも聞く気になるんじゃないかなあ」
話しながら、私は大いに反省した。彼が授業に苦しんでいることを知らなかった自分を恥じ、申し訳なく思った。彼は、試験問題にも、ひと工夫もふた工夫もしていた。例えば、記述問題。早稲田太郎君と西原花子さんが何らかの問題で対立し、最後に早稲田太郎君が
「ほれやったら、あんたはんの言い分、言うてみとくんなはれ」とか言って、
「問題 両者の言い分と、あなたの考えを、法的根拠に基づいて述べよ」につなげる。
「この京都弁、これでいい?」と、問題文の下書きを見せにくる。
「これ、京都弁とちゃうわ」添削して
「それやったら、お宅さんの言いたいこと、言うてみてください」に直した。
「けど、京都弁を使う必然性はあるの?」
「読んで面白ければいいんだよ。興味を持ってほしいんだ」
また、試験後には、数百人の答案すべてに朱筆を入れて、返却した。
「反論のある場合は、研究室に来てください」とも言っていたので、単位を落としそうな学生が研究室にやってきて、粘る。博史は、丁寧に付き合う。昼間は細切れにしか時間が取れないので、授業後の午後九時以降が面談時間である。毎日のように終電になり、帰宅は午前二時を過ぎる。それでも「今日は、骨のある子が来てさ」と、うれしそうだった。
博史は、真面目に真剣に必死に、仕事をしていた。どうすれば、学生に興味を持たせて向学心に火を点けることができるのか。学生の脳裏にしっかり刻み込むことができるのか。そのための努力を惜しまなかった。