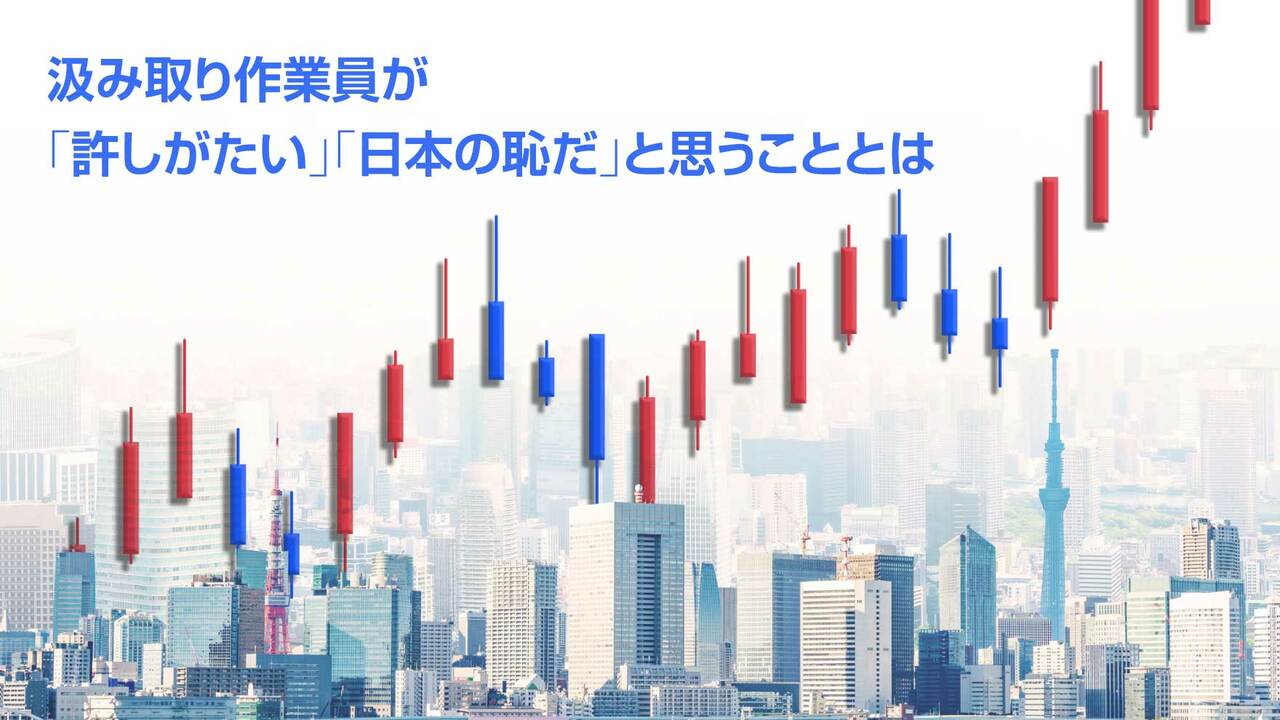末吉は、そのとき農家から礼として、米や野菜、味噌や卵などをもらった。当時は戦後の食糧難の時代だったが、そのおかげで佐藤家は、食べる物に困ることはなかった。
末吉は、戦前は一流機械メーカーの技師兼工場長として働く、いうなればエリートだった。それが戦争で会社が潰れ、今は便所の汲み取りをしている。一昔前ならば、蔑まれた仕事だ。事実二十一世紀になった今も、この仕事に差別意識を持つ人は多い。末吉も家族も
「うんこ屋。うんこ屋の子ども」
とはやし立てられることもあった。しかしその当時の末吉には、そんなことを気にしている余裕などなかった。とにかく家族を養い、守らなければならなかった。
紘一も親の仕事が原因で、からかわれたり、いじめられたりした。しかし、紘一は父がどれほど苦労をして、自分たちを養ってくれているかを知っていた。そして、そのおかげで他の家より、むしろ裕福な暮らしをさせてもらっていることに感謝していた。
だから、紘一は進んで末吉の後を継いだ。その後、西方町が西方市として市制発足したのをきっかけに、市内の屎尿処理は、完全に市の業務として掌握され、下水道課から清掃課に業務移譲された。そして、屎尿の汲み取り屋の仕事も、「屎尿収集運搬業務委託」という市との委託契約が結ばれ、市の委託業者として仕事をすることになった。
また、周辺三市が合同で清掃組合を作り、そこが管理運営する屎尿処理施設を整備した。そして、そこですべての屎尿が、科学的、機械的処理を衛生的にされることになり、収集運搬も完全にバキュームカーによる機械収集・運搬のみが許されることとなった。それによって、汲み取り屋は、市民との直接の商売は、事実上できなくなった。
藤倉産業は、こうなることを役場の人間から聞かされていたので、町制の時代から、バキュームカーを導入していた。
そして、市政発足と同時に有限会社に法人化して、父の末吉は会長として一線を退き、息子の紘一が初代社長に就任した。また手伝いとして来てくれていた人たちとも、会社の社員として正式雇用契約を結んでその生活を保障した。
会社としての体制をすぐに整えたおかげで、西方市の入札指名参加の許可が下りた。その業務の特殊性と、戦後すぐの頃から一貫してこの仕事を継続していることなどが評価され、毎年の入札による業務受注ではなく、随意契約の形で、永続的に仕事ができることになった。
今でこそ、一般に重要視され語られることの多い「サスティナビリティ(持続可能性)」の高さが、特に公共性が重視される業務には欠かせないものといえ、藤倉産業は、その点ではこの時点で、他を圧倒的にリードしていたと言ってよい。その結果、この業務の委託契約を取れたのは、藤倉産業だけであった。
その結果、水洗化はしているものの、依然として下水道につながずに、浄化槽(各施設、建物ごとに、屎尿を処理する設備)で処理し、汚水槽に貯留しているところ、たとえば市民会館や各公共施設で、イベントなどがあって一挙に大人数の人がトイレを使うと、何十トンもある貯留槽がすぐにいっぱいになるので、大型のバキュームカーで一日中、何往復も施設と屎尿処理場を走り続ける仕事が頻繁にあった。
おかげで、その収益は莫大なものになり、大型バキュームカーの購入代金、当時の金額で二百万円を一週間かからずに払い終えることも可能なほどだった。