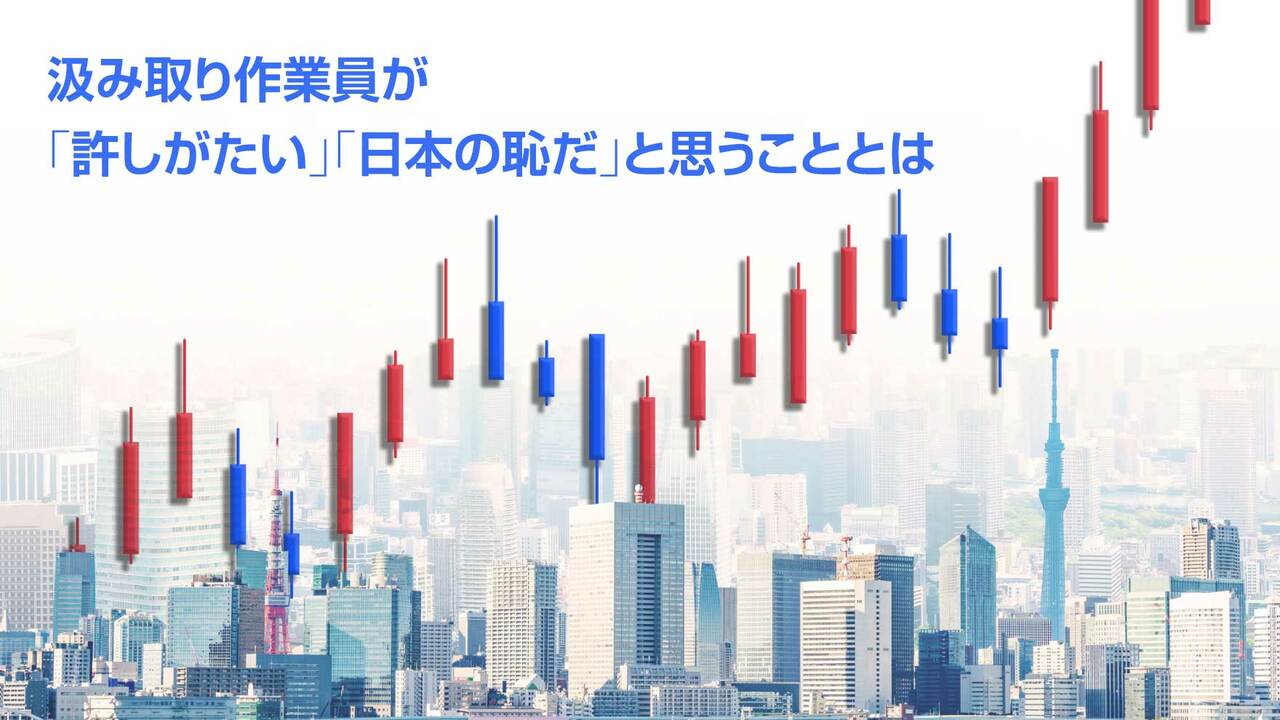また、ある一部上場の大企業は、障害者雇用促進法で定められた、障害者の雇用率をクリアしようと、自力で通勤できて、自力で勤務でき、学歴のある健一を本社工場の作業員として採用した。そしてある部署に配属したが、そこで求められる精密な作業を健一にさせるわけにはいかなかった。そうかといって、居てもらわなければ障害者雇用率は下がってしまう。
そこで会社は、精密機器の操作とは直接関係のない、英文の工作機械のマニュアルの翻訳を健一にさせた。健一の大学の専攻は法律である。ましてや言語障害だった健一は、語学には中学の頃から拒絶感を抱いていて、高校のときなどはいつも赤点スレスレでしのいでいたほどだった。
それに中途で採用された障害者の給料は、極端に低く、とても夫婦で生活できるレベルではなかった。そう、健一はまともに就職もしていないのに、無謀にも結婚していたのだった。そして妻の良美は、リウマチと再生不良性貧血という難病を二つも抱えて苦しんでおり、とても働ける状態ではなかった。健一はわずか数か月でその会社を辞めた。
そんな健一を今の会社の社長、佐藤紘一は、ただ「頑張れ」とだけ言って雇ってくれた。そして、他の社員とまったく同じに仕事をさせた。当然、健一には初めからすべてをこなすのは、無理だった。
そして社員からはいじめられた。それは、かなり悲惨なものだった。会社の主な仕事は、市民が出す生ゴミや、ビン・カン・ペットボトル・段ボールなどの資源ごみを各家庭から回収して、清掃工場に運ぶ仕事だった。その他にバキュームカーでのトイレの汲み取り作業もあった。
健一は慣れない作業のせいもあって、よく捻挫した。その腫れた足首を安全靴で蹴られた。また、通勤用のバイクを壊されたり、歪んだ顔や震える手のまねをされて、からかわれたりもした。また、嫌なトイレの汲み取りの仕事があると、みんな健一に押し付けた。
それでも健一は、他には雇ってもらえるところはないと思うと、ひたすら耐えるしかなかった。バキュームカーの運転や操作は、定年間近の先輩であった内村のやり方やマニュアルを見て覚えた。そして内村が退職してからは、健一ひとりに押し付けられた。それでも社長の紘一だけは、自分が手伝うと言ってくれた。