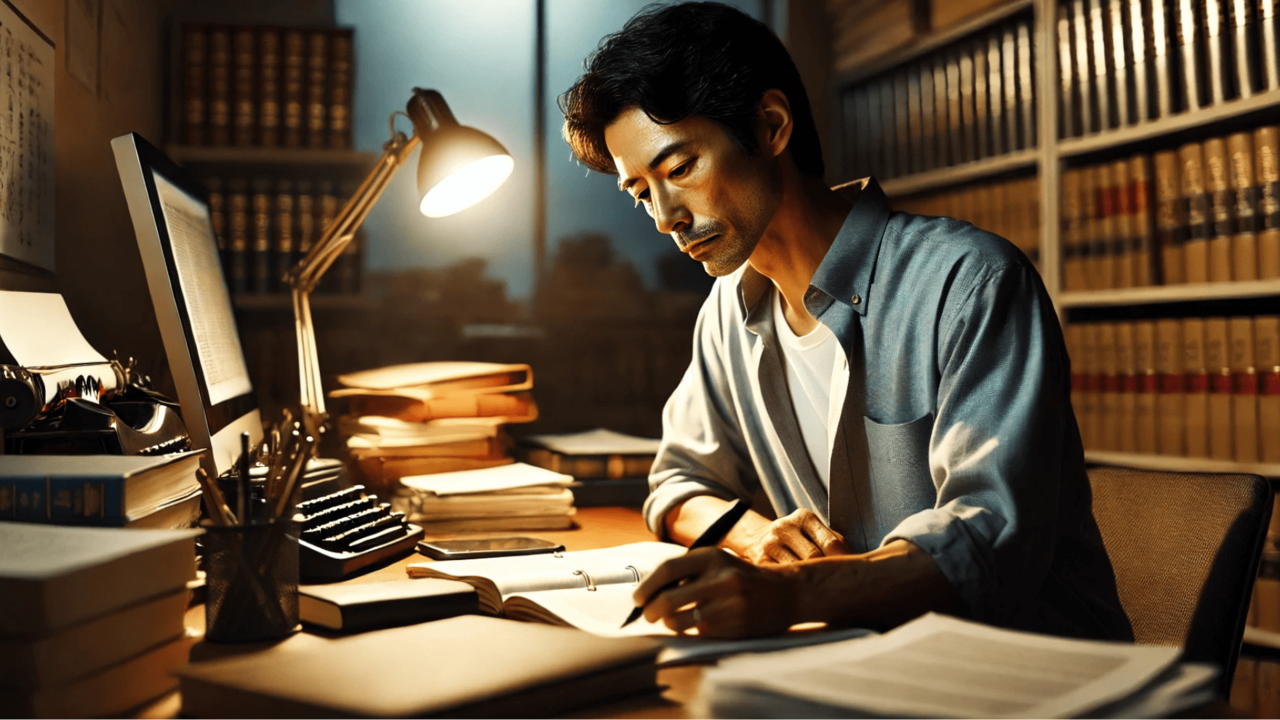走り出た。寝台車の助手席から義父が降りるところだった。黒服の男性が二人がかりで後部ドアから担架を運び出そうとしていた。担架には、白い布が掛けられていた。二人は、傍らに立つ私に一礼すると、慣れた手つきで丁寧に担架を家内に運び入れた。そして、博史を、夫の体を、布団に寝かせた。
「どうぞ」という言葉の終わりまで聞かずに、私は手を伸ばした。博史の顔に触れた。
はっとした。
冷たい。想像もしていなかった冷たさだった。もう一度触れ、冷たさと硬さに驚いた。とんでもない冷たさと硬さだった。
生きている人ではなかった。血の通わなくなった体だった。
鼻が、博史の顔の特徴である大きな鼻が、骨ばって高く盛り上がっていた。鼻の孔には、ガーゼが詰められていた。目が閉じられ、まぶたが窪んでいた。
私の知っている寝顔ではなかった。寝息が聞こえない。表情がない。
「博史さん」
声をかけてその頭を両手で包み込もうとしたとき、
「ああっ、いかんっ」
義父の小さいが、はっきりした声がとどめた。それまでに聞いたことのない厳しい声だった。
一瞬のうちに、思い知った。博史はもう、ただ寝ているのではない。起こそうとして揺すぶったりしてはならない、壊してはならない体、として存在しているのだ。
私たちの結婚生活は、終わった。二人で共に歩んだ人生は、二十六年と七カ月で止まった。
第二章 結婚
Nissie西原博史
博史と私は、インターネットのサークルで知り合った。私が一九九〇年一月に入会し、博史が三月に入会した。
そういうと、近頃では「ええっ」と驚かれるし、我が子ですら「ママたち、そんなとこで出会ったの?」と、いかがわしいものを見る目をする。だが、私たちが出会った頃には、いわゆる「出会い系サイト」なるものは存在しなかったし、パソコン人口自体が多くはなかった。男女の出会いの場として活用されるのは、後年もっとネットが普及してからである。当時は、真面目な情報交換と交流のために使われ始めた時期だった。
西原博史は一九五八年九月七日、東京都で生まれた。
父の春夫は当時、早稲田大学の専任講師だった。母の幸子は早稲田大学の法学部を卒業して一時期デパートに勤めたが、博史が一歳になる頃に退職し、専業主婦になった。
博史が五歳のとき、父がドイツのフンボルト財団の助成を得てフライブルク大学に留学したため、一家で渡独。博史も現地の幼稚園に通った。
本人は「そのときに覚えたドイツ語は、グーテナハト(お休みなさい)くらい」と言っていたが、大人になってもドイツ人からはよく「発音が良い」とほめられていた。帰国後、小学校に入った。その頃の写真を見ると、丸々と太っている。
体型だけでなく「いつも、ぼうっとしているような感じ」を心配した父が勧めて、剣道を習い始めた。良い指導者に恵まれ、地元の中学校と早稲田学院高校では部活に剣道部を選んだ。高校三年生のときに三段を取得した。
大学は内部進学で、法学部を選んだ。しかしまだ、法律の道に進むと決めたわけではなかったそうだ。