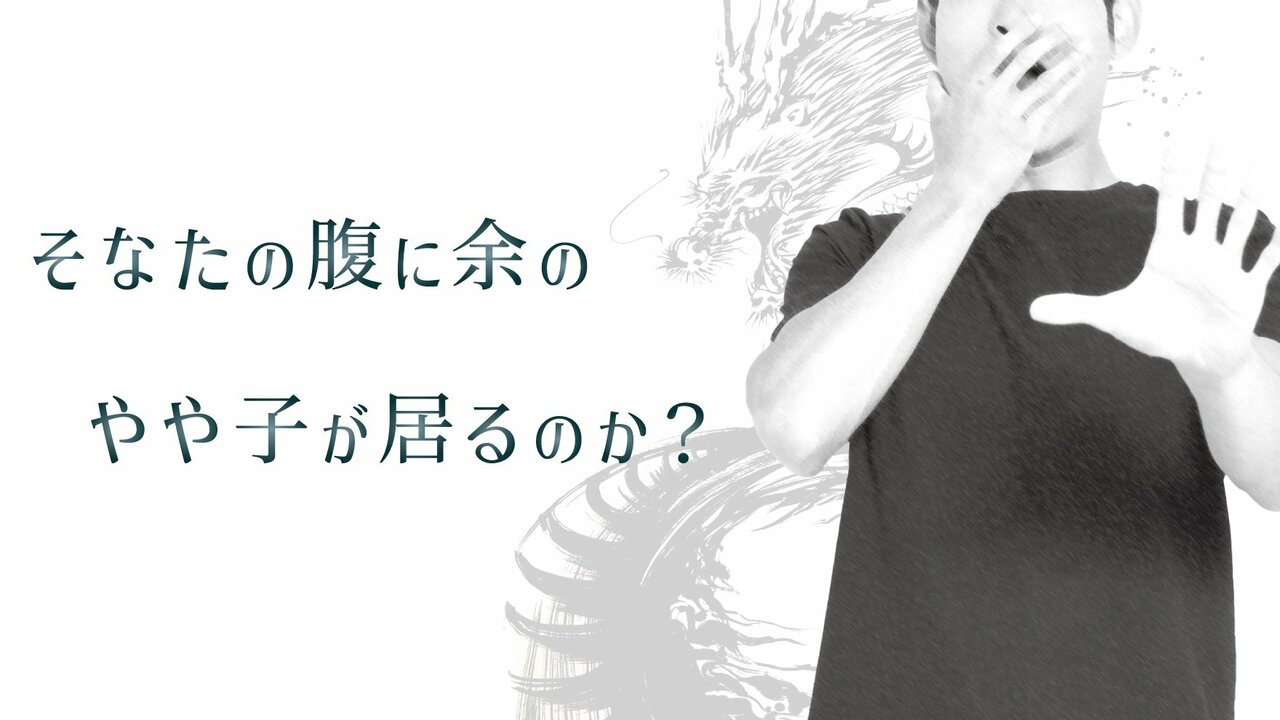「もう……いい加減にしてー」
紗久弥姫は今まで父親以外の異性に手を触れられたことがなく、ましてや強引に手を掴まれ、突然裳を触られ、恥ずかしさのあまり若者の顔を思いっきり引っ叩いた。
「い、痛い! 何をするのだ?」
「無礼をはたらいた当然の報いです。わたくしは奥宮の館へ帰ります」
「ま、待つのだ」
青龍は紗久弥姫の前に立ち塞がると、紗久弥姫はくるりと身を翻した。
「おろかな人のわたくしに構わないで下さいませ。姉上様と一緒に敵討ちをします。敵の一人と刺し違えても構いません。父上様や幸姉上様の元に行けるのなら、死ぬことなど畏れません。むしろ嬉しく思います」
「な、なんと? そなたは相打ちをして死ぬ? 与えられた命を粗末にするとは……。そ、そなたともそっと話がしたい」
紗久弥姫の瞳から大粒の涙がポロポロと落ちた。
「何で泣く?」
「私は名乗りましたが、貴方様は名前を名乗ることはせず、汚らわしい人間の話を聞く耳はないと……。即刻この場から立ち去れーってわたくしを叱りました。今度は帰ろうとするともう少し話がしたいとは……」
「わ、悪かった……。許して欲しい。余は話すのが苦手なのだ。とくに女人には……。天女にも声を発したことがない。つい、いや、これは弁解すべきではない。名を名乗らなかったことを詫びよう。余の名は青龍。粋明天青龍だ。龍族で、龍王の末の皇子だ。そなたは何度も余を神と申していたが、龍族は尊き天に仕える眷属である。龍王は十二の神将様をお守りし、眷属達を束ねる長なのだ」
「眷属って? 清姉上様が教えて下さった天上界にいらっしゃる天や神様を守護する十二支の! あなた様は龍王様の皇子様……?」

「さ、紗久弥姫……。よ、余の妃になってはくれまいか?」
「えっ?」