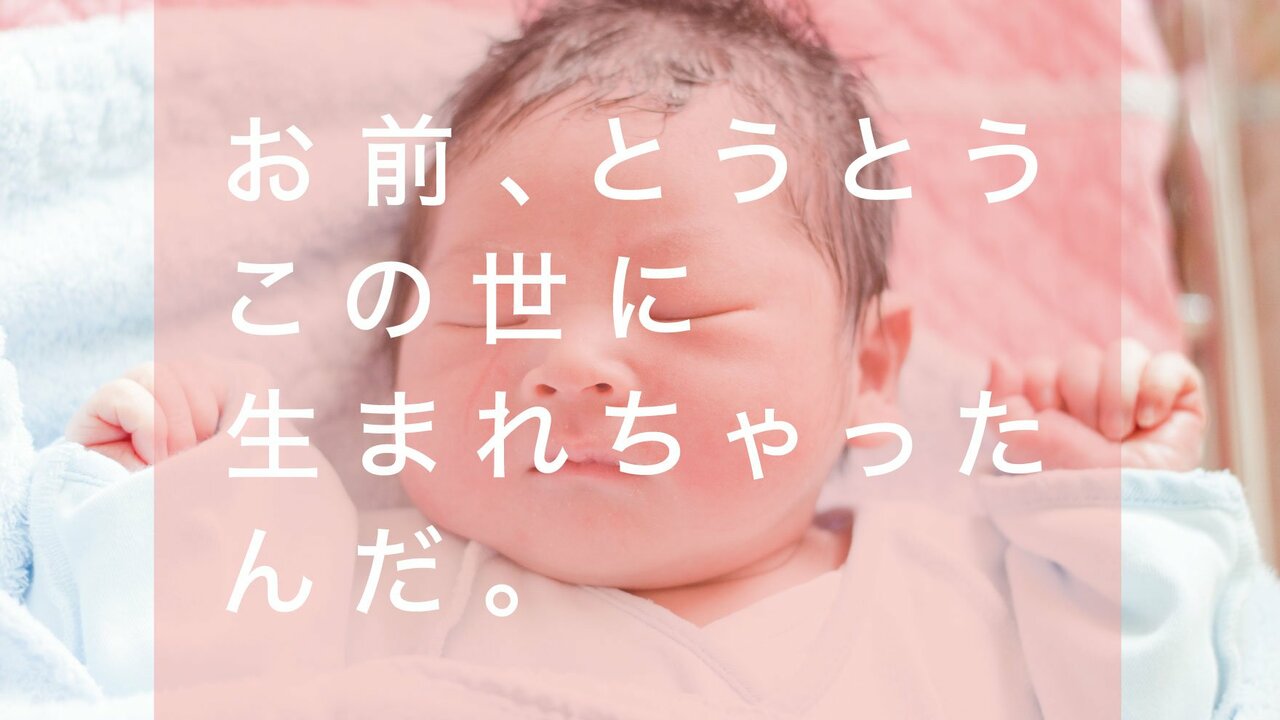照明に気を遣わない画家は多い。気を遣う必要もない。ただ八汐が心地悪いだけで、自然光じゃないと色を塗ることができない。朝が早くなると寝不足じゃないかと心配するから
「その兆候はない。不足だったら休みの日寝坊すればいい」
意欲が空回りして、背景の色がどうにも定まらない。構図は決まっている。工房の、それに合わせてシェルターの高さが決まった製材機や乾燥機、接着機や圧縮機、彫刻やかんな掛けや建具制作などの工作機で鉛直線と水平線を出して、それを背景にジムの様々な肢体を陰影を出して描く。『工房の隅のジム』。
三週間も、機械の色や工房の照明や暖色にしたい誘惑で迷って、画帳のテストを繰り返した。広くなると色の印象は違ってしまうし。これが苦しいのだった。けれども苦しまなければ発見できないことは学んだのだ。
夜桜を眺めながら公園や川の堤や名物の古木の下を逍遥した。月光があったり、ランタンが吊るされていたり、夜店の照明があったり、人々は陽気にさざめいていた。
二人は夜風を楽しみ、互いの体温を懐かしんだ。吹雪いて散る夜、今夜で終わりだねと頷きながら。
頭の中で下の方に寂しい暖色を、上の方に叢雲と月光を、背景にコラージュしてみた。
親父の許可を取って、親父は水臭い奴だと苦笑した、工房の機械使うから、太洋に額縁を作らせた。絵より出しゃばるなよ。絵見ないとわからない、もう家教えろよ。淳さんに訊かなくちゃ。淳さんは俺のこと好きだから大丈夫だ。勘違いするなよ。義理の弟だから優しくするんだからな。絵を持ち出すのも太洋を家に連れてくるのも危惧されたので画集から淳さんに決めてもらってそいつをコピーして、これに似せて。太洋は大いに不満で断られそうだったので、お前が真ん中にいるんだぞ、と気を惹いたら、口を尖がらせて時給一万だと吹っ掛けてきた。いいよ。