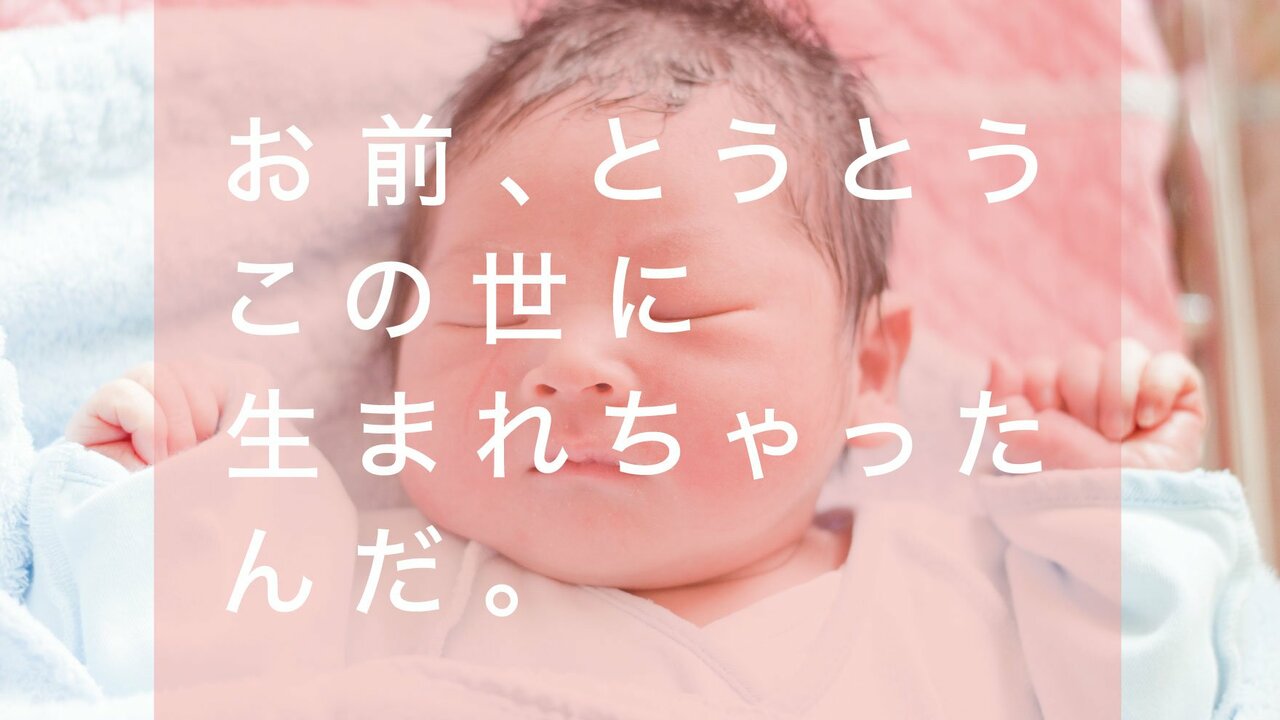ロビーの自販機で温かい缶珈琲を買う。あの子、と思う。人がいいのね。よくまあおばさんのこと覚えていてくれて。重たげな瞼で、伏目で。背が高いからかな。気が弱いのかな。玄関フードで待つ間もなくきっかりにライトバンが入ってくる。なんか嬉しい。
「偉い人になった気分」
珈琲でよかった? 向こうが向こうが狼狽える。
「あ、飲んできた?」
「いや」
ぶっきら棒め。ぷしゅぷしゅと同時にプルタブを鳴らしてほっと一息。
「帰る?」
「ううん。おかげさまで間に合うから、保健所で三時からお勉強会。適当なところで降ろして。ここでも」
「回り道でもない」
保健所まで送られて
「ゆとりでした。今日は本当に」
「何時に終わるの?」
「予定は五時。だけど、本当にもう大丈夫。ご親切様。恩に着ます」
「……じゃあ……会社まで送るから……そのあと……飯いっしょは?」
変な子、と思う。
「会社って、うちなの」
親切の押し売りだったかな。食事して帰るのもいいけれど。邪慳に断るの気の毒だし。
「半日わたしに付き合ってくれて、時間が勿体なくない?」
「仕事は……いいんだ」
どういいんだか。今時の若者風なのか、軟派って言うのか、わからない。講演は都の神経病院の医師によるALSの医療の現況報告だった。これはこれでどこかに記録しておかなければならない。
大ホールに何千人も集めて高いところから内容空疎で退屈な講演をなさる偉い人も多いが、この年若き医師は、パイプの折り畳み椅子を七、八十並べた保健所の殺風景な一室で車椅子のALS患者も十人くらい、付き添いの家族やボランティアのわずか五十人ばかりに、同じフロアに立って、この病を得て生き延びることについて、人とサイエンスとアートについて、熱心に語りかけたのだ。