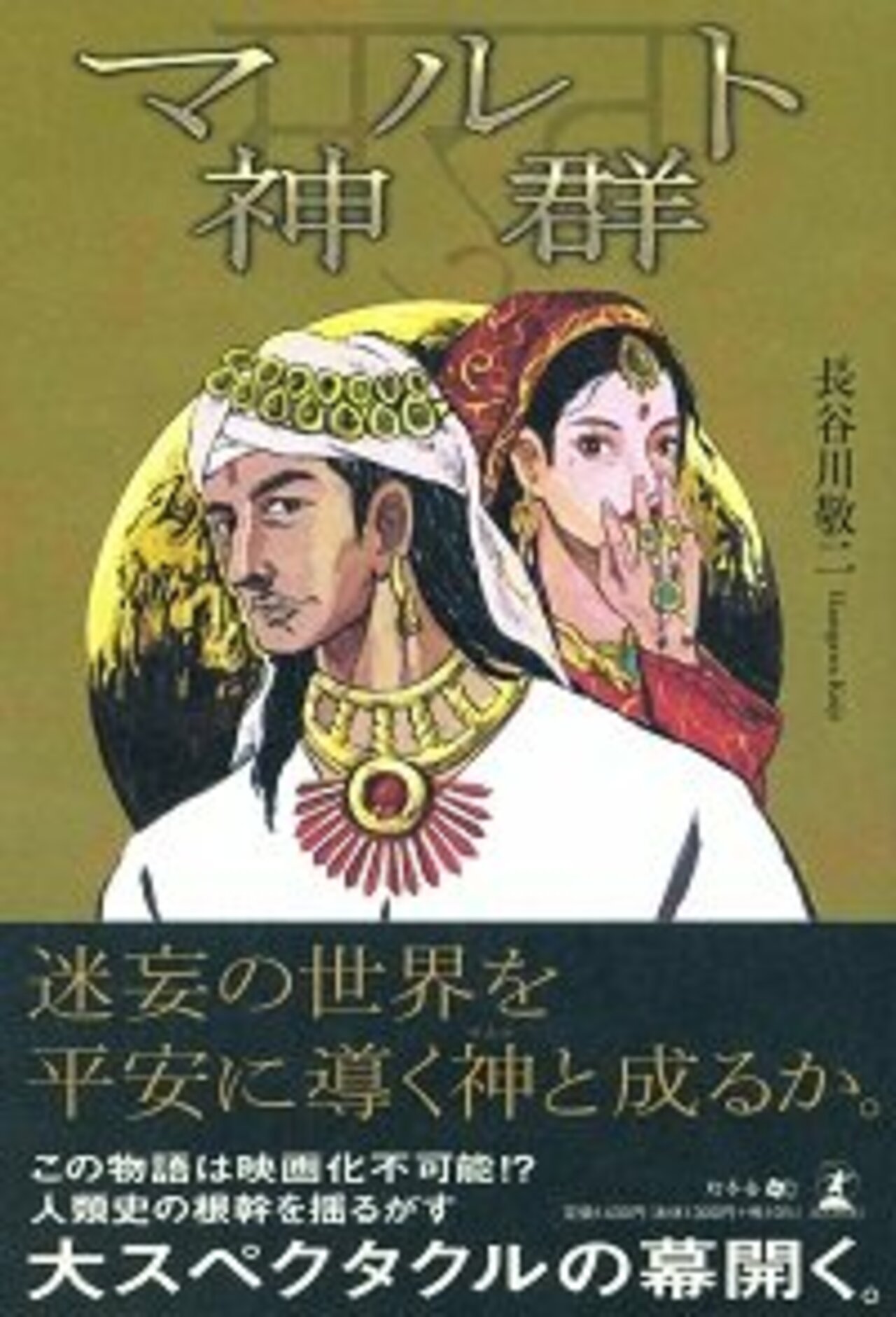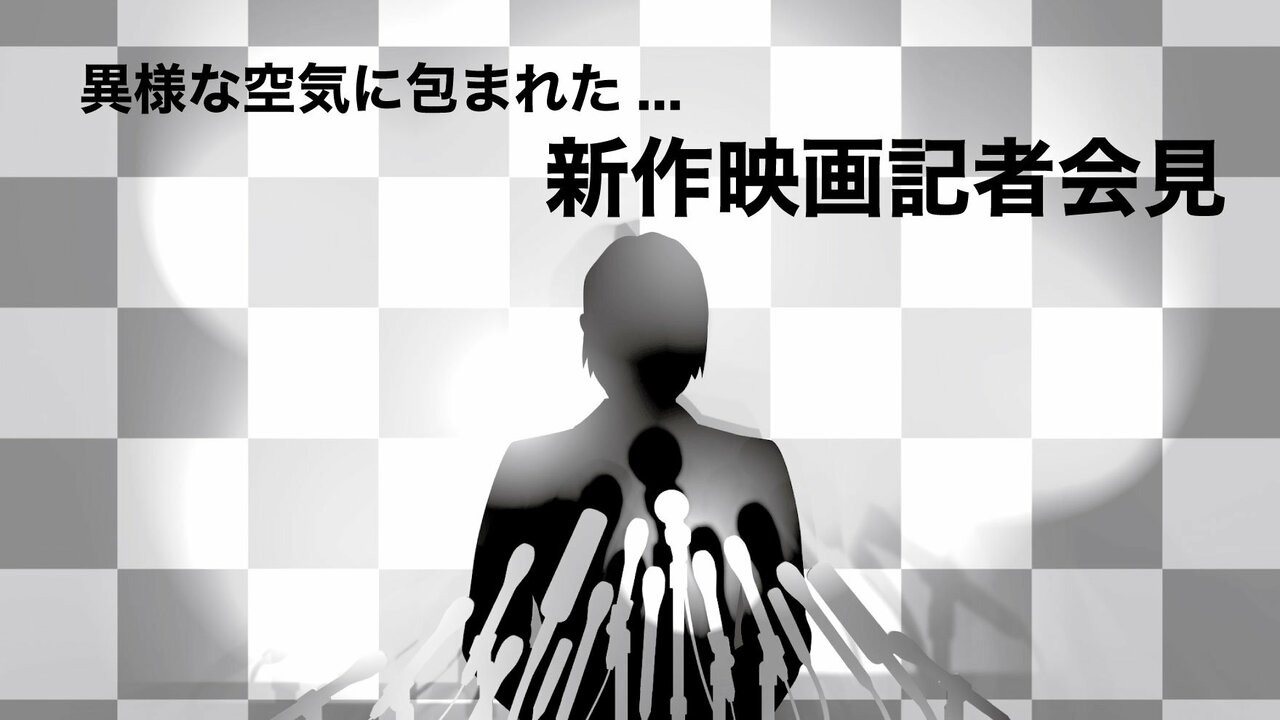「生憎ですが、撮影が始まりますのでインタビューはここまでということに。そうそう、明日なら撮影所長、監督、プロデューサーの取材は可能だと思いますのでお聞きになりたいことなら、この日にどうぞ」
男はそう告げると二人の前を遮るようにして撮影所の中へ入っていった。まるで大きな山が二人の前から突然姿を消し去ったような印象だった。笹野はしばし呆然としていたが、やがて傍らの内山に声をかけた。
「内山君、映画界に詳しい君だからこそ聞くが、あの男に見覚えがあるかね」
「いいえ、一向に。しかしあれ、ほんとに日本人なんですかね」
笹野も同感だった。今まで海外で名声を博した日本人を何人となく取材してきたが、短時間ながらこうも違和感を覚えさせた日本人は初めてだった。
「一体何者なんだ、あの婆須槃頭という男……」
「笹野さん。それにしてもこの撮影所の雰囲気は異常です。インド映画というものは元来恐ろしく分業体制が確立していて、一本の映画にそう関わりあってはいられないものなんです。それがどうです。この撮影所全体がたった一本の映画のために全力を集中して、ほかのセクションは全く鳴りを潜めている。
こんな撮影風景は、私は見分したことはありませんが、昭和三十九年の東宝砧撮影所での黒澤明監督の『赤ひげ』以来といっていいでしょう」
笹野は自分より十五歳近く年かさのこの男の、これまでの映画界で培ってきた経験をこれほど頼もしく思ったことはなかった。