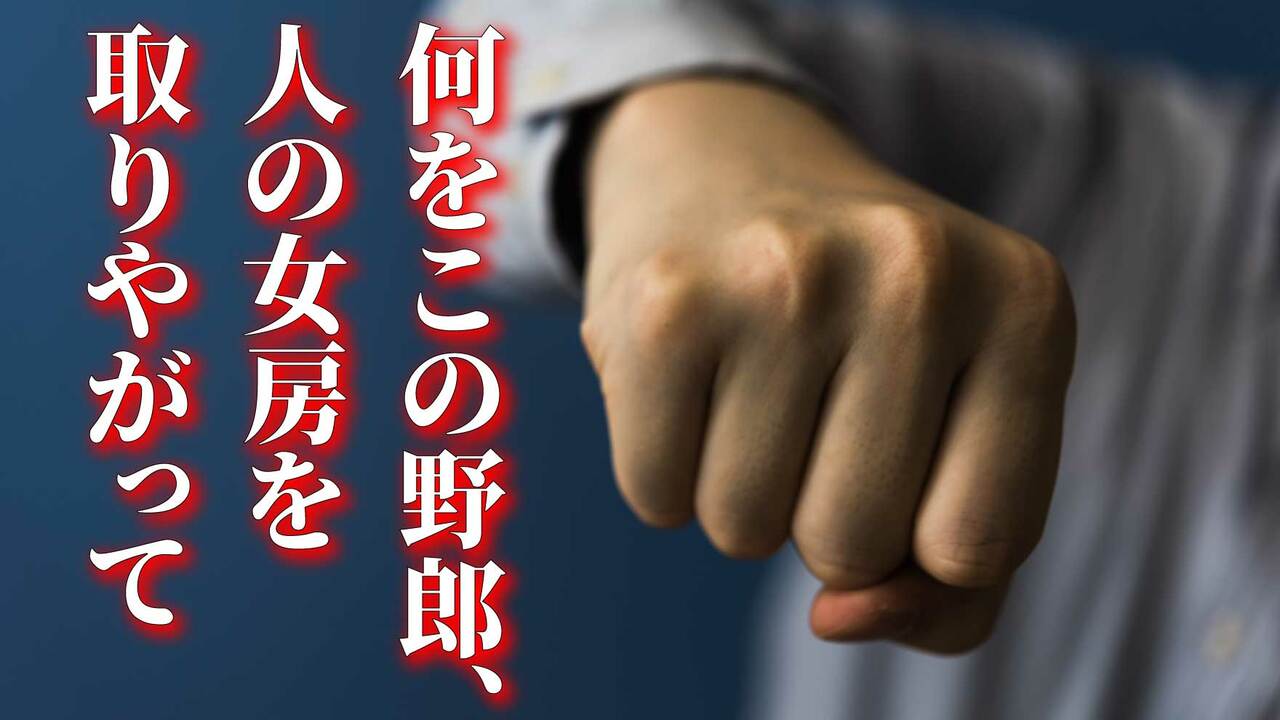事故に遭った妻は…
「君が、怒るのもわかるけど、僕は無理矢理智子を誘惑したわけじゃないんだから……」
どうやら井上は、完全に開き直ってきた。年齢を重ねた老獪さで、自分よりも一五、六歳年少の達郎に勝てるという確信が持てたのかもしれない。
「な、なんだって……」
「智子は、亭主の君なんかより、僕に惚れていたんだ。僕は、女房に先立たれて独身だったから、いずれは智子も君と離婚して、僕と再婚することになっていたんだ。それまでは、お互い絶対に人には秘密にしておこう、と言っていたのに……。どうして君にばれたんだろうか……」
智子が、離婚して、再婚する! いったいどういうことだ。
俺がいない間に、事はそこまで進んでいたのか。達郎は、二人の男女関係の進捗の早さに、驚愕せざるをえなかった。
達郎の表情を見た、井上は、
「智子は、君に抱かれたって、感じたことはないと言っていた。だが、僕に抱かれている時は、何もかもが真っ白になって、天に昇るくらい幸せだと言っていた」
井上が勝ち誇ったように言った。
達郎は、この井上の薄い頭髪が、智子の局部をまさぐっている場面を想像し、立腹の極限に達した。
「だいたい君、女房のからだも喜ばせられないで、文句を言うな!」
「何をこの野郎、人の女房を取りやがって……」
達郎は、堪忍袋の尾が切れた。
右手の拳が井上の頬に食い込んだ。勢いでかけ慣れていないサングラスがずれ落ちた。メリッという音がした。井上は勢い良く倒れこんだ。階段の登り口で止まるかのように見えたが、片足を踏み外し、そのまま、背中から一挙に転げ落ちた。最後に、ドボン、というような鈍い音がした。そして、頭を逆さにして、足を階段に上げたまま静止した。
井上は、全く動かなくなってしまった。普通なら、痛え、などと言って呻くはずであるが。
達郎は、恐る恐る階段を降りて近づいた。見ると、頭から小豆色をした血がべっとりと流れていた。血が薄い禿頭を染めていた。眼球は空を仰いでいる。呼吸はしていない。死、死んだのか……?
達郎は咄嗟にその場から逃げた。一目散で階段を降りた。四階、三階、急ぐ足がもつれるようになり、つんのめりそうになった。まだ二階か、こんなに階段が長いとは……