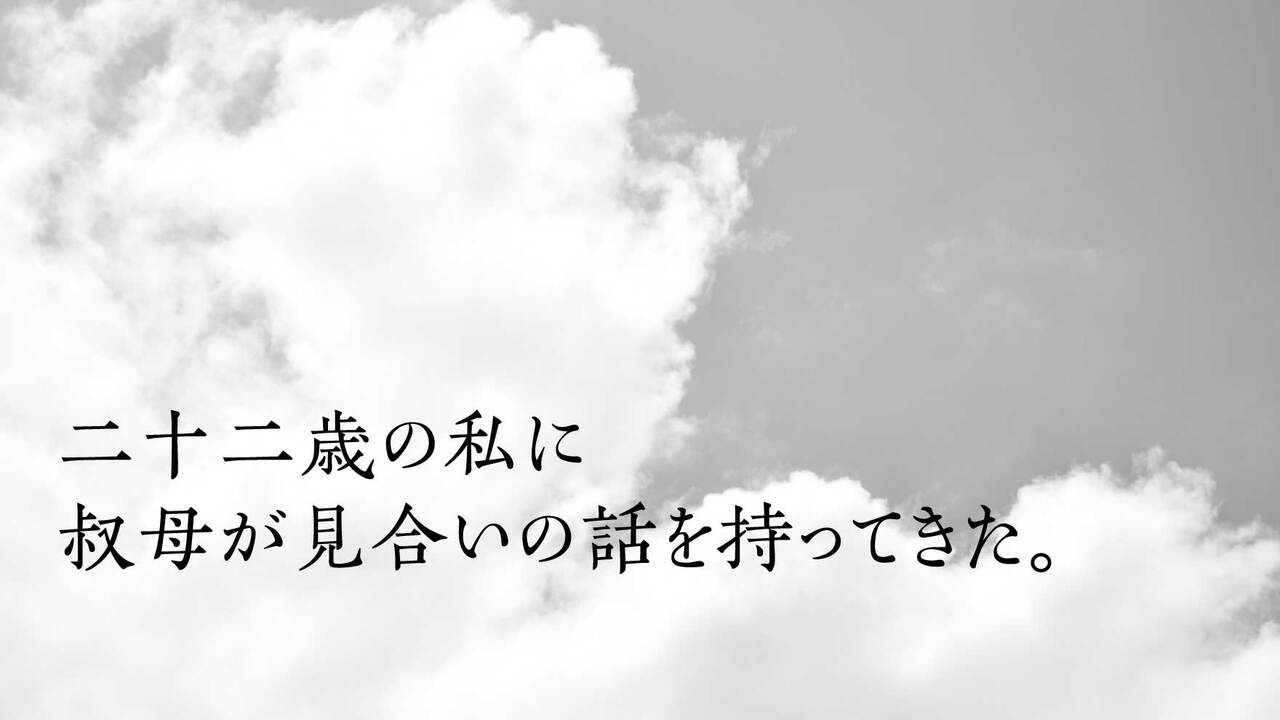四
兄は四歳になってすぐ、私が二歳の時に交通事故で亡くなった。あと十日ほどで幼稚園に通うことになっていて、園児服と帽子と黄色いカバンが、私が小学校に入っても居間の椅子に掛けてあった。
「葵ももうすぐ小学校へ上がるんやから、そろそろ片付けたらどうや」
どんなに父が言っても母は頑として聞かず、私は兄の遺品と向き合って過ごした。私が小学校に行くようになっても母の足は地面から浮いていて、ふわりふわりと宙を漂っているようだった。
時々両手を差しだして兄に語りかけている母を見るにつけ、母の中に私は存在していないのだと思ってきた。教師をしていた父は帰りも遅く、日曜以外は家に居なかった。
父の多忙は母の行状から目を背けていたからなんだと、中学生になって分かった。父も現実から目を背けていたのだと。近所に同じような年頃の子どもが多かったのが、救いだった。
小学校の頃は学校から帰るとランドセルを放り投げて近くの公園に行き、陽が暮れるまで遊び惚けていた。六時を報せる『夕焼け小焼け』のメロディが、お寺から聞こえてくる。
冬の日暮れは早く、辺りに薄っすらと闇が迫ってきても、足はなかなか家に向いてはくれなかった。一緒に遊んでいた友達は、そのメロディが聞こえ出すと弾かれたようにいなくなる。
どんなに帰りが遅くなっても父は知らないままで、祖母は、女の子が暗うなっても帰らへんと心配や、と顔を曇らせた。四歳のままの兄に幼児ことばで語りかけ、その時だけは優しげな正気の眼差しを向ける母の顔を見るのが耐えられず、帰り着いても玄関の戸をなかなか開けられなかった。
そんな母が三十七歳で急死した。もう兄を偲ぶ母の姿を見ないですむようになったのに、母の恨みが私の背中に張り付いているようで、ここは私にとって居心地のいい家ではなかった。父親には何の相談もせず、高校を出たら就職しようと決めていた。
「学校の推薦で、印刷会社を受けることにしてん」