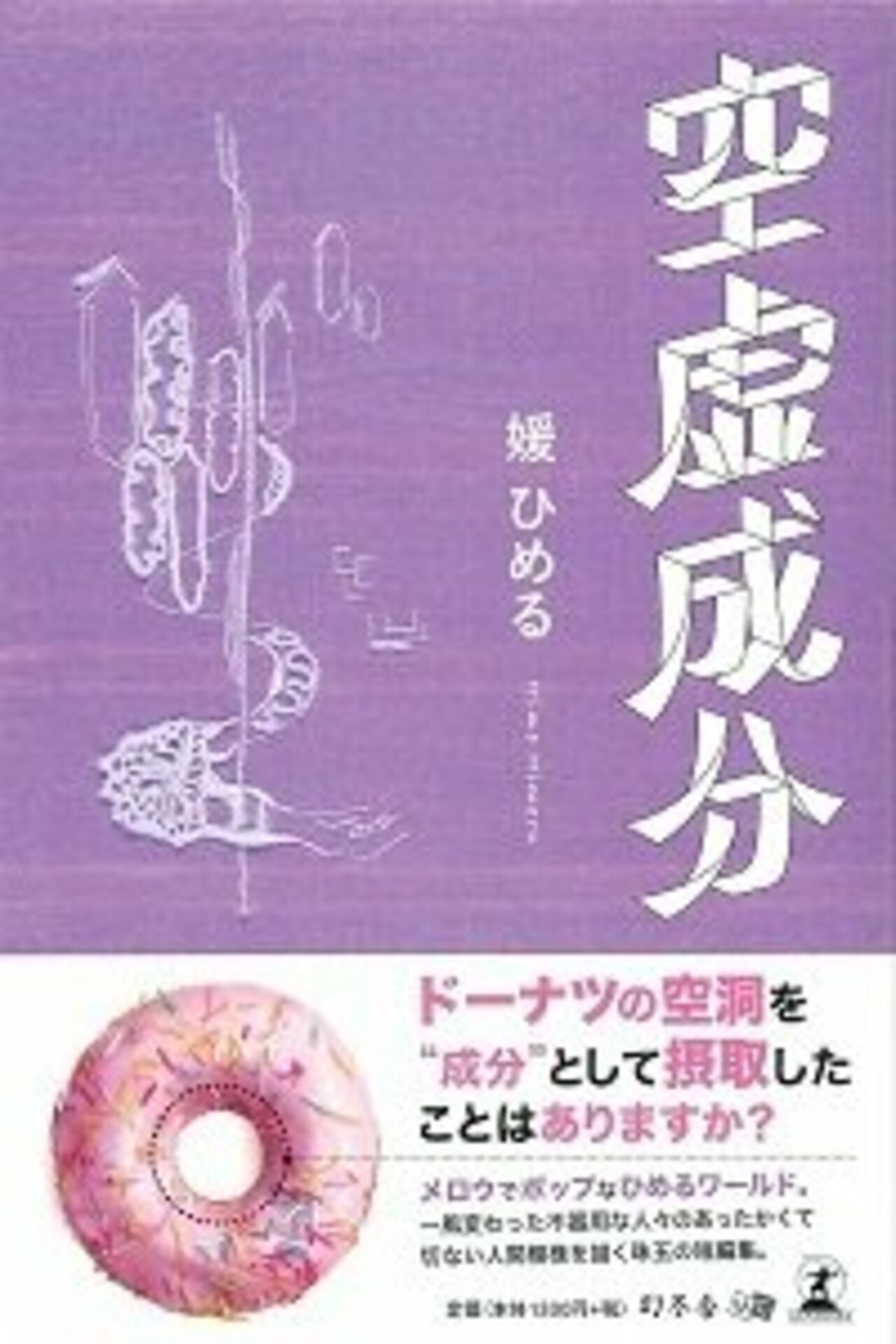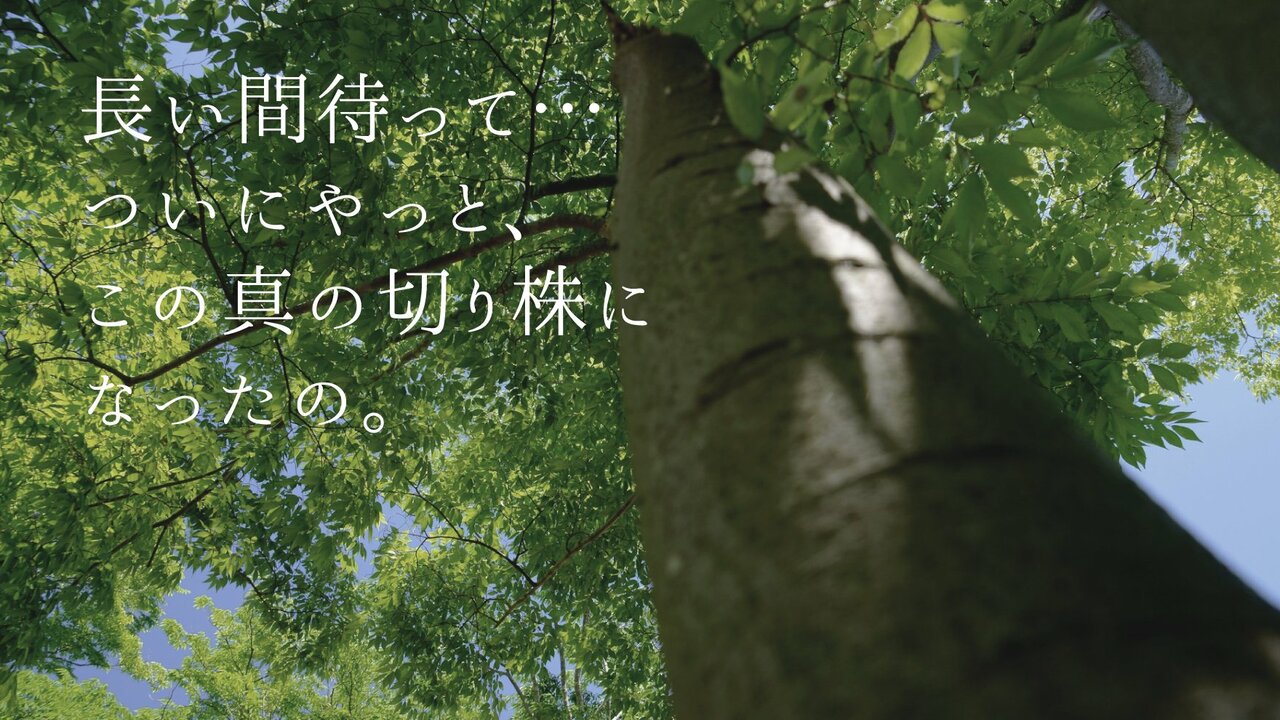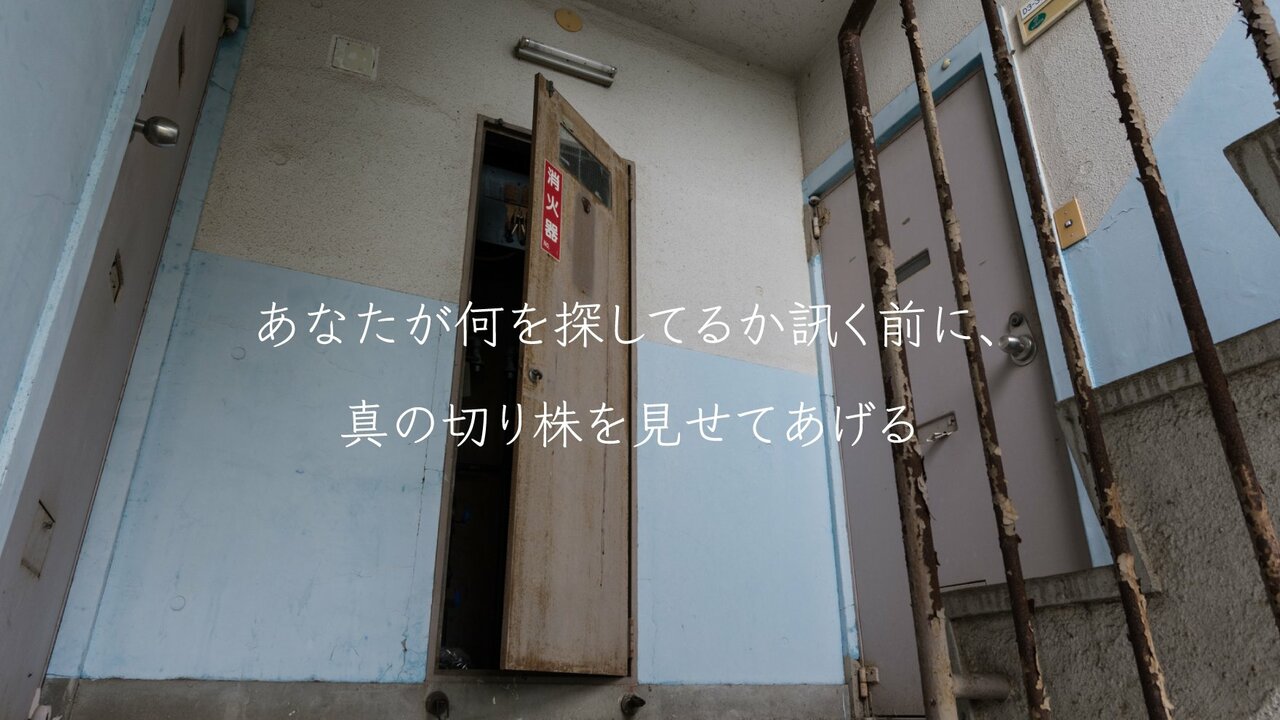「立派な太い幹をしてたわ。杉とかだと思うけど。木の種類は関係ないから」
「えーっと……」
私は頭の中で質問を整理した。
「その大木が切り倒されて──これに?」 「そうよ」
「もしかして、まだ木だった頃から、将来は真の切り株になると気付いてらっしゃったんですか?」
「もーちろんよ」
彼女は大げさに目を見開いた。
「でも、切り倒されるまでが長かったの。あたしも子供の世話とか、途中から旦那の看病とかいろいろあって、ちょっと忘れてた時期もあったくらい。でもある日見たら切り倒されてるじゃない。あのときは本当にびっくりしたわ」
「切り倒されることが始めから分かってたんですか?」
「ええもちろん。だって、材木屋が植えてる木だったから。当時あたし犬を飼ってたんだけど、その犬がね、材木屋が持ってる林に逃げ込んじゃったの。それで慌てて探しにいったとき、たまたまこの木を見つけたってわけ。周りは全部同じ木だったけど、あたしには、これだって一目で分かったわ」
「そういうものかもしれませんね」
私は考え考え言った。
「見つけた瞬間に、そういうのって分かるものなんでしょうね。見つけるときも、見つけようとしてるときじゃなくて、他のことをしてるときとか、ひょんなときなんですよね、きっと」
「まさにその通りよ」
あなた話分かるじゃない、というような目で、彼女は私を見た。
「でもね、切られた後がまた長かったの。切り株になりたてのときは、真の切り株としてはまだまだだった。そこであたしは待ったわ。我ながらよく待ったと思う。待って待って待って──ついにやっと、この真の切り株になったの」
可愛くてならない孫でも見ているように、顔がとろけている。
「これは、その切り株の一部ですか?」
いいえ。彼女は急に頬を引き締めると、きっぱりと首を振った。
「これで全部です」
じゃあ、と私は慎重に言葉を続ける。
「きっと物凄く乾燥したんでしょうね。だからこんなにちっちゃくなったんですね?」
これが元は大木だったとはどうしても思えないのだ。あら、と彼女が高い声をあげる。
「あなたにはこの素晴らしさが分からない?」 私は頬が引きつるのを感じた。必死で適当な言葉を探していると、腕にふわりと手を置かれた。
「いいのよ」
彼女は私から手を離すと、未熟者を諭すような優しい口調で言った。
「そういうものよね。自分以外の人には分からない。自分の中だけのことで、これは闘いなの」
「たたかい」
新しい考え方だった。なるほど、そうかもしれない、と私は妙に納得した。