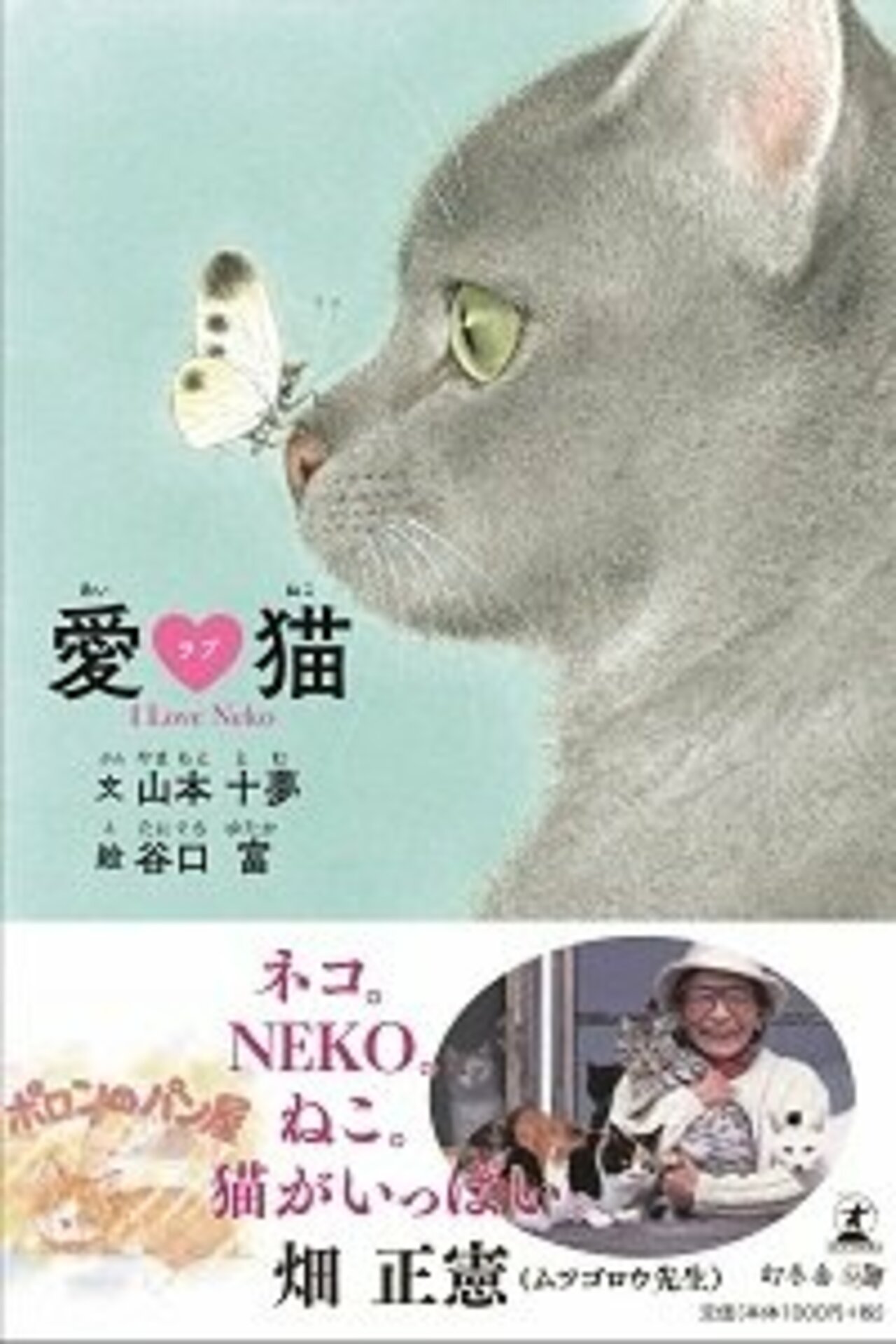「ゲンキは、無芸大食(とにかく食べること)がトレードマークなのに」
ぼくも気にはなっていた。ぼくにもよそよそしい態度をとって近づかなくなった。おかんが獣医さんのところへ連れていくと、診断の結果はストレス性の胃潰瘍だった。
それから半年くらいがすぎたころだ。あいかわらず店は大いそがしだけれど、おとんとおかんの顔がすぐれない。目もくぼんでいる。つかれはてて元気がなくなってしまったのだ。
「あなた、このまま続けていて本当にいいのかしら」
「何が?」
「お店は繁盛して売上はすごいの。でも何かが変」
お客が帰ったあとのしずまりかえった空間の中で、おとんも、おかんも考えこんでしまった。
「うーん、そうかもな。オレも店を出そうと思い立ったころのイメージと、だいぶちがう方向にいってる気がする」
「そうでしょう? 本当は、かわいそうな猫を助けることが私たちの夢だったわよね。猫カフェをはじめて、里親をさがして、殺処分ゼロをめざすはずだったわ」
「そうだ。ところが今オレたちは、猫の見世物ショーをやっているからなぁ」
「猫たちの引き取りを断ったり、里親募集をやめたり。それで、パフォーマンスだけやって、オハナやゲンキたちに、ずいぶん負担をかけてたのよね。金もうけ主義に走ってたのかもしれない」
「オレたちがやってきたことは、ひょっとして動物虐待なんじゃないか?」
これまで胸の奥にためていた、まよいの言葉が自然に出た。