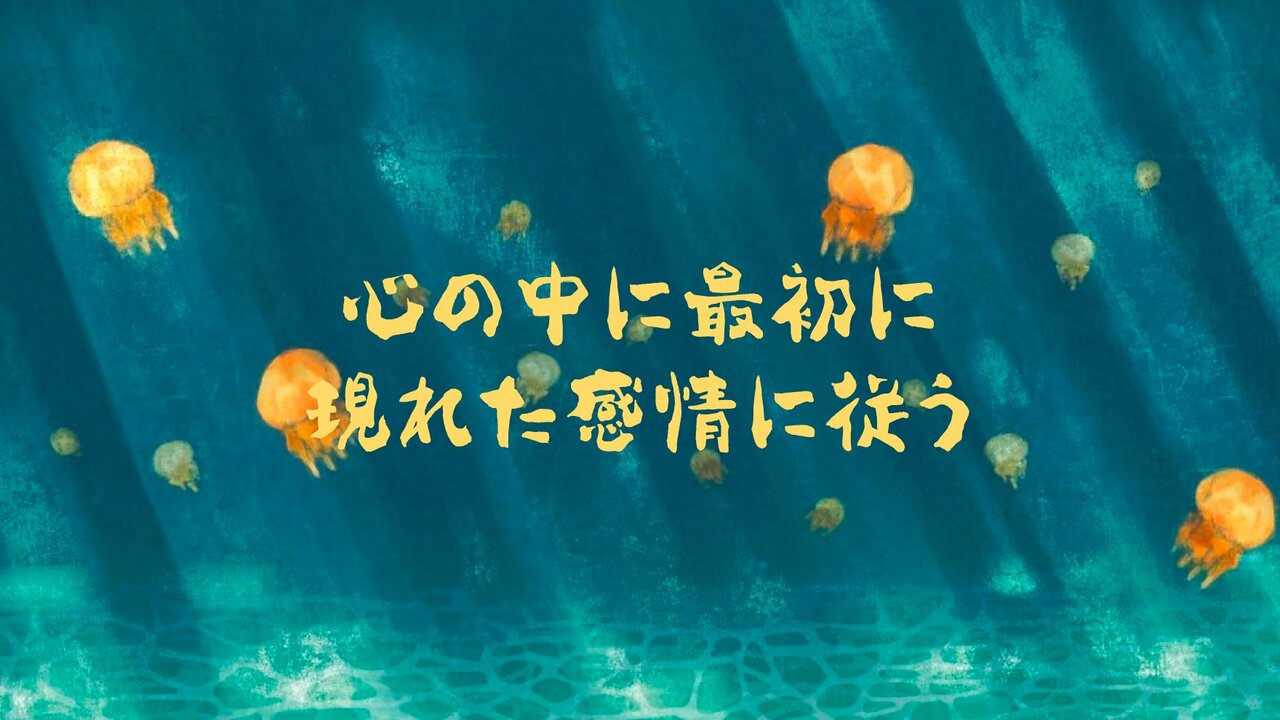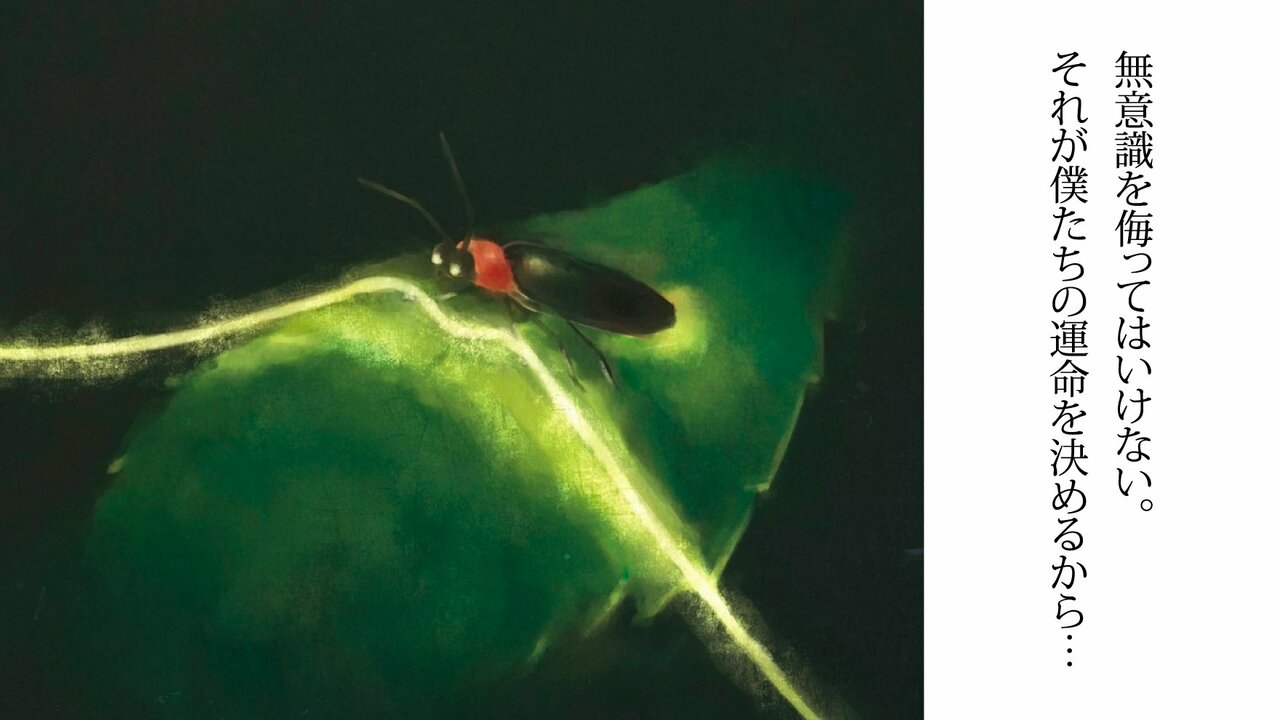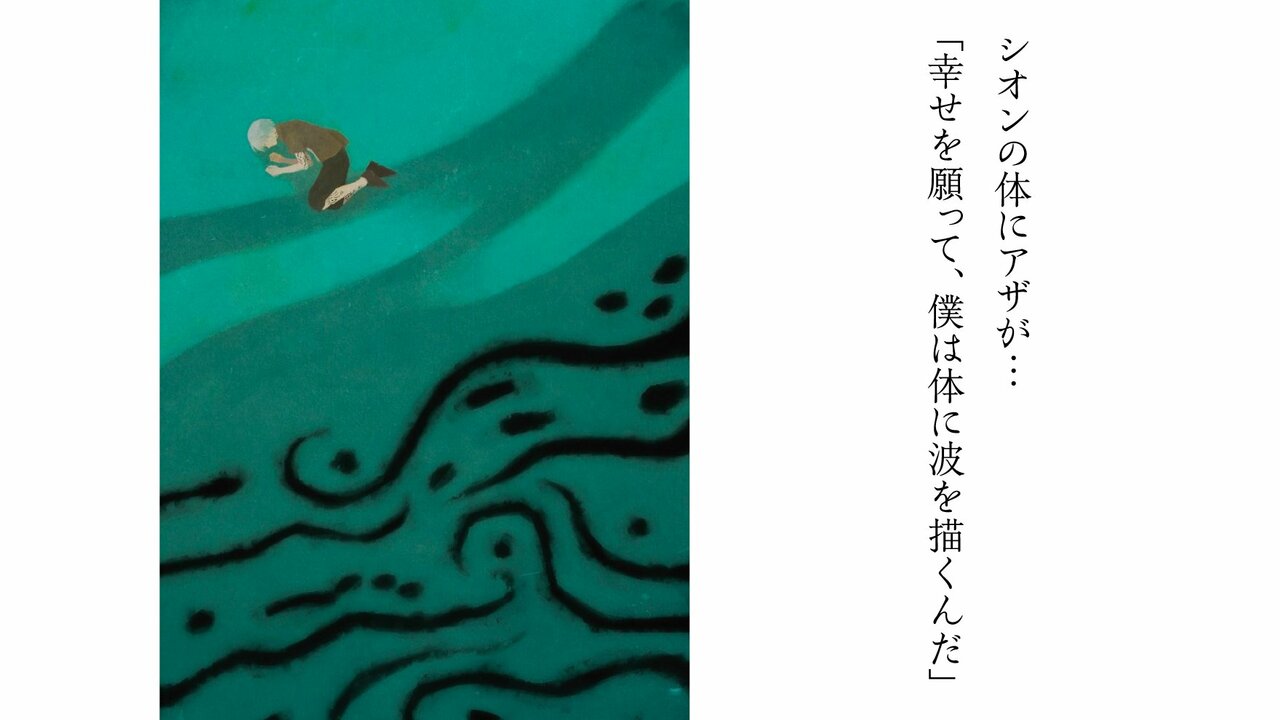シオンは素晴らしい聞き役だった。人一倍、心優しく、冷静で、よく気がつくが、数えきれない程の人の痛みを全部、一人で抱え込むシオンの孤独に、ローレンは気がついた。
「孤独の中でもがいているように見える……シオンを見ていると、そんな感じがする」
今、目の前に立っているシオンは、まるで遠くの世界の人のよう。
「ぼくももう行かなくちゃ。ぼくのはもう切れそうなんだ」
シオンはローレンの頭にそっと触れ、今にも切れそうな細い糸の先へと歩き始めた。
「シオン、どこへ行くの?」
ローレンはシオンの後を追いかけた。

あたりは森の中。息を切らしながらシオンを追いかけた。森の中は、少し肌寒くて、体がフワフワと浮いている感覚だ。
ふと見上げると、木々の隙間からピンク色の綺麗な空が見えた。
「わあ……ここは夢の中みたい」
そう呟き再び正面に目を向けると、ずいぶん先を歩いていたシオンの姿は消えていた。立ち止まるローレン。陽は落ちてあたりはまっくら。
真っ暗だ。何も見えない。先が見えないというのはなんて不安なんだ。私はどこに、どうして、どうやって――
「独りにしないで……」
温かい涙がローレンの冷えた頬を伝った。