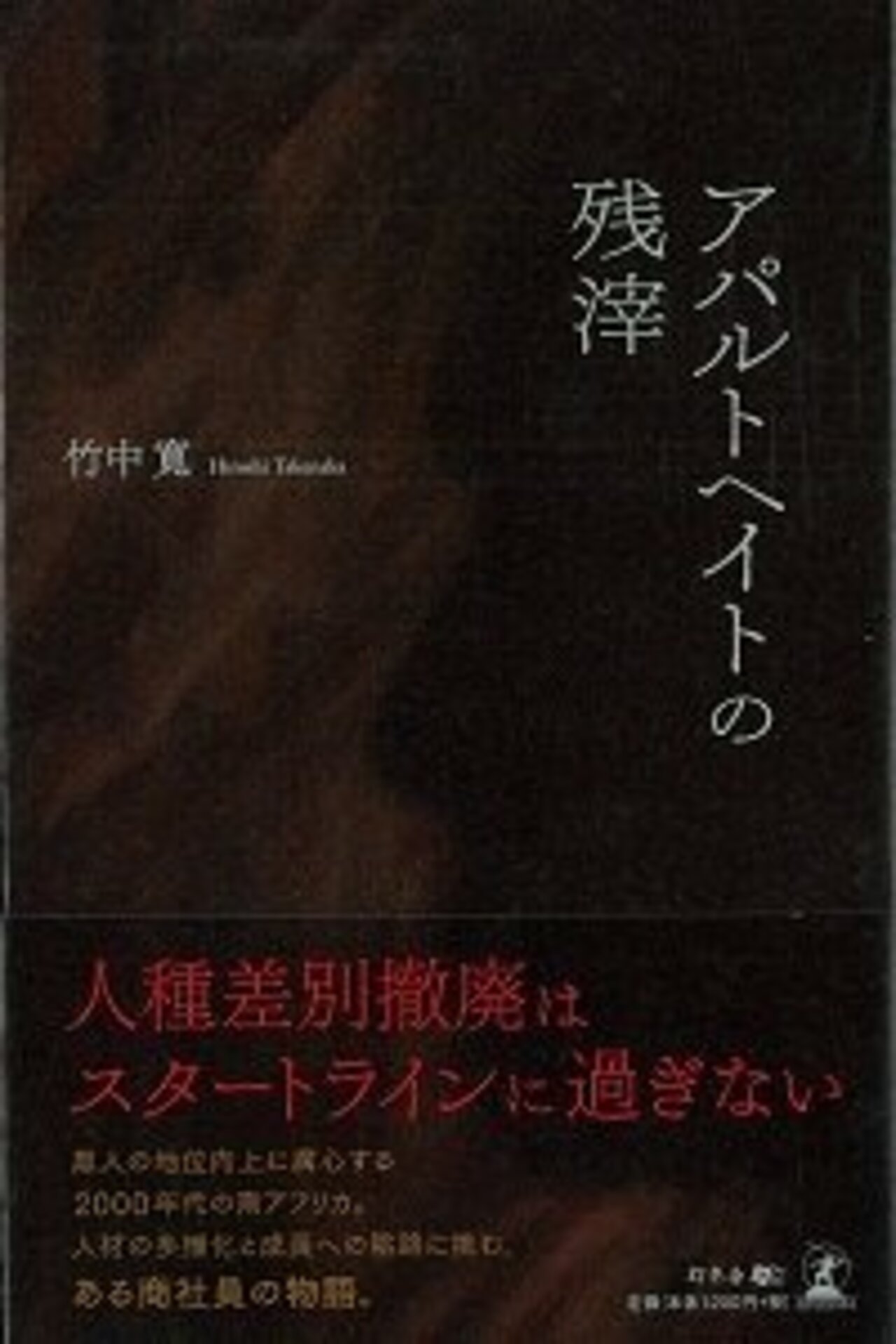「その三人とは?」
高倉が聞くと、斉藤は、
「はい、一人はプレトリアのリトレッド工場の作業員、三十五歳、二人目はダーバンのリトレッド工場の作業員、二十七歳です。どちらも黒人ですね。三人目は、このオフィス裏の倉庫にいます。名前はピート・ダン三十三歳です」
「それは倉庫のチーフが強盗に襲われた時に、状況を説明したあのカラードです。でも彼は……」
アンドルーが言い淀んだ。
それに高倉が違和感を覚えた時、秋山が質問した。
「考課テストとはどういう内容ですか?」
「商品知識、タイヤ技術の初級知識、タイヤ組み付け装着の実技、それに実務に関する小論文ですよ。ピート・ダンは実技を除いて、どの科目もトップです」
「やっぱりそうか……あの事件の状況説明が簡潔明解だった。倉庫ではタイヤの保管はしているが、組み付け装着はやっていないので実技が劣るのは仕方ないだろうな。他の二人の成績は?」
高倉が聞くと、
「二人共工場の作業者ということもあり、特に実技が抜群でした」
「よしわかった。斉藤さん、そのファイルをここへ置いといて下さい」
そう言ってこの日の打ち合わせを終え、四人は社長室を出てそれぞれ家路についた。
外はすっかり夜の帳につつまれていた。
秘書のアンネマリーが扉を叩いて入ってきた。
「遅くまでご苦労さまです。何か飲み物を用意しますか?」
と、窓のカーテンを閉めながら聞いた。
その気配りに感じ入りながら、彼女が背中で呼んでいるような錯覚を起こした。いやそう思いたかったのかも知れない。
白人女性はパンストが嫌いなのか、身につける習慣があまりないようだ。
アンネマリーの素足の下腿が透き通るように白く、それと窓の横に置いてあるパキラという観葉植物の濃い緑とのコントラストが鮮やかに目に入る。
胸の高まりを覚え彼女に近寄った。
そしてうしろからそっと抱いた。
彼女は抱かれたまましばらく動かないで、再び聞いた。
「あのう……コーヒーを持って参りますか?」
高倉はハッと我に返り、抱いた腕を無理にほどきながら言った。
「君こそ遅くまでご苦労さん。何もいらないよ」
「それでは私はお先に帰らせていただきます」
と、彼女は何ごともなかったかのように社長室を去った。
ほんとは帰って欲しくないんだが、そう思いながら、彼はそのうしろ姿を目で追っていた。
オフィスはシンと静まりかえっている。
冷静さを取り戻した彼は、あ、いかん、いかん、社長と秘書の恋愛は格好のスキャンダルのネタになる。マキシマ社をせっかくここまで立て直したのに、社長が不祥事を起こしたら元の木阿弥だぞ、と反省した。