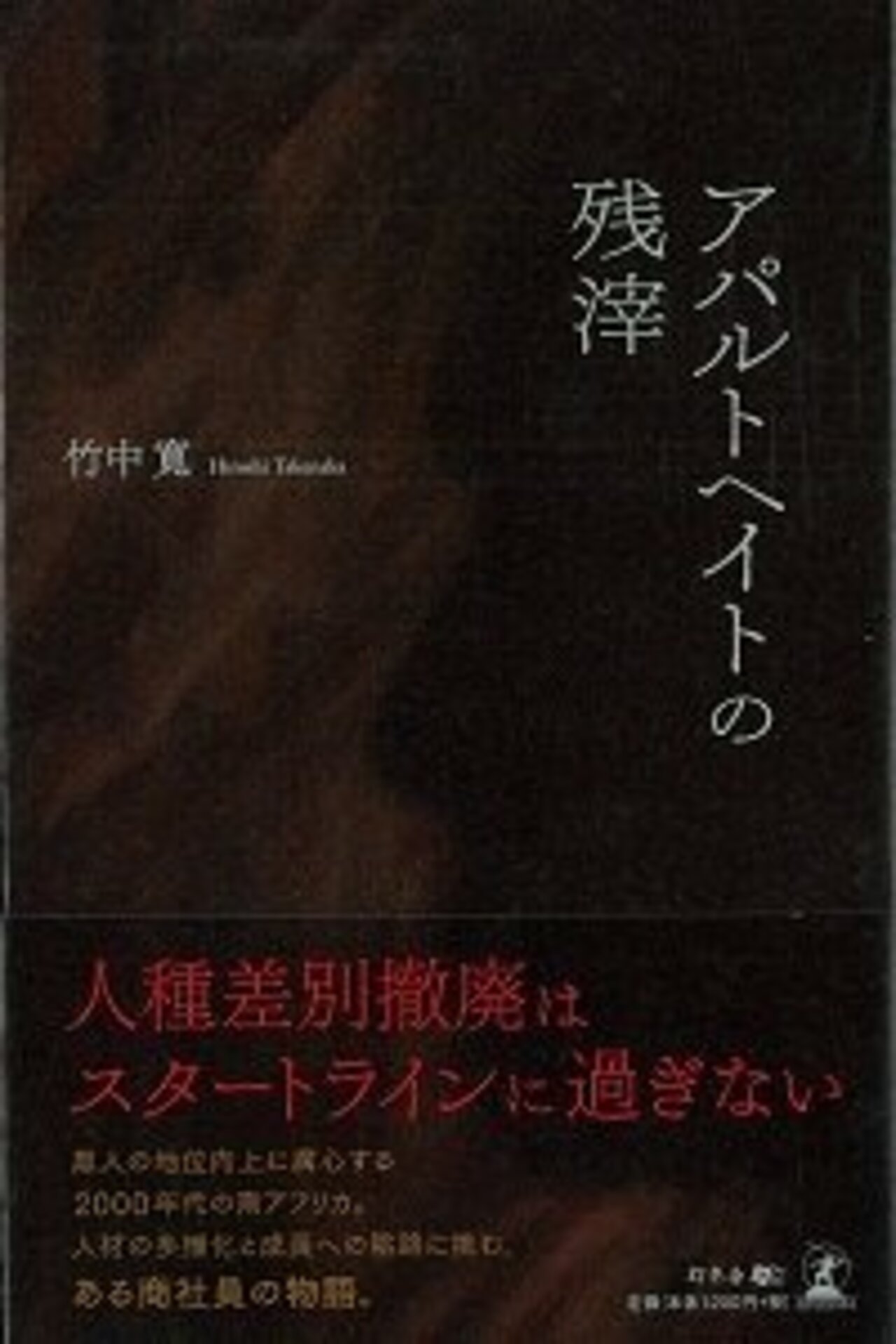ロッド・モーローの解任から三週間ほど経った日の朝六時頃、高倉はいつもの通りトースト、ソーセージ、目玉焼き、レタスとポタージュの朝食を取っていた。
そのとき高倉の携帯が鳴った。
モザンビークのマドールタイヤ担当マネージャーのシェーン・ネッスルからであった。
「ジョージ、大変です。ブリット銀行がマドールタイヤの救済を取りやめました」
「やっぱり、そうか、これでマドールタイヤは完全に倒産するな……」
少し沈黙した後、彼は指示した。
「シェーン、先日言った通り、すぐにトラックをマドールタイヤ工場に回して、製品ストックを全部引き取って南アフリカへ持って来い。全部だ。まだ可能か?」
「ロックアウトされる可能性があるが、まだ大丈夫そうです」
管財人が入ってロックアウトされてしまったら、手が出せない。急がねばならない。
「そうか、急いでやってくれ。但し、強引にやって警察沙汰になるようなことは絶対に避けてくれ」
「大丈夫です。こうなった時は、売掛金の代りにタイヤを引き取ることでマドールタイヤの了解をもらっています」
「頼むぞ、シェーン」
この時、シェーンは乗用車用タイヤを中心に合計一万三千本のマドール製品を入手した。もちろん、原材料代金の代りとして。
これを売りさばいて五百万ランドの損失を少しでも補填しようと試みた。結局、百万ランドの稼ぎに過ぎなかったが、少しは損失を相殺することができた。
マドールタイヤ倒産から三カ月後、高倉はモザンビークに出張した際に、倒産したマドールタイヤ工場に寄ってみた。
そこには警備員二人以外の人影は全くなく静まり返っていた。工場の中には入れず、まわりを一周しただけだが、雑草がさらに伸びていた。
『国破れ山河あり、城春にして草木深し』という杜甫の詩が彼の口から自然に吐き出された。
会社が倒産するというのはあわれなものだ。自分たちマキシマ社がこうならないようにしなくてはならない、と、彼は決意を新たにした。