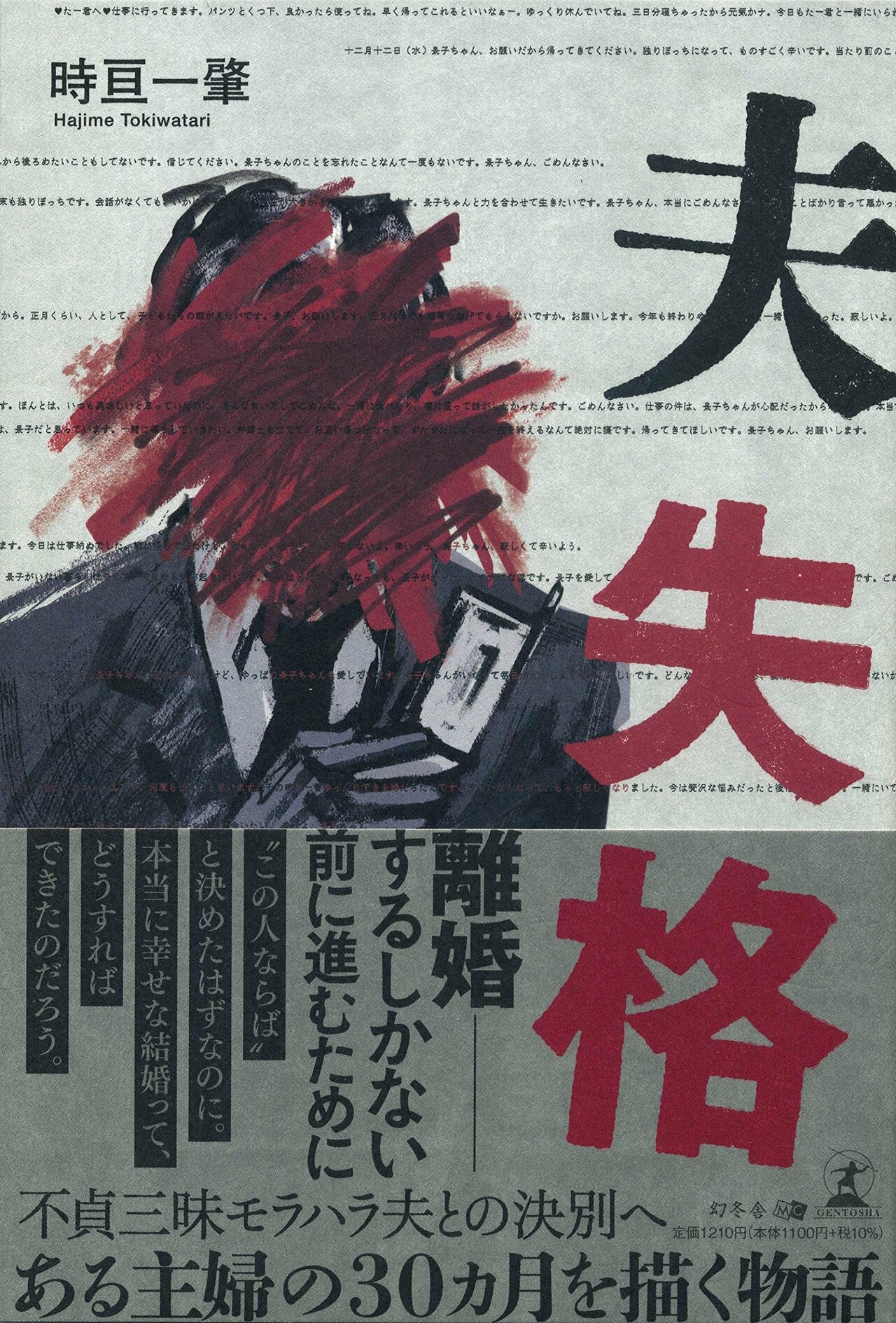「なあ、お義母さん、山田の家は嫌や思う前にうちに来てたら、お義姉さんのところに行こうって思った?」
「うん、そうやなぁ。でも今は、景子ちゃんが嫌やなかったら、最期まで看てほしいと思ってる。もし、あんたが嫌やったら施設に入れてほしい。山田にはやらんといて」
孝雄に対する気持ちは、もうとっくに冷めていた。それでも、こうして、この家で暮らしながら、彼の母親を介護し続けてこられたのは、自分は孝雄の妻ではなく、家政婦なのだと思うようにしたからだ。そう思えば、辛くても仕事だと割り切ってすることができる。
でも、その家政婦としてやっていることさえ、今回、浮気のことがわかって、どこまで人を馬鹿にすれば気が済むのだろうとばかばかしく思えてきて、それで、晴香さんに代わってもらいたいと孝雄には言ったのだったが……。
夫を見れば、あれやこれやと考えてしまうことも、ふいと夫が出かけてしまうと家の中は平和そのもので、「乗りかかった舟や。私でよければ最期まで看てあげる」と、義母に約束してしまっていた。
「ありがとう。景子ちゃんのことは、いつもちゃんと見てるで……」
義母は体調がボロボロでも、頭はしっかりした人だったので、二人きりでいる時には、お互いの愚痴(ぐち)や楽しかったことなどを話すようになっていた。また、そうやって義母に話すことにより、ほかに漏れることもなく、気持ちが楽になるのも確かだった。
しんじれる
そのきもちをたいせつに
きょうこのとき
みんながいるから
きっとしあわせ
ありがとう
おもえるきもち
たいせつに
ありがとう
かんしゃのきもち
わすれない
*