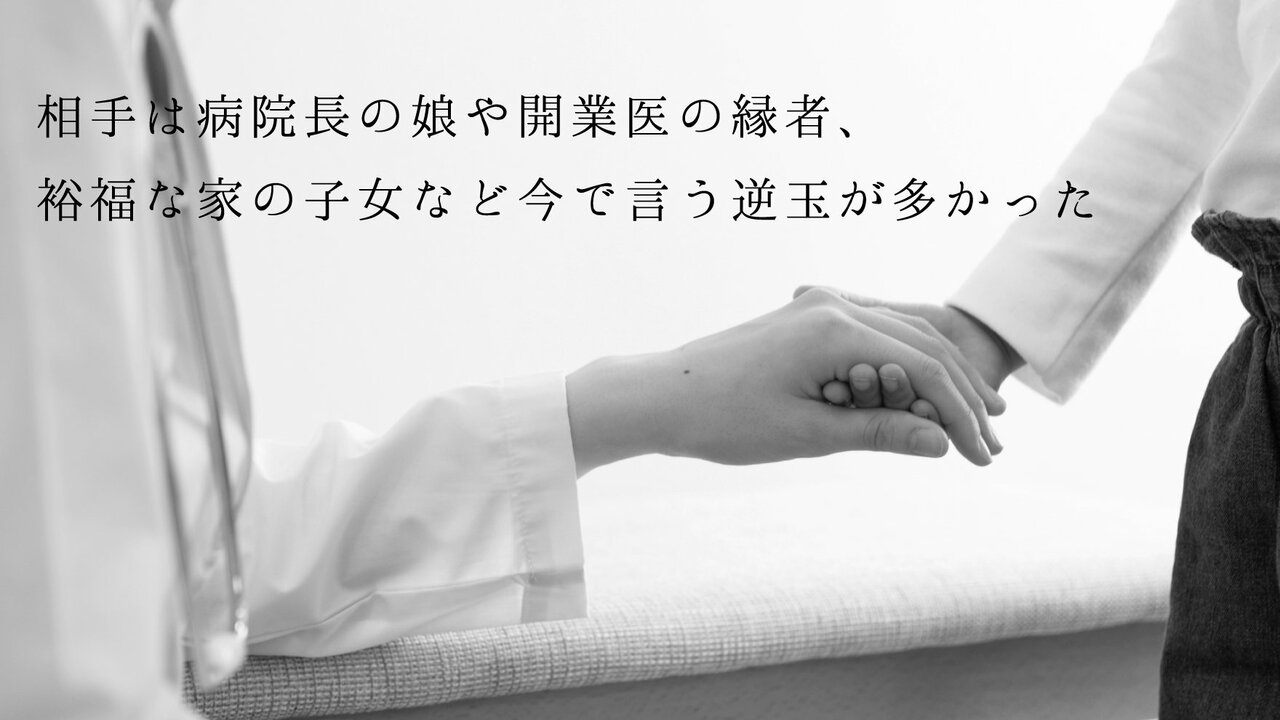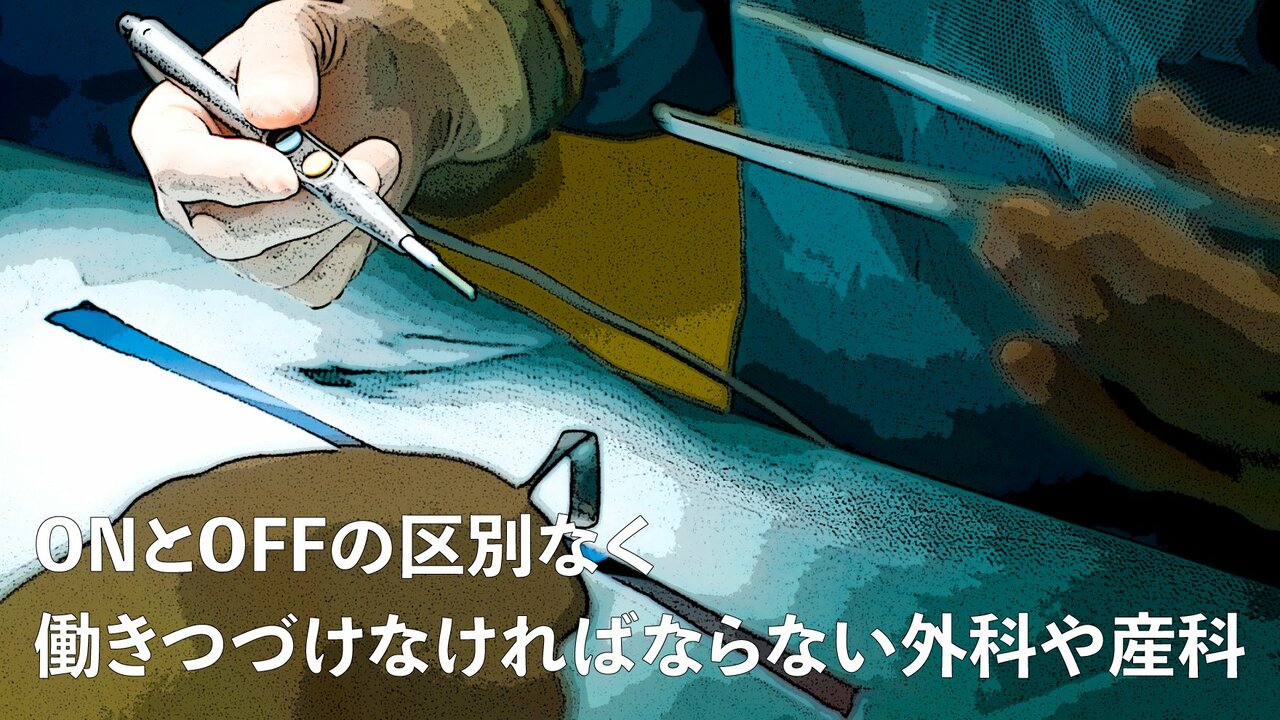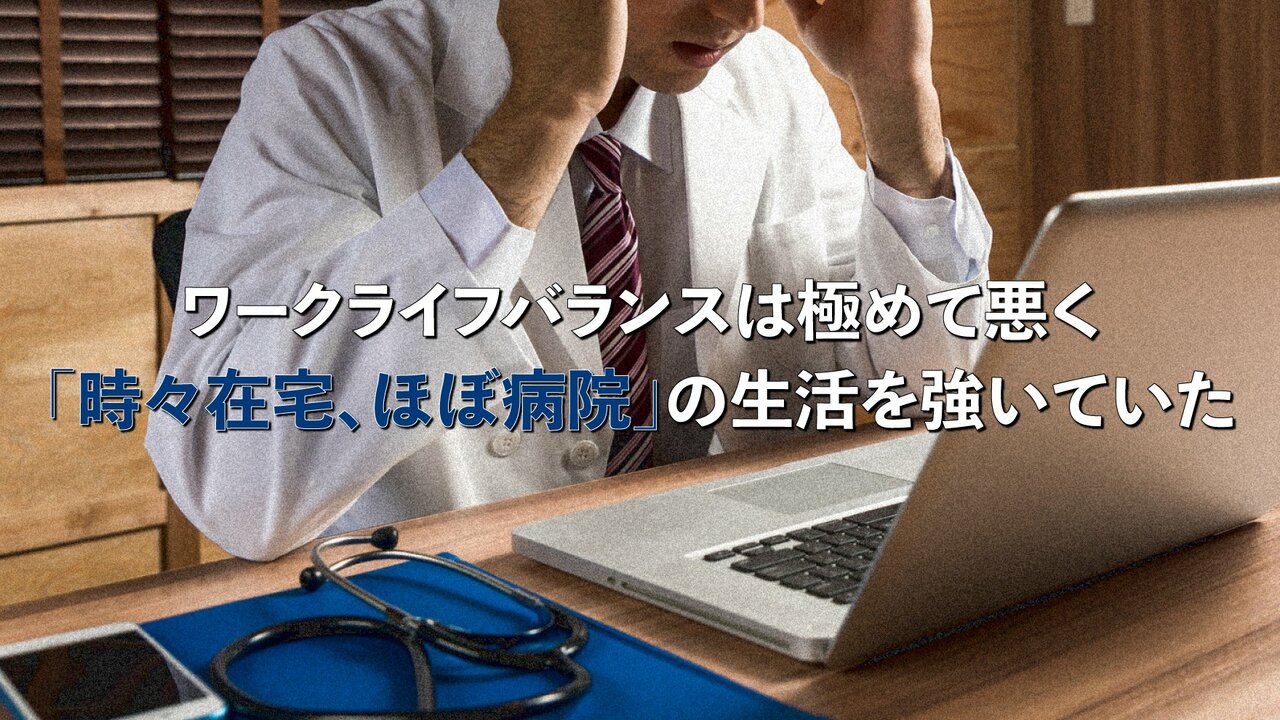第1章 令和の今、行政改革最高のチャンス
勤務医の働き方改革
私が外科医になった昭和43年頃は医学部のインターン闘争に端を発した大学紛争の真っ盛りであった。先日も大学病院に大勢の無給医がいるとマスコミが報じていたが、当時給料を貰えるのはほんの一握りの助手(現、助教)や講師、助教授(現、准教授)、教授と十数名で倍以上の者が無給。これが当たり前であった。
医局講座制という一種の徒弟制で丁稚奉公、修業の時代である。話は逸れるが京都大学医学部や附属病院は東京大学や大阪大学に比べ定員がかなり少ない。これは終戦直後の文部省の調査に対し、他の大学は出征したり疎開していた人数も現人数に加えたのに我が京都大学は馬鹿正直にその時にいた医師の人数のみを回答し、それが固定されているとのことである。
吉本興業の事件では興行界や芸人社会の後進性が暴露されたが、医学界の医師も昔は芸者や役者と並んで“3者”と呼ばれる少し下等な人気商売で、職能の腕を売って媚びるという風に理解されていた。他の2者は今ではタレントという片仮名でレベルアップしているようだが……。
芸人の世界は落語界のように付き人から前座、二つ目、真打と段階がある。それと同様に医師にも長い下積み生活の時代があったのである。
結婚などはなかなか出来ず、無給時代に結婚する相手は病院長の娘や開業医の縁者、裕福な家の子女など今で言う逆玉が多かった。職場の看護師や薬剤師と結婚してもダブルポケットの二輪車ではなく一輪車のような家計であった。
私の先輩は普通の家庭の人を嫁にして子供も生まれたが、粉ミルク代は附属病院前の薬局で盆と暮れの節季払い。お盆休みや年末年始の高い当直料で稼ぎギリギリで払っていた。
その頃は高価な医学書や学会に出席する費用の調達にも苦労していた。無給医は公務員ではないので交通費や宿泊費等は何も出ない。発表者のみに医局や研究室でプールしている積立金、稀に恵まれた者は文部省(今の文部科学省)からの科学研究費が支給されている上司(独語でオーベン)から頂けるくらいであった。