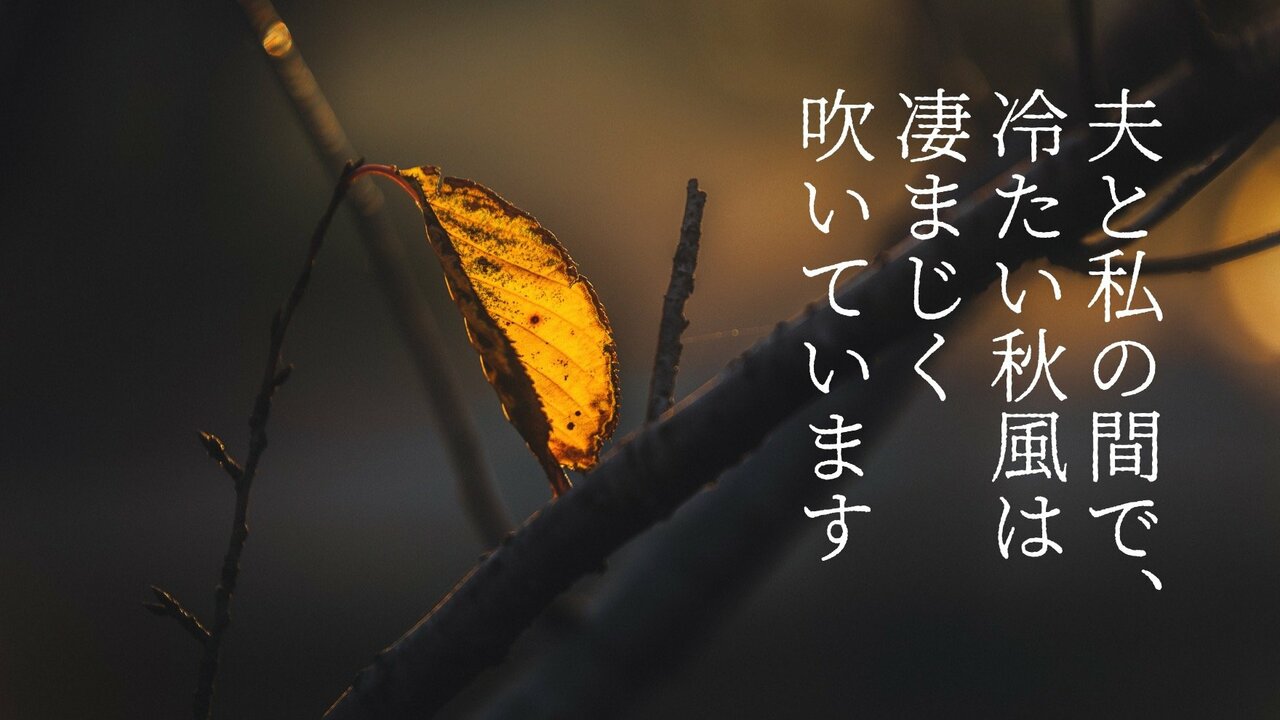5 桜花
弥生の空に春の彩を添える桜花。
河津桜の開花が告げられると、拙宅の庭の「枝垂桜」や「御衣黄(ぎょいこう)」の咲く日も近い。日本列島、南から北へと桜前線は日ごとに移動してゆく。待ち遠しいことこの上ない。
桜の種類は二〇~三〇種あるという。東京では紅が淡く、白い五弁の「染井吉野」が有名だが、江戸の「染井村(現在の豊島区駒込)」の造園師や植木職人によって育成されたことからこの名がついたのだそうだ。あたりを淡い桃色に染める満開の染井吉野は、目にも心にも優しく映る。
桜といえば、この季節の真鯛は「桜鯛」。まだ幼い鮎は「桜魚」。相模湾や駿河湾で獲れる透けた小さな海老は「桜海老」。いずれも美味なるものだ。
そして「お花見」といえば「酒宴」。桜は人びとに喜びと希望を与えてくれる。桜に精があるならば、人に対して功徳と施しをしているに違いない。
桜は奈良時代から植えられていた。
平安時代、爛熟した公家文化が生まれると、桜の花に心を寄せ、「和歌」を詠み、「詩」を作り、自然と同化し一時の宴を楽しんだ。その末期、武家の平氏一門は都で隆盛を極めることになる。
能に『熊野(ゆや)』という作品がある。熊野は時の権力者、内大臣「平宗盛」の愛人、その熊野の許に、東国の母から老境の寂しさをしたためた文が届く。熊野は宗盛にお暇を願うが、宗盛は熊野を元気づけようと牛車を出し、花見に連れ出す。華やかに人の行きかう四条から五条へ、そして春爛漫の清水寺に着く。
仏に母の快癒を祈念する折から酒宴となり、舞を舞うよう命ぜられる。涙をたたえて酒宴を盛り上げ、舞う熊野の姿―散る花弁を舞扇で受け、扇から桜の花弁が、はらはらと濡れ落ちる。その時、一首が生まれる。
「いかにせん都の春も惜しけれど馴れし東の花や散るらん」
宗盛に差し出すと、「急いで故郷へ……」と言葉が返る。熊野は都の春を惜しみつつ、老母の許へ帰って行く。
散る花と、「人の生と死」を重ね合わせた心の描写。滅亡に向かう平氏の運命。「散る花の美学」。日本人が誰しも心に内在している感性なのだろう。