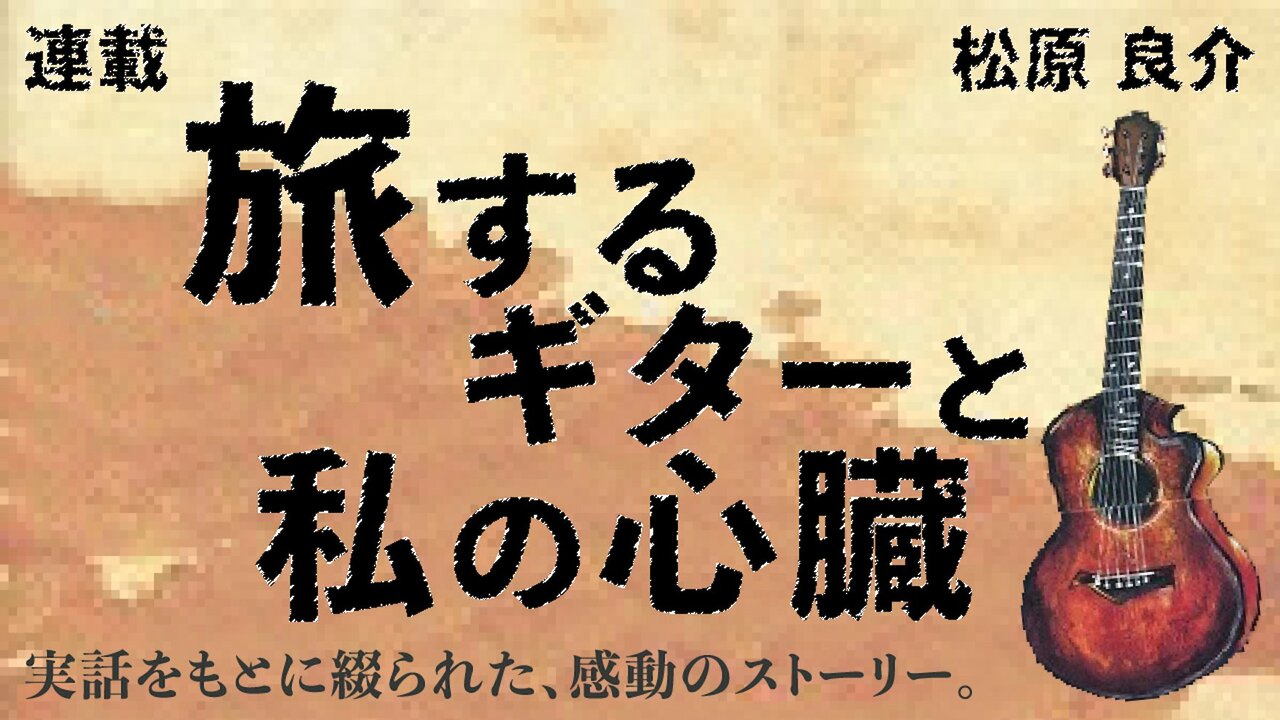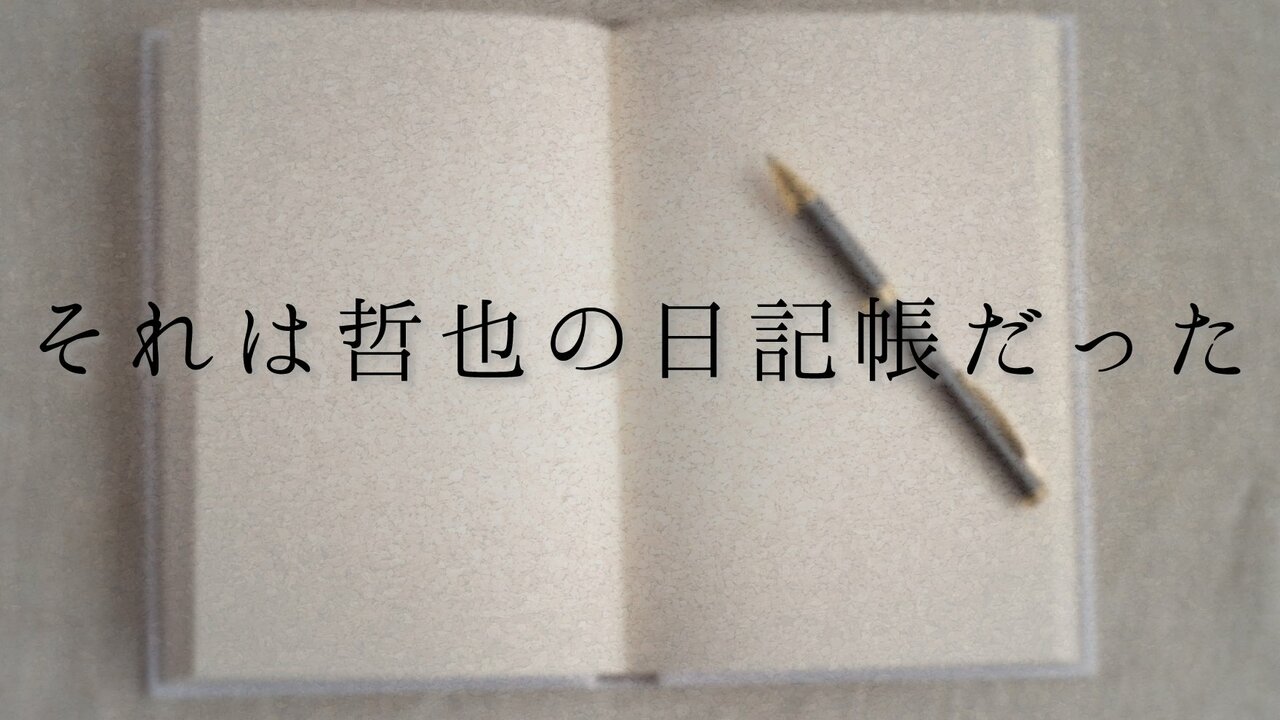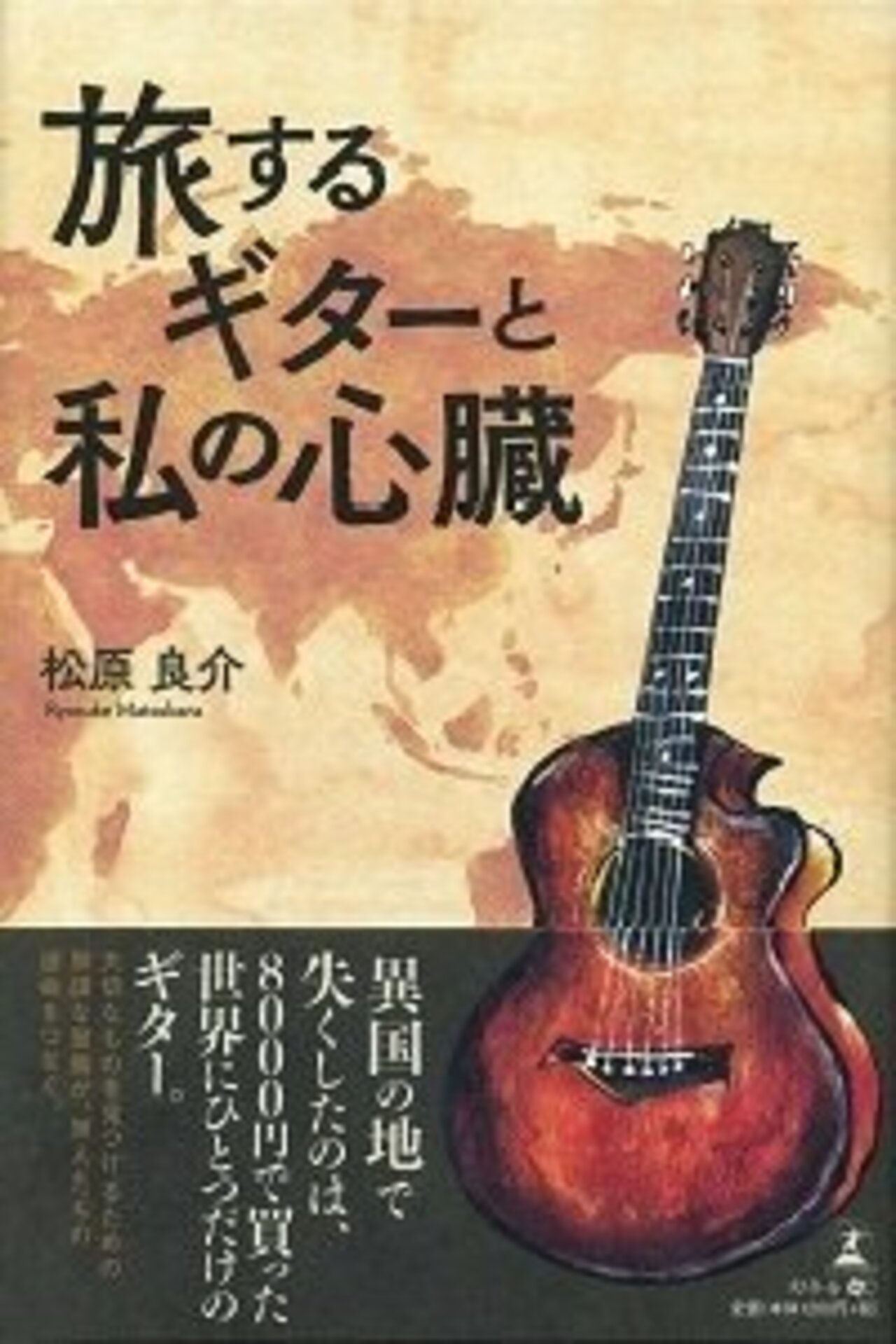彼は虚ろな目で天井を見つめていた。
周りには医療ドラマで見るような機材が並んでいる。
こっちに気がついた哲也は、一瞬驚いたような顔をしたように見えたが、その表情に意思があるとは思えなかった。管の刺さったやせ細った腕が、すべてを物語っているようだった。
私は現実を直視できなかった。
の哲也に少し声をかけたところで、哲也の母が病室に入ってきた。私は何と声をかければよいかわからずその場に立ち尽くすだけの自分が悔しかった。
痛々しく変わり果てた哲也の様子を見た私は、病室を出た後もしばらく言葉を失っていた。
「祐介君、病院まで歩いてきたの? よかったら送っていこうか?」
目を赤くさせた私を気遣うように哲也の母は声をかけてくれた。
「ウチで少しお茶でも飲んでいきなさいよ、さっきケーキをいただいたんだけど食べきれなくって」
そう言うと去年購入したという軽自動車に「いいから、早く乗って」と、少し強引に私を乗せた。哲也の母が運転する車に乗るのは初めてだった。
病院から哲也の実家までは車で5分ほどの道のりだったが、気持ちの整理ができないせいでしばらく沈黙が続いた。信号で停止した車中の空気が重たく、待っている時間が長く感じた。
「祐介君。私、あなたには本当に感謝してるの」
赤信号で停車した車内で哲也の母は言った。
「あの子、小学校の頃いろいろあってね……。中学校に上がるまでほとんど学校に行ってなかったの」
初めて聞いた話に私が目を丸くさせていると、
「驚いたでしょ? 本当に大変だったんだから、学校に行ってもらうの」
と哲也の母はハンドルを握りながら、なかなか変わらない信号機を見つめていた。
「家でもほとんど話もしないし、何考えているかわからない子でね。どうしていいかわからなくて、主人ともそのことでよく喧嘩したわ」
「中学校に行っても、はじめはあんまり気の乗らない感じだったんだけど、ある日あの子がリビングでCDをかけて音楽を聴いていたの。あの子、自分の部屋にプレーヤーがないから」
「そうしたらね。『ずいぶん古いの聞いているな』って、主人が」
「それで『父さんこれ知っているの?』ってなってね。それから二人とも、よく音楽の話をするようになったわ、二人で一緒にギターを弾いていたこともあったっけ……」
昔を振り返った哲也の母は嬉しそうに笑っていた。
「一緒にコンサートに行ったり、楽器を見に行ったりして……。でも、一番嬉しかったのは、楽しそうに学校に行くようになったこと。それを見送るのがおばさん嬉しかったわ」
話の終わりに「ありがとう」と言われたとき、今まで必死にこらえていたものが一気に私の目からこぼれた。
車の窓の外に流れる景色はところどころ変わっていた。
同級生の父親が経営していた八百屋はコンビニエンスストアに変わり、駅前のパン屋とクリーニング店のあった場所は、ビジネスホテルになっていた。でも、当時ギターを担いで通っていたスタジオは変わらず残っていた。
「そうそう、祐介君ちょっと見せたいものがあるんだけどいい?」
自宅に着いた哲也の母が、車のドアを閉めながら言った。
案内されたのは哲也の部屋だった。
ここに入るのは何年ぶりだろうか。2階に上がる階段がきしむ音も変わらず懐かしかった。ベッドも本棚も当時の配置のまま置かれていた。
生活感はないものの、そこに並んだコミックも、少し埃をかぶったCDも、昔弾いていたエレキギターも、数年ぶりに帰ってきた自分の部屋のように私を懐かしい気分にさせた。壁に貼り付けてある数枚の写真も昔のままで、その写真の右下に1995年と記載があった。
懐かしい気分で部屋のなかを見渡していると、窓際に見覚えのあるバックパックが置いてあった。空港で哲也を見送ったときに彼が背負っていたものだった。
「そう、実はそれなんだけどね。片付けたいんだけど、なんだかどう扱っていいのかわからなくってね……。なかから変な虫とか出てきたら嫌だし……」
そう言って哲也の母は、両腕をさするようなしぐさをしながら身体を震わせた。
「へー、……。おばさん、これ開けてみていい?」
「うん、そうしてくれるかしら。私は下からごみ袋持ってくるわね」
「えッ? ごみ袋?」
そう言うとパタパタとスリッパの音を鳴らせて階段を下りていった。
(ごみ袋って……捨てる気かよ……)
バッグを両手で持ち上げると、私はずっしりとしたその重量に驚いた。
「マジかよこれ。何入ってんだよ」
シンプルなつくりのバックパックは、上部についている入り口からしかアクセスできないタイプで、それ以外にチャックなどはなく、まるで取っ手のついた大きな土嚢袋のようだった。プラスチック製のジョイントを二つ外すとバックが開いた。
なかにアクセスするためには、さらになかにあるもう一つの口を開けなくてはならないのだが、硬く縛られた紐によってその口は強固に守られていた。
他人のバッグに手を入れる罪悪感と好奇心に似た気持ちが、私のバックの紐を解く手を迷わせた。どうにか開けたバックのなかからは、カメラや衣類、寝袋やヘッドライトなどが出てきた。それらは特に汚れてもおらず、異臭にまみれた得体のしれないものが出てくることを想像していた私は、少し肩透かしを食らった。
「へぇ……これは何に使うんだろ?」
私はS字状の金具を手に取って首を傾げた。きれいに押し込められたバックパックからは、手品のように旅で使うアイテムが次々に現れた。私はそれらをテーブルの上に丁寧に並べた。