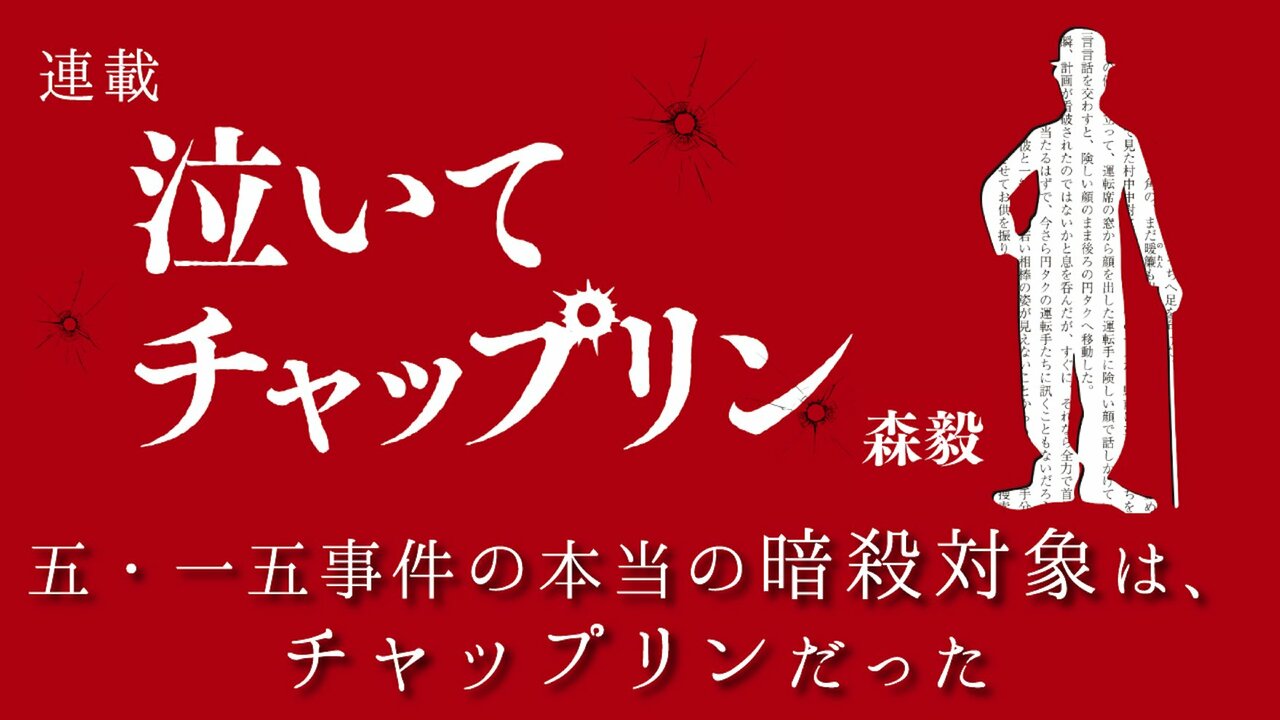クーデターを二日後にひかえ、首謀者橋本欣五郎中佐と長勇少佐の二人が潜伏している築地の待合《金龍亭》に、荒木中将が説得のため、参謀本部に勤務する腹心の部下三名を従えて乗り込んだのは、夜の八時を少し回ったころだった。
木坂も非常呼集された東京憲兵隊の分隊長以下特高班の十名と共に、その黒板塀に囲まれた《金龍亭》の周囲を固め、いつでも飛び込めるよう、邸内の気配に神経を研ぎ澄ましていた。他に援護の人員はいなかった。
明らかに事の重大さを軽視している対応だったが、それは、「内に未曾有の不況をかかえ外に満州事変の処理が急がれている今この非常時に、皇軍の威信にキズをつけぬためにも事が公にならぬよう穏便かつ迅速に解決せよ」という荒木中将の、これも紋切り型の尤(もっと)もらしい至上命令のためであった。
がしかし、その「皇軍の威信にキズをつけぬため」というのは、事件を内々に処理し、要職にある軍首脳の責任問題に発展しないための方便、つまり、ここで首脳たちの責任を追及するより、恩を売っておいたほうが得策という野心家荒木中将の、その後を見据えた打算が働いていたことは想像に難くなかった。
木坂には、日頃から青年将校等と酒を酌み交わし、自慢のカイゼル髭をしごきながら国家改造論をぶっている荒木中将の、その説得ぶりも目に見えるようだった。
「オイ! 貴様らはクーデターを計画しとるそうじゃないか、そんなバカな真似はすぐヤメレ!」と、まずは一喝。
「貴様らが憂国の情やみがたく決起せんとしたことは、よおっく分かっとる。だが事はすでに露見しとるんだ、もう観念せい。
事ここに至ったからには、軍人は軍人らしく潔く旗をおろせ。そうすれば、後のことはけっして悪いようにはせん。
貴様らがここで無様な悪あがきをして、世間に醜態を晒すような真似をしないかぎり、わたしも、きみらの面目が立つよう粉骨砕身(ふんこつさいしん)努力する。
だからきみらも、もう一度頭を冷やしてよおっく考えてくれ。
今や満州の情勢も陸軍を中心に総仕上げの段階にはいっておる。重要にして、かつ寸刻もゆるがせにできない非常時であることは、参謀本部にいるきみらが一番分かっとるはずじゃろ。そのきみらが陸軍の総意に反し、陸軍の足元をすくうような、さらにいえば『統帥大権』を(ないがしろ)にし、恐れ多くも畏(かしこ)くも宸襟(しんきん)を悩まし奉(たてまつ)るような、そんな帝国軍人にあるまじきバカな真似はすぐヤメレ」
と、これまた紋切り型の論法や、「貴様」と「きみ」の使い分けもさることながら、この「ヤメレ」という文法を無視した何処ぞの方言のような日本語は、いうまでもなく「やめろ」という断固とした命令形の角を円くした、笑止といえば笑止、したたかといえばしたたかな荒木流の動詞の変格活用(?)で、それは説得というより懐柔、あからさまにいえば裏取引の折衝といってもいいようなものだった。
待機すること、およそ一時間。
荒木中将以下四人が揃って出てきた。どの顔も入っていった時より険しかった。
すかさず分隊長の伊藤少佐とともに、木坂も駆け寄った。
「次の命令があるまで、二人をしっかり見張っておれ。一歩も外へ出してはならん。
また、だれが来ても荒木閣下の許可なく中に入れてはならん。いいな!」
と、胸に参謀飾緒を輝かせた中佐の一人が鋭くいい放ち、分隊長の復唱も待たず、四人は門前に待たせてあった公用車でサッと消え去った。
荒木閣下十八番の、酒を酌み交わしながらの話し合いも思わしくなかったようだった。
後には車の排気ガスと微かに漂う酒気が残った。
「桜会の連中が来たら、どうするかなあ……」
だれにいうともなく分隊長が困惑顔でいった。
たしかに橋本中佐か長少佐の電話一本で、桜会の少、中佐連中がおっ取り刀で駆けつけてくることは考えるまでもなく、もしもそんなことになったら万事休すだった。
今や、余りに巨大化した帝国陸海軍は、その必然的に抱懐している強固な国家主義と、「国防問題は政治問題に優先する」という内に秘めた伝統的な思想信念、というより、驕り昂ぶったプライドによって他の省庁を威圧し、国政を左右する幕府的存在になっていた。
そしてその王道を行くのが、陸軍にあっては国家防衛の最前線に立つ師団でも連隊でもなく、「三宅坂」といえば通じる宮城の濠に面して鎮座する陸軍省と参謀本部、いわゆる「省部(しょうぶ)」であったが、そこには陸軍のエリート中のエリートが雲集し「省部は国家なり」という自負と驕りが渦巻いていた。
それにひきかえ憲兵隊は、陸軍省に所属し、その補佐をする、いってみれば軍隊の綻びを繕(つくろ)い、陰で支える裏方でしかなかった。
したがって憲兵隊に配属される将校の、軍人としての評価のほども推して知るべしというもので、たとえ同じ階級であっても、省部と憲兵隊では、実質的な格にはライオンと猫ほどの差があり、実直さだけが取得といってもいい伊藤分隊長が困惑するのも当然だった。
だが、そんな憲兵隊でも、第一線で実務にあたっている下士官以下の憲兵は逆だった。
彼等は自ら志願し、所属する連隊からも推薦され、学力体力の厳しい入隊試験をパスし、さらにその後の六カ月間の苛酷な訓練に耐え抜いた兵(つわもの)ばかりだった。
また特高は、さらにその中から選抜された者たちで、司法警察官の資格も取っており、憲兵隊はそういう下士官以下の憲兵によって支えられているといっても過言ではなかった。
とはいっても、陸士を出ていない彼らが昇進することは、名誉の戦死でもしないかぎり道はなく、これもいってみれば、曹長止まりの万年裏方の将棋の駒でしかなかった。
が木坂は、それもまた人の世の定めと、分隊長の困惑顔にも笑顔で応えた。
「そのご心配は明朝までは無用かと思います。ここの電話線は切っておきましたし、事が露見したことも桜会の方々にはまだ知られていないと思いますので。それに荒木閣下としても、今夜中に解決するよう万全を尽くされるでしょう。でないと、事が公になってしまうのは必定ですからね」
「なるほど、電話線をね。さすがに手回しがいいねえ。あ、だが電話が通じないとなると、逆に、あの二人が出かけることになるかもしれんが、その時はどうするか、むしろ、そっちの方が問題だなあ。参謀本部の暴れ馬といわれる二人だし……」
と、分隊長はさらに困惑の色を深めた。
「そうですね。その時は、刀にかけてもお止めしますか」
冗談半分だったが、分隊長は真にうけ、目を剝いた。
「刀にかけても?」
「あ、いえ、それはものの譬えで、そのご心配もまず無用かと思います。
かりにも参謀本部に勤務されるエリートのお二人ですし、すでに事が露見した今、ここでわたしらを相手に大立ち回りを演じるような見苦しい真似はなさらないでしよう」
「むん、それはまあそうかもしれんが、『窮鼠(きゅうそ)猫を嚙む』ともいうし、万が一のことも考えておいたほうがいいのじゃないか? 事敗れたりとなれば 何をするか分からんからな」
「その時は致し方ありません。一歩も外へ出してはならんという命令ですので」
「む、やはり穏やかにというわけにはいかんか……」
「荒木閣下でさえ思い通りにいかなかったご様子でしたし、わたしらもそれ相当の覚悟で当たるしかありませんね。それに、まだ正式な逮捕命令が出ているわけではありませんし、現行犯でもない上官に対し、かりにも干戈(かんか)を交えるような強硬手段におよべば、こちらが先に軍法会議に、ということにもなりかねませんからね」
「私らが軍法会議に?」
と分隊長は、またも目を剝いた。
「ええ、それが軍紀ですので……外へ出してはならんとは命令されましたが、刀にかけてもとは一言もいわれておりませんので」
「いやいや、それは詭弁(きべん)というものだろう」
と、分隊長は生真面目だった。
実直といってもよかったが、世間ではそれを愚直と嘲笑し無能呼ばわりしていた。
況(いわん)や、「軍隊は要領を旨(むね)とすべし」という軍隊においてをや……悲しむべきことだった。