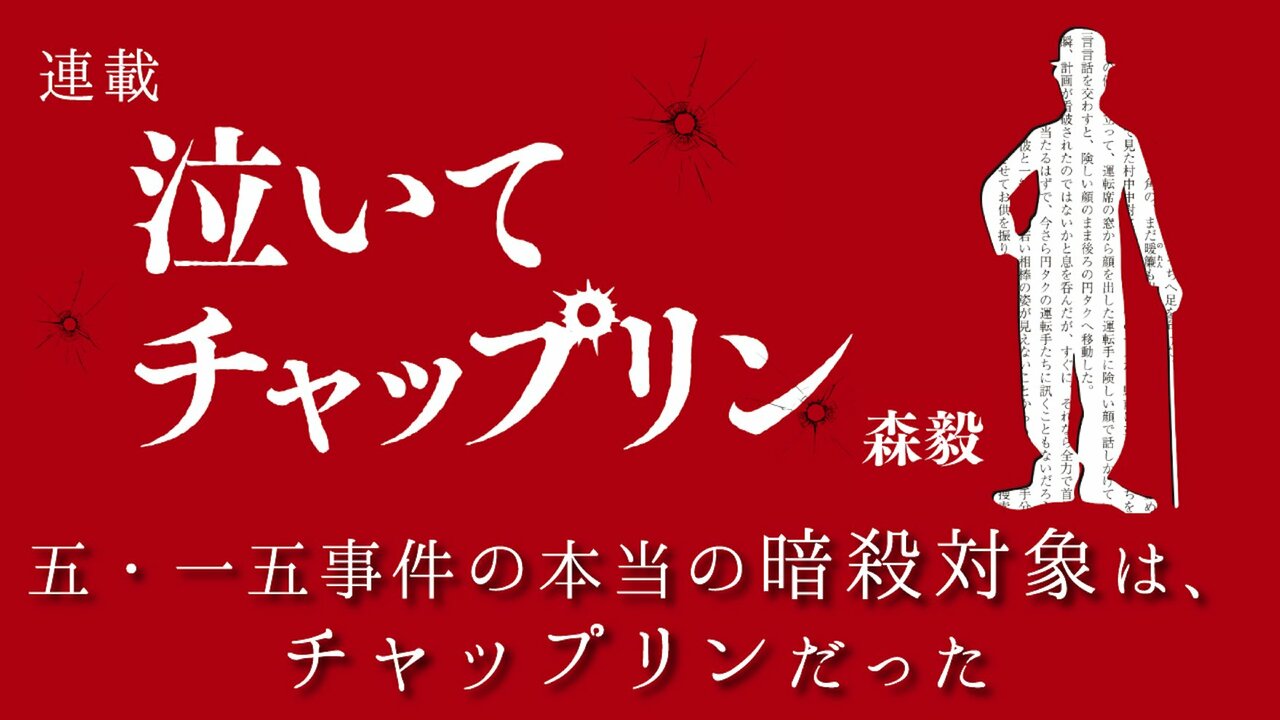四
日中は、市電、乗り合いバス、トラック、それに円タクなどにくわえ、自転車や荷を満載したリヤカーや大八車までが入り乱れて行き交い、それが大震災からの復興と近代化の槌音(つちおと)か進軍ラッパでもあるかのように思える、建設工事やクラクションなど、街の騒音がひっきりなしに飛び交っていた大手町の交差点も、土曜日ということもあり、八時を過ぎたばかりだというのに道往く人も稀だった。
またその周辺の、今は窓の灯も消えた商社や銀行の幾何学的でモダンなビルが、奇跡的ともいわれる復興を誇示しているかのように夜空に黒々と聳(そび)えていたが、これも昼間の光景とは裏腹に、近代化の負の側面、すなわち破壊と建設による伝統文化と人心の荒廃を象徴する巨大な墓石が林立しているように見えなくもなかった。
時に、見るからに無機質な冷えびえとしたビルの谷間を吹き抜けてくる、季節はずれの北風に街路樹の梢の若葉もふるえていた。
木坂曹長はハンチングを目深にかぶり、草臥(くたび)れた三つ揃いのうえに、これまたそれ以上に年季のはいった薄ねずみ色のレインコートを羽織り、夜の底に沈んだ大都会の交差点の一角に立っていた。
むろん軍隊は、服装についても厳格な規律があったが、特高だけは、張り込み、尾行、時には日雇い労働者に変装することもある特殊な任務柄、そうした私服での勤務も許されていた。ことにレインコートは、急な雨風や夜露を凌ぐための必需品で、いってみればそれが制服のようなものだった。
とはいえ、公式の会議や式典に出席するときには、帝国陸軍の軍人として軍服を着用しなければならなかったが、この道二十年、今では軍服姿の木坂曹長を想像するのは容(たやす)易いことではなかった。どう見ても係長どまりの官吏か、ウダツの上がらぬサラリーマンといったところだった。
が、時にはそれが思わぬ功を奏することもあった。
ビルの谷間を吹き抜けてくる風に耐えながら佇むこと、およそ十五分。
やっと円タクを捕まえることができた。
日中は目にあまるほど行き交っていた円タクは何処へ消えてしまったのか、その十五分間に目にした円タクは、わずかに五、六台だった。しかもシャクなことに空車は一台もなく、呼び止めようと上げた手を嘲(あざ)笑うように、目の前を風のように走り去っていった。得てして待っている時にはそんなものだった。
「土曜日だというのに、寒いなか大分待ちぼうけを喰わされたようで、『花のサラリーマン』も楽じゃありませんねえ」
と、やはり相当に年季の入ったハンチングを被った木坂と同年代の運転手が、乗り込んだ木坂をバックミラーで覗き見ながらお愛想をいった。
「花のサラリーマンといわれるほど若くはないが、そんなことが分かるのかね?」
木坂も半分お付き合いで笑って応じた。
「いえ、ネタを明かせば身も蓋もない話ですがね。さっき東京駅までのお客さんを乗せてここを通ったときに、手を上げた旦那さんを見たんですよ」
と、運転手は正直だった。
「なるほどね。どんなことにも、それなりのウラがあるというわけだ」
「ええ、まあ大概のことはそういうもんですからね……で、どちらまでですか?」
「千駄ヶ谷(せんだがや)の駅の近くなんだが、何分ぐらいかかるかな?」
「まあ二十分てとこですかね……なんでしたら、もうちょい飛ばしましょうか?」
「いや、べつにそれほど急いでるわけじゃないから……ああ、そうか、今日は土曜日で、円タクの稼ぎ時だからチンタラ走るわけにもいかないのかな?」
「いえ、べつにそういうわけせられたあげくに、大分待ちぼうけを喰わされたようなんで、お急ぎじゃないかと思って……あたしの方は、チンタラ走ろうが飛ばそうが大した変わりはないんで。なんせこの不景気ですからね。きょう日はもう、土曜も日曜もあったもんじゃないですからね、ほんとに」
と、運転手は車を発進させギアチェンジをしながら、またバックミラーを覗きこんだ。
「でも、円タクは別じゃないのかい。きみも見た通り、わたしがあそこで立っていた間に円タクも何台か通ったけど、空車は一台もなかったよ」
「そりゃあ旦那さん、あんなところでいくら待ってても、歌の文句じゃありませんが、『宵待ち草のやるせなさ』っていうやつで、お役所も会社も退ひけちまった土曜日の夜に、人けどころか、野良犬一匹いない大手町を流してるノーテンキな(やっこ)さんはいませんからね。まあ、そういうわけで、も一つネタを明かせば、旦那さんがまだここらで待ちぼうけを喰わされているんじゃないかと、それで急いでトンボ返りしてきたってわけです。
わたしらも心底ノホホンと構えていたんじゃ、それこそアゴが干上がっちゃいますからね。いえ冗談抜きで、ほんとに」
と、運転手はバックミラーの中で笑った。
「なるほど、『道によって賢し』で、それにもやはり、それなりのウラがあるというわけだ。
たしかに土曜日の夜に、こんな人気(ひとけ)のない大手町あたりをチンタラ流してるより、新宿や、《吉原(よしわら)》を控えた浅草あたりの盛り場へ行ったほうが稼げるだろうからね」
と、木坂も笑った。
「いえ、ところがどっこい、世の中そうそう甘くないんですよね。ま、旦那さんもご存知でしょうが、近頃はその《吉原》でさえ閑古鳥ならぬ、白粉首(おしろいくび)を並べた『張見世(はりみせ)』の姐(ねえ)さんたちが泣いてるって体たらくですからね、ほんとに」
と、ここにきて運転手はすっかりうちとけた調子でいった。
「ほう、吉原もそんなにひどいのかね。わたしも、もう花のサラリーマンといわれる歳ではなし、近頃はそっちの方角にはトンとご無沙汰でね……しかもこの不景気だからね」
「たしかに。歳はともかく不景気のほうは、あたしらも同じで、今に円タクの屋根にも、ペンペン草がボーボーなんてことになりかねないでしょうね。
いえ冗談抜きで、嘘だと思うなら、東京駅や新宿の駅前広場へ行ってごらんになれば、それが洒落(しゃれ)や冗談でないってことが一目で分かりますよ。
主(おも)だった駅や盛り場には、昼といわず夜といわず、客待ちの円タクが、それこそ『待てど暮らせど出ぬ月を』じゃありませんが、煙草吹かしながらバカ面してトグロを巻いてますからね。いえ、ほんとに」
と運転手は、今度は真剣な眼差しをバックミラーに映した。
「ほう、トグロをね。なるほど……」
と、木坂は苦笑し感心もした。
円タクの運転手の中には「雲助」と忌(い)み嫌われ、その昔の、箱根の山の駕籠かきに譬(たと)えられるようなタチの悪い連中もゴロゴロしていたが、そんな連中が昼なお暗き箱根の山中ならぬ、帝都東京のど真ん中でトグロを巻いているというのは、遮二無二近代化を急ぐ日本社会の歪(ひずみ)を描いた風刺漫画の格好のネタになるような話で、云い得て妙であり、あらためて苦笑した。
「いえね、そういってるあたしも、また今夜も新宿辺でトグロを巻いてるって寸法ですからね。まったく笑っちゃいますよ、ほんとに」
と、自嘲するような投げやりな口調でいった。
あるいは、彼はそこでトグロを巻いている己の姿を醒めた思いで想い描いていたのかもしれないと、木坂はちょっぴり同情した。
「だったら、何もわざわざ新宿へ戻らなくても、東京駅でいいんじゃないの?」
「いえ、あたしはもっぱら新宿界隈を拠点にしているんで。そっちには気心の知れた仲間もいますからね。それにトグロを巻いているのも十分や二十分ならどうってことはないですが、まあ一時間、へたすると二時間ですからね。知らない連中のなかにはいって煙草ばかり吹かしていたって気が滅入っちゃうばかりで、仲間とバカいい合ってりゃちょっとは気が紛れるってもんですよ……それにしても、この不景気風は、いったい何時までつづくんでしょうかねえ、ほんとに」
と運転手は、またバックミラーのなかで苦笑した。
「なあに、もうすこしの辛抱だよ。あれほどの大震災から、わずか十年で東京も見違えるような東洋一の大都会に復興したんだ。すぐにまた本当に笑えるような世の中になるさ」
と木坂も、気休めにもならないような気休めをいって苦笑した。
にしても、「円タクが駅前広場でトグロを巻いている」という話はちょっと面白かった。
たんなる冗談にしても、風刺を効かせた比喩としても。
十分後。
木坂は千駄ヶ谷の閑静な住宅街の一角にある、西田税(みつぎ)元陸軍少尉の家の前に立っていた。