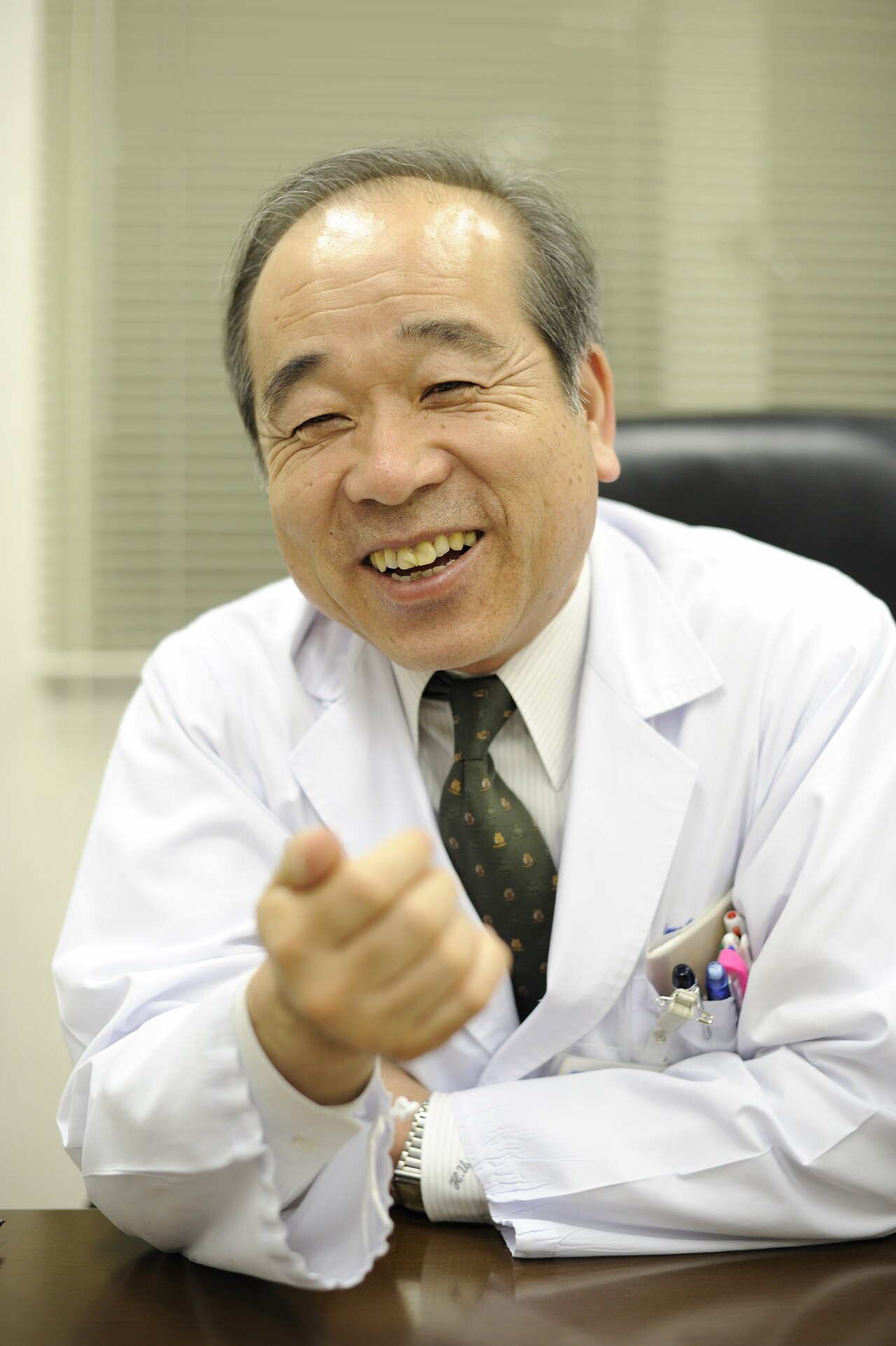ある日、いつものように梅澤がギターを隠し持って彼女の病室を訪れると、4人の患者のカーテンが全部開け放たれていた。そして、4人の患者が全員、ベッドの上で正座していた。びっくりしている梅澤に、彼女が、「みなさん、先生の歌を聴きたいって言っておられます。それで、みんなで待っていたんですよ」と言った。
「え〜、本当ですか? やっぱり、バレてたんですね。本当にいいんですか?」
梅澤の問いに、同室の患者が口々に、
「勿論です!」
「お願いします!」
「楽しみにしてたんですよ!」
「岡本さんだけズルいって思ってました!」と返事をした。
梅澤は、照れながらも、「それじゃ」と言って歌いだした。一曲終わるごとに四人の患者が、周りを憚ることなく音の出る拍手をしてくれた。梅澤は、最後に、自分の一番好きな「悲しくてやりきれない」を歌った。4人の患者が、それぞれの思いを胸に
歌を聴いているのがわかった。
「そろそろ、看護師さんが検温に回ってこられますよね。それじゃ、今日はこのくらいで。また、来ます」
梅澤は、ギターを白衣の中に隠して病室を出て行った。4カ月の第3内科での研修が過ぎていった。研修最後の日に、梅澤は受け持ち患者に挨拶に回った。最後に岡本を訪れた。彼女は、梅澤の挨拶を神妙に聴いていた。
そして最後に、「先生の顔を触らせていただけませんか?」と尋ねた。梅澤が
「いいですよ」と答えると、彼女は、恐る恐る両手を梅澤の方に伸ばして、両頰に触れた。まるで彫り物の全体像を確かめるように、その手でゆっくりと、耳、眉毛、目、鼻、口と触っていった。
そして、「ありがとうございました。想像していた通りの先生でした」と告げた。
梅澤はまじまじと岡本の顔を見つめていた。見開いてはいるが、彼女の目は、目の前の光景を見る事が出来ない。しかし、彼女には梅澤の顔が見えているのだろうと思った。
何か励ましの言葉をかけなければと思いながら、時間が過ぎていった。むしろ、言葉を発すると、これまで培った時間や感情が萎んでしまうように思えた。
「じゃ、行きます」
梅澤は、それだけしか言えず、岡本の部屋を後にした。
古い京帝大附属病院の病室にはクーラーが無く、吹き込む風が唯一の涼しさであった。窓の外には楡の葉が生い茂り、セミが煩く鳴いていた。