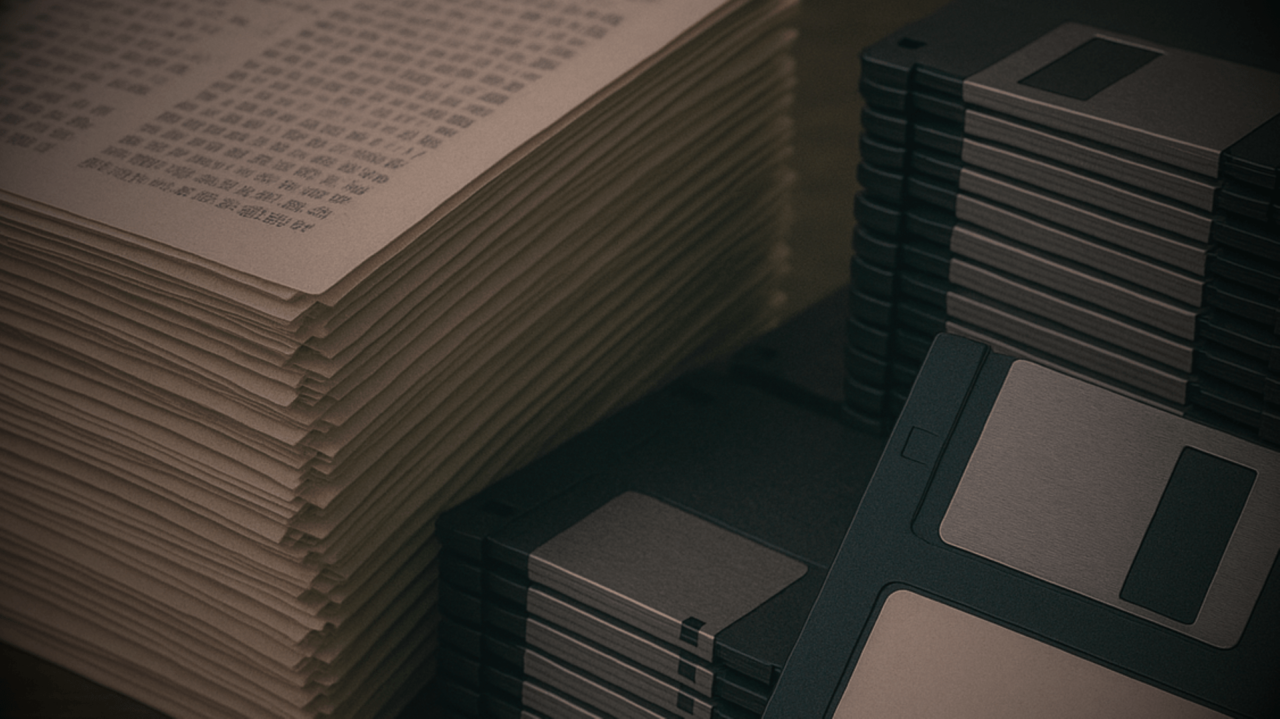実は、昭和40年の夏の甲子園準優勝投手、木樽正明氏も、とあるTV番組で、「昭和40年の夏の大会前に行われる春季大会準決勝で、習志野と当たり、その時、習志野の主砲、谷沢健一(中日)に決勝点となるホームランを打たれて負けると、斎藤監督は明るいうちに銚子市に帰ると市民から罵声を浴びせられることがわかっていたから、暗くなってから汽車に乗って帰った」と回想している。
これは、銚子市民が一丸となって銚子商野球部を応援し、愛着があるからこそ出る表現に違いなかった。しかし、期待が大きい分、負けるとこのような仕打ちが待っている。この「勝てば官軍、負ければ賊軍」という現象は、ある種、銚子商の「歴史」の一部であった。
この歴史的大敗を経て、斎藤監督と銚子商野球部は、この汚名を返上すべく、同時期に幾度も対戦した球史に残る大投手をターゲットに打倒を誓った。この前年の昭和47年。
銚子商野球部を語る上で、最も重要な「宿敵」の一人である、作新学院高校、江川 卓投手である。江川投手と銚子商の戦いの歴史は、昭和47年の秋から始まる。その時すでに江川投手はおひざ元、栃木県で「怪物」にふさわしい活躍と成績を残していた。公式戦だけで完全試合2回、ノーヒットノーランが7回というすさまじい記録である。
斎藤監督は、昭和47年の秋季大会で完璧に抑えられた相手との再戦を待ち望み、在籍する選手の底上げのために限られた時間で鍛え上げ、そして、一人の「天才打者」が銚子商に入学するのを待った。その選手こそ、後に読売ジャイアンツで、2度の首位打者に輝き、怪物のチームメイトとなる篠塚利夫(のち和典)である。
篠塚は、斎藤監督の古巣でもある銚子第一中学校出身であり、銚子市内では、その選手としての才能と能力は知られた存在だった。斎藤監督は、どうしても篠塚が欲しかった。それは、打倒江川だけではなく、その先の全銚子市民が待ち望んだ、「全国優勝」のために。
そして、昭和48年の4月。銚子市を沸かせていた天才打者は、銚子商という地元の星と、地元の英雄である名将の下に、選手として入学する。この銚子商と作新、江川投手との戦いの歴史の中で、一度目の対戦は、前年の昭和47年の秋季大会における関東大会での対決だ。この時、銚子商は、9回を1安打20奪三振と力の違いを見せ付けられ完敗(スコアは4-0)。
この1安打は、当時銚子商で5番を打っており、過去5度の対戦で江川投手から最もヒットを打ち、チーム内で「江川キラー」と呼ばれた青野達也の1本だった。