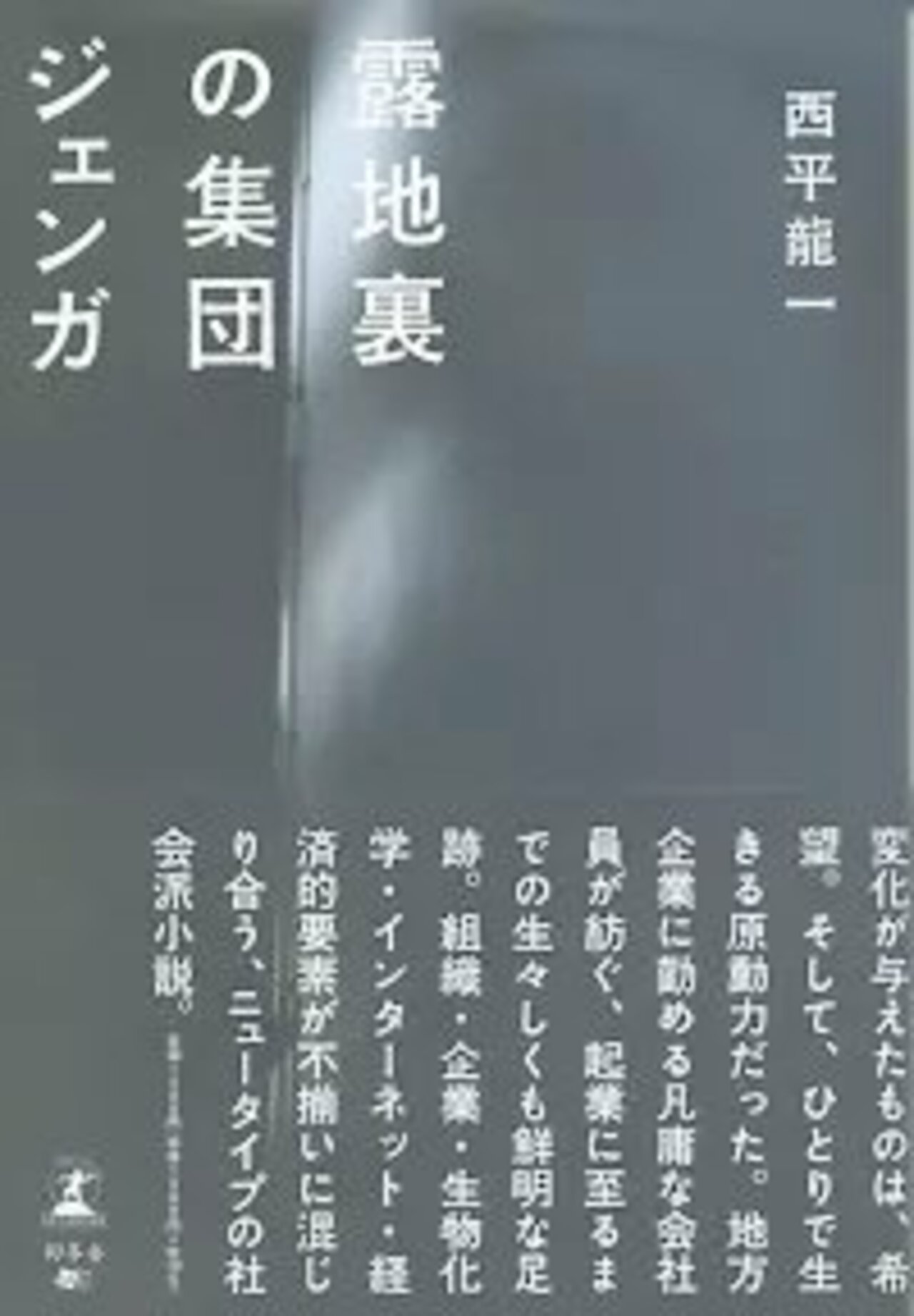「ナツはね。こういう話をしっかり聞こうとしないからダメなのよ。意識が低い女はダメな女なんだよ。だからナツって男ができないのよ。ユウ聞いてよ。私ナツのためにいってるんだよ」
鉤鼻に皺を寄せて、エリカが言った。ナツの頬が初めて引きつった。
「私はエリカと違って仕事ばっかで出会いがないのよ。トリミングにくる男はね。大抵もう家族がいるんだからね」
ナツの口調は強かった。グラスをギュッと両手で握りしめている。
「出会いがないってさ。それは自分でそういう状況つくってんじゃん。ナツの場合仕事のせいにしてるけど、そうじゃないんだよね。いつも生理前にさ。前の彼氏に連絡する癖があるじゃん。それって女として向上心がないだけでしょ。やめちゃえばいいのに」
「はあ? 向上心って何よ。フリーターのあんたにいわれたくないんですけど」
ナツは余った手もとの割り箸をエリカに投げつけて、グラスを持つ手も振り上げた。僕は肘を押さえて、立ち上がったナツを座らせた。両肩が怒りで小刻みに震えている。
床の割り箸を拾うために視線を落とすと、森はまだ、勃起していた。スキニーパンツの股間の部分はテントのように張っていて、そしてシャツから小さな突端の輪郭が浮いていた。エリカは森の耳朶に不安定な視線を注いでいる。そしてみずみずしく赤色に染まった唇を、舌の先で円を描くように舐めていた。
「やめちゃえば。ってどっちの意味なのよ」
ナツはまだ小さく震えていた。僕も酷く腹が立っているようだった。森はエリカに促すように、空の缶を振ってみせた。エリカは頷いて、キッチンに向かって小走りをする。背後を駆け抜けるエリカからは、腐った脂と香水が混じった臭いが漂った。裸足の爪は小豆色のネイルが施されていて、シバンムシの塊に見えている。
「伝え方はよくないけどさ。エリカの意見も一理あると思うよ」
森は真っ直ぐナツを見た。ナツは又、グラスを両手で握りしめた。
「きれいになりたいって女の本能でしょ。古墳の埴輪にも化粧がされていたとかよくいうしね。ずっと続いているから拒みきれない文化なんだよ。男は競争にこだわる、とかさ。これも本能なんだよね。俺もなんで出世したいのか説明してくれっていわれてもね。それはうまくできないものなんだよ。だってね。それは個性じゃなくて文化だからさ。それはね、きっと遺伝子レベルで組み込まれているんだよ。だからさ、それに俺たちは従ったほうが賢いと思うんだよね」
森の口角がゆっくり上がった。ナツは握ったグラスから手を離して、まるで観念でもしたかのように、力なくゆっくり頷いた。エリカが戻ってきた。頬は紅潮していて、絢爛な目は、蝋のようにドロンと溶けているように見えた。
そして、「ホンノウホンノウ・ブンカブンカ・イデンシイデンシ」と、拳を突き上げ、リズミカルに叫んでいる。森はそれを見て、手を叩いて嘲笑した。そして僕に手招きをして、ちょっとビールが足りなくなって。そう言って外へ誘った。
テーブルの上には、エリカの運んだ缶のビールが何本も乱雑に並んでいるのに。