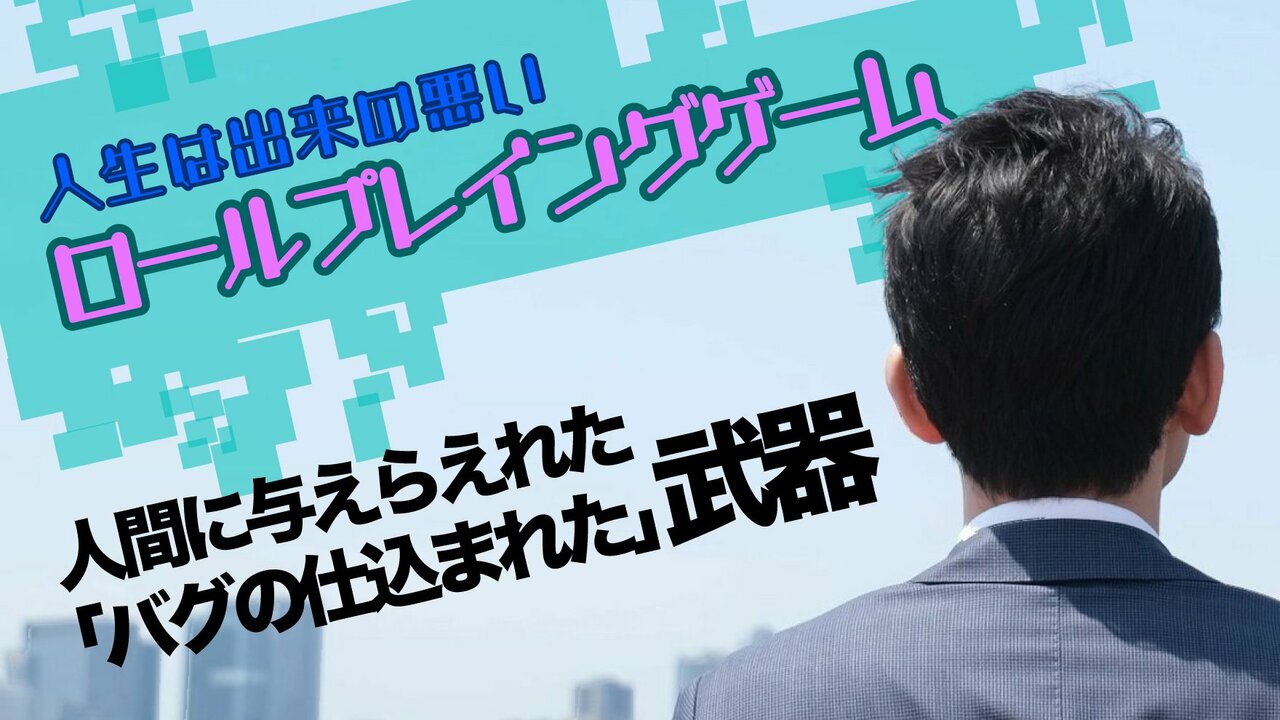六月二十八日(横浜市港北区)
「おとーさん、おかえりー!!」
玄関の重い扉を開けると、待っていましたと言わんばかりに、両手を目いっぱいに広げた娘が待ち構えていた。彼女は鍵を差す音で私の帰宅を察知する。そして、いつも仔犬のように駆けつけてくるのだ。
「ただいま、栞」
全身を預けて飛び込んでくる娘を、私は両ひざをついてしっかりと受け止め、片手に収まる小さな頭をポンポンと撫でた。そして、娘を抱え上げると、そのまま廊下を抜けてリビングへ向かう。栞はキャッキャ言いながら、宙に泳がせた手足をバタバタさせている。四歳児のコンパクトな体にぎっしりと詰まった生命の柔らかい重みが、腕に心地よく伝わってきた。
「おかえりなさい、今日は早かったわね。お疲れ様でした」
クリーム色のエプロンを着けた真子が、慣れた手つきでル・クルーゼの鍋をゆっくりとかき混ぜている。ビーフシチューの香ばしい匂いが、ふんわりと部屋の中に漂っていた。
「おとーさん、見て、見て。今日ね、幼稚園でこれ作ったの。先生にとーっても褒められたんだよ」
手提げ鞄をソファーに置いてネクタイを緩める私の腕を、栞がしきりに引っ張る。その小さな手には、さらに小さな赤と緑の折り紙が握られていた。それが花であると理解するのに一瞬の時間を要した。
「お、これはチューリップかな。上手に作れて偉いぞ、栞」
「でしょー」
どうやら正解だったようだ。娘を傷つけずに済んで、私は少し安堵した。栞は満足そうににっこりと笑って、今にもちぎれそうな折り紙の花を振り回しながらキャーッと嬌声を上げて部屋の奥へと駆けて行った。「もう夜だから、おうちの中で走らないの!!」という真子の声が、娘の後ろを追いかける。
五年前に三十五年ローンを組んで購入したベッドタウンの新築マンションは、私たちと同世代の夫婦が多く、栞と同年代の子供たちで溢れている。
幼稚園や小学校が終わる夕方以降は、最新の防音構造という謳い文句がウソのようにあちこちから子供たちの笑い声や泣き声、ドタバタと走り回る音が響いてきて、建物全体が一つの大きな楽器みたいになる。
最寄駅まで多少遠いことさえ気にしなければ、近所には学校、小児科、公園、スーパーといった子育てに必要なもろもろが過不足なく揃っていて、住環境にこれといった不満は無い。マンションを分譲した不動産会社は、もともと私たちのような家族層をターゲットとしていたに違いない。
「もうすぐご飯の準備ができるから、早く手を洗って着替えてらっしゃい」
妻がシチューをよそいながら言った。シミ一つない真っ白なシステムキッチンには、大中小、三枚の皿が仲良く並んでいる。