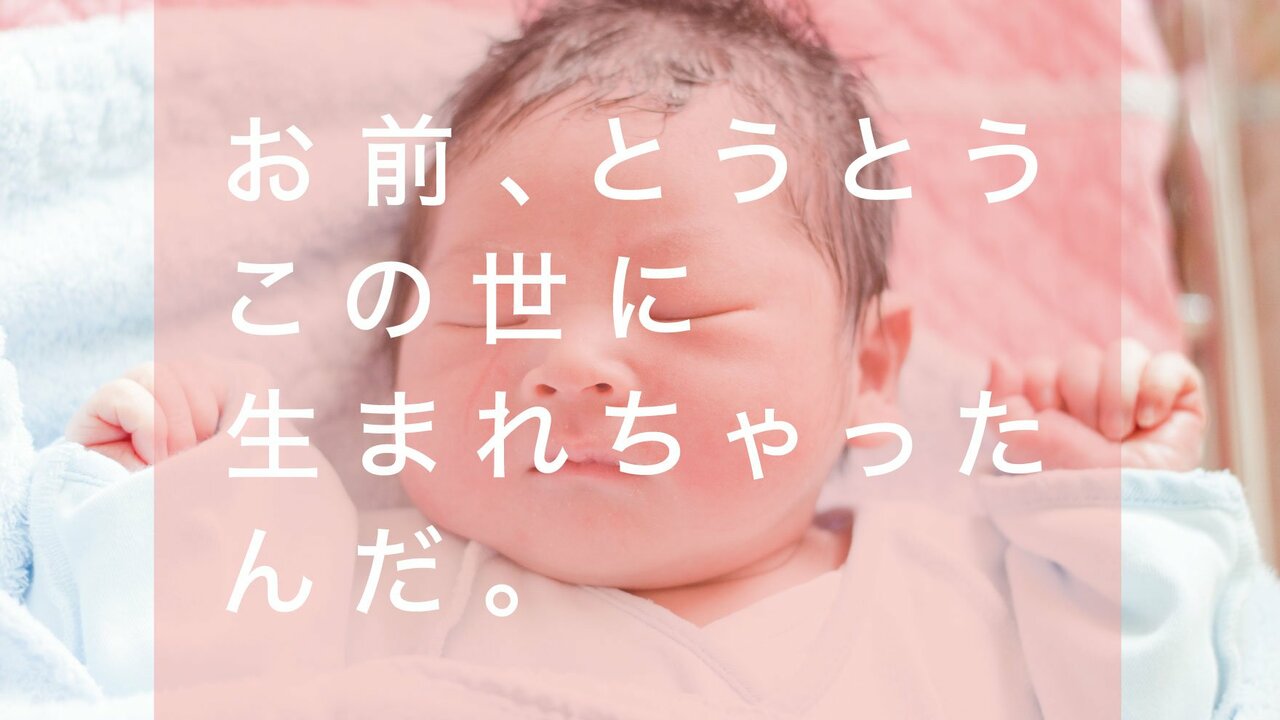室町の父からの電話
独りは何がいいって、感情にどっぷり身を任せてしまえることだ。やまびこが窓に移す流体の残像さえ面白くてときめいてくる。那須塩原で下りてタクシーに乗るとそわそわして、チーズケーキの保冷剤を確かめたり、ストールを気にしたり、腰の線が気になったり、窶れて見えるのじゃないかと気後れしたり。木立の中の古風な山荘の玄関でノッカーに手を掛けた時は急に留守のような不安に襲われた。後退る。
ドアが内開きに開いて、生方本人が立っている。瞠った眼が少し窪んで、ドアに掛けた手が蒼白で、枯れ木のように冬物らしいセーターの肩と胸が細って見えた。とてもゆっくり
「室町淳」
と呼んだ。腕を伸ばして淳の手を掴んで引き入れるのも非力で
「本当かい?」
中に入ってもまじまじと顔を探って、いきなり抱きしめた。頭を胸に抱いて、いつまでも、立っているのが苦しくなるまで。
「入り給え。このとおり病み上がりで、立っているのも疲れるんだ」
ソファに掛けさせようとして、思い直したように部屋を横切って奥へ奥へ引っ張って行って、躰二つごとベッドに倒れ込んだ。長い時間じっとしていた。不思議に淳も苦しくなかった。むしろ心が軽く明るくなっていくようだった。
リヴィングに戻ってからもソファで凭れ合ったままじっとしていた。
少し寒いように思ったとき、生方も躰を起こして、夜は涼し過ぎるんだと言った。
「ひどいもてなしようだ。あれ以来の嬉しい賓客なのに」
「いいえ、お見舞いだから」
「いいものを頂けるようだ」
茶を淹れようとして
「だが、もうこの時間だね。一食抜いてしまった。お持たせはあとにとっておいて、食事にしよう」
「お見舞いにならないわ。先生はどうぞしっかりお上がりになって」
生方は眉根を険しくして
「先生じゃないよ」
あの時もそうだった。
「……生方さん」
「違う」
「……草太さん……」
「まあまあ。さんがないのがいい」
あの時のままの遣り取り。
生方は沈んで