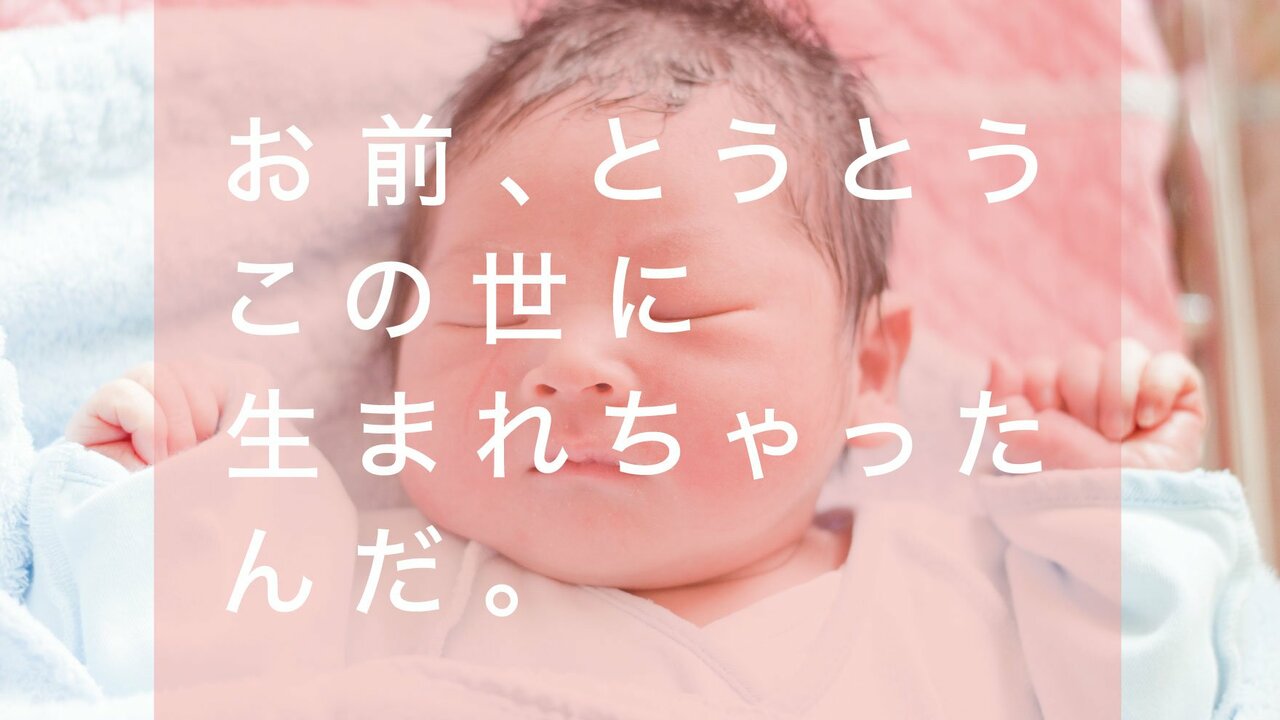忘れもしない。シラバスだけで学生が集まった最初の日、教壇を下りて通路を廻りながらそれとなく新人を観察するのだが、この子は窓側の通路の端の席にいて少々注意散漫な高校生みたいな印象だった。僕の翳が射して慌てて頬杖の手を引っ込めようとした。
どじだ、小さいものを落とした。拾ってみると岩波の文庫本で、カバーをかけてあったが中は隈取りしたように焼けた鈴木信太郎譯のヴァレリー詩集で、スピンが挟んであったのは『海邊の墓地』。旋毛を見下ろして、女の子にはまだ理解できないよと本気と意地悪で言ったら耳朶が真っ赤になって、小さい声でわかろうと努力していますと応じた。真っ直ぐは痛ましい。
学部は?
「いつもあの通路の端の席で……時々友だちがいっしょで……男子も……毎回一度はあの通路を歩きながら病跡学を講義した……」
狂人と天才と犯罪者と君が、精神の病のせいでそういうことをしたのか、その病にもかかわらずそういうことをしたのか、病がそういうことをしたのか。病跡学は胡乱な学だ。精神医学全体の怪しさの鏡だ。人の、君の、怪しさに気が付くよ。なんて若僧が言っていた。
「何度も……お部屋の前を通りました。もし廊下で見つかったらとどきどきしながら」
「そうだったのか。それは可哀想だった」
「信じられなくて……ここには素敵な女性の先生方もいらっしゃるし……わたしは子供で……洗練された……恋の作法……を知らないし……今だって……」
「凄いね、恋の作法……僕だって知らない」
「お別れのご挨拶を……」
「だめだよ。僕が狡かった……君から誘わせたくて……僕のせいで幸せな恋を二年間ふいにした……」